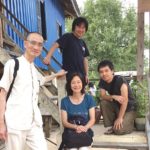「本屋は伝統を壊していかなければ存続が難しい」
「京都に来た私に本屋のあり方の可能性を広げてくれた『ホホホ座浄土寺店』というお店がある」
シリーズ第1回で聞いた、本屋『CAVABOOKS』の店主・宮迫さんの言葉が心に残る。
そもそも、京都の本屋の伝統って何だろう?
京都は、日本の古いものを残していく街だから。
昔からあるものを価値化して大切にしていく街だから。
「だから京都にある本屋も、伝統にこだわりがあるはずだ」と、私が思い込んでいただけじゃないだろうか。
次に訪れた本屋・『ホホホ座浄土寺店』の山下賢二さんは、京都出身であり昔からある京都の本屋を知りつつも、自らが営む店を「本が多いおみやげ屋さん」と話しているそうだ。
京都出身でこだわりがあるなら、軽々しい気持ちでいろいろと話してはいけないのかもしれない。そう覚悟した私の心をほぐすように、山下さんはフランクに出迎えてくれた。
「ネット書店だと目的の本をワンクリックで買える。でも実店舗なら、目的の外にある本とも出会える。今はネットがあるから、実店舗はいらないって言う人もいるけど、実際になくなったら街の余白がなくなり、寂しくて窮屈な地域になると思いますね」
そう話す山下さんと『ホホホ座浄土寺店』の背景は、聞けば聞くほど追ってみたくなるものだった。
※本記事は内容に不備があったため、2022年11月31日に修正して再投稿しております。
昭和50年代の立ち読み小僧が本屋の店主に
時は昭和50年代にさかのぼる。
なかなか本屋から出ようとしない少年がいた。
いっしょに来ている友達は「早く帰ろう」と言うが、少年はずっと立ち読みをしている。
夕方になり、少年の家では母親が帰りの遅い息子に対して「あの子、また……」と思い、近所の本屋に電話をかけると、店主は「息子さんいますよ。帰らせますね」と答えた。

約40年後、少年は「新しいかたちの町の本屋」を目指す『ホホホ座浄土寺店』という本屋の店主になっていた。名前は山下賢二さん。当時を振り返りつつ、こう語る。
「本屋は、小学生の僕にとってものすごい刺激空間でした。色々な世界への扉が棚に並んでいる感じ。今でいうインターネットのURLのようなもので、それを片っ端からクリックしていくような感じで立ち読みしてました」
本は、異なる時代、異なる世界に飛んでいける場所であり、子どもだった山下さんにとって現実逃避ができる場所でもあった。
しかし時代は移りゆく。
山下さんは昭和50年代から現在まで、本屋のあり方がどう変わってきたのか教えてくれた。
「町の本屋は、取次を介して送られてきた本をうまく並べれば、それで営業できていた時代がありました。ところがバブルの頃あたりから、在庫量で売るメガ書店ができ、そのチェーン店ができ、その後、インターネットで直接、本を買えるようにもなってきて、個人の町の本屋は自然淘汰されていきました。そして、そのアンチテーゼのようなかたちで店主自らが選書して本以外の雑貨も置く個人書店が生まれた背景があります。が、今はさらに時代が進んで、その選書しているはずの本屋が似たような品ぞろえになってきている(笑)」
ネット書店。
メガ書店。
個人書店。
三種類の書店がせめぎ合い、客が自分の行く本屋を選べる時代になった。
対面で本を売り、自分の感性で空間を作る楽しさ

本屋のかたちが変わっていく一方で、大人になった山下さんは京都を離れ上京した。
さまざまなアルバイトや出版社での編集職を経て、ある古本屋の初代店長になった。
「そこで、対面の商売で自分の感性で空間を作るおもしろさに目覚めたんです。それが子ども時代の本屋との思い出につながりました」
やっぱり自分は、本を売る仕事がしたい。
同時期にさまざまな要素が重なった。地元の京都で子育てしたい、親が病気になった……山下さんは京都に戻って2004年に『ガケ書房』という本屋を立ち上げた。いまの『ホホホ座浄土寺店』の前身である。
「実は東京にいたころから、自費出版で仲間とガケ書房という出版チームで『ハイキーン』という雑誌を第3号まで出していたんですよ。今で言うリトルプレス(自主制作の出版物)ですね。それをそのまま店名にしました」
やがて11年間継続した『ガケ書房』は店名と場所を変え『ホホホ座浄土寺店』になり、地元の住民がスーパーの帰りに足を運んだり、個性的な本屋があると聞きつけた観光客が京都駅からバスに乗って足を運んだりする本屋になった。
店内はいろいろなものが置いてあって、雑貨やお菓子もあった。見ているだけで楽しい気持ちになるが、山下さんはあえて雑然とした雰囲気にしている。

そこには、自分の営む本屋を敷居の高い場所にしたくないという思いがあった。
本屋は公園のような存在
「誰でも、どんな服装でも気軽に入れる雰囲気の本屋にしてるんです。老若男女、貧富の差なく気軽に入れる。昔の町の本屋はそんな場所だったんですよね。『ホホホ座浄土寺店』もそんな感じの本屋でいたい。公園のような。僕はその公園の管理人で、お客さんはときどき本を買うことで公園の管理費を払ってもらっているような感覚でいます」
だが、届いた本を並べるだけだと今は寂れていく時代だ。
山下さんは、実際にはどのようなことをしているのだろうか。
「コロナ前年の2019年、僕は公私ともに最悪の状況だったんです。『ホホホ座浄土寺店』を持ち直すために、今後はどんどんいろいろな挑戦をしていこうと決めて始めた事業のひとつが本の宅配です。届け先が京都市内であれば1冊から宅配料無料で届けています。でも実は本の宅配というのは、昔ながらの町の本屋がしていたことなんです。僕は「これからの本屋」ではなく「これまでの本屋」の良かったところをいつも見ていたいです」
思いがけず2020年に新型コロナが流行して、宅配を頼む人が増えた。インターネットで『ホホホ座浄土寺店』が選んだ本を買う人も激増し、店頭まで本を買いに来る人もそこまで減らなかった。また、全国一律の給付金や条件の緩くなった様々な貸付も店の状況を好転させるに十分な要素だった。
「天変地異が起きて、もぐっていた地下からぴょこんと顔を出したような感覚でした。もちろんコロナは僕も大嫌いですよ。だけどそれとは別に、業績は上がっていきました」
これは『ホホホ座浄土寺店』に限った話ではなく、京都の多くの本屋に当てはまるという。さまざまな京都の書店が、存続に向けて挑戦をし続けた結果とも言えるだろう。
お客さんの喜ぶ顔を思い浮かべて本を選ぶ

新しい本屋のかたちを取り入れる一方で山下さんには、『ガケ書房』を開店したころから変わらない気持ちがある。
「僕がいちばん大切にしているのは、お客さんの顔を想像しながら選書をすることなんです。『ホホホ座浄土寺店』は、本の多いお土産屋と名乗っているんですが、お土産というのは京都のお土産という意味ではありません。お客さんが買った本が、例えば東京に関する本であっても、『ホホホ座浄土寺店』で買えばそれはお土産になるってことなんです」
お客さんが自宅に戻り、買った本を本棚に並べる。お客さんはそれを見たときに『ホホホ座浄土寺店』のことを思い出すかもしれない。例えば「あの日、京都駅からバスに揺られて行ったなあ。途中で彼氏とケンカしたなぁ」といった、道のりを含む「場所の記憶」がそこで蘇るのだ。
山下さんは、自ら選書をして注文した本が届いたとき、いつも嬉しくなるそうだ。そしてその本をお客さんがレジに持って来ると、ますます喜びは増す。
そんな山下さんは最近、新たに選書での通信販売を始めた。
3000円、5000円、10000円とコースが分かれていて、お客さんの年齢・職業・好みだけを聞いて本を選ぶというものだ。「3000円からなら私もやってみたい。それが面白ければ、次は5000円にしようかな」と思えそうだ。
「本を選ぶためにお客さんがくれた情報でプロファイリングするんです。これがなかなか難しくて、たとえば一言で音楽が好きだと言っても、人によってジャンルが違いますから。でも難しい分、お客さんと想像力で対話しているようで面白いです」
誰もが気軽に入れる、新しいかたちの町の本屋さん。
京都駅から遠くても、その本屋を訪れるためにバスに乗る観光客も多い。
今日も『ホホホ座浄土寺店』は、それを体現するためにチャレンジを続ける。
第1回の『CAVABOOKS』、今回の『ホホホ座浄土寺店』、そして……次は。
京都には、2010年にイギリスのガーディアン誌が発表した「世界で一番美しい本屋10」に日本で唯一選ばれた本屋があるという。
変化する京都の本屋シリーズ。
最終回は、そこに向かってみようと思った。
あわせて読みたい