ひとりで生きる それは簡単 簡単だけど許されないのか
(「独房暮らし」ザ・クロマニヨンズ)
人が職場を辞めるとき、その理由としてもっとも多く挙げられるのが「人間関係」だといいます。
人間は「社会(ポリス)的動物」と定義したのは古代ギリシャの哲学者。とても簡単に言うと、「ひとりひとりが気持ちよく暮らしたいと考えている。そんなひとりひとりによってできる集団は気持ちよく暮らすためのものになる」ということです。
ですが、これだけ歴史を積み重ねてテクノロジーが発展した現在、SNSの数字で人の価値が判断されたり、ひとりひとりの「生きづらさ」は増していく一方のようにも思えます。
全国から若者が集まるユニークなコミュニティがあると聞いたのは、そんなことを考えていたときのこと。現代社会が抱える矛盾を解決するヒントに、四国の南西部、愛媛県西予市のとある町で出会いました。
40年前に立ち上がった3人の若者たち
愛媛県の松山空港から1時間半、海と山がつながる明浜(あけはま)町と呼ばれる場所にそのコミュニティ「無茶々園」はありました。
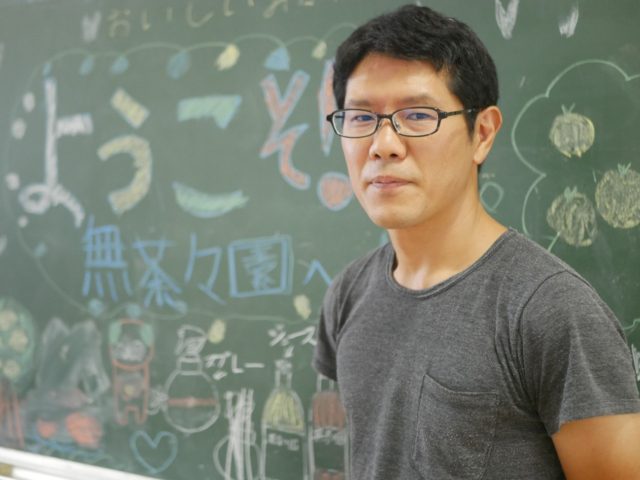
(写真:あらましを解説してくれた株式会社地域法人無茶々園の平野拓也さん)
今から40年前、3人の若者たちによって立ち上げられた無茶々園。「新しい農業のかたち」を求めて15a(アール、1aは100㎡)の畑から始まった取り組みでした。
当時の日本は、ベトナム戦争や学生運動の盛り上がりなど社会全体が数多くのひずみにぶつかっていた時代であり、経済成長にともなう環境問題が知られだした頃でもありました。
そんなとき無茶々園を立ち上げた3人が目指したのは自然農法、つまり完全無農薬・無化学肥料での野菜づくりです。今でこそ当たり前にスーパーに並ぶ「有機野菜」ですが、当時の農村において、安定した収穫をもたらしてくれる存在だった農薬を使わないことはあまりにも「常識はずれ」なこと。

(写真:無茶々園のみかん畑と明浜の町なみ)
当然、たくさんの苦労が待ち受けていましたが、それよりも「現状の農業への疑問」そして「世の中を何とかしたいという思い」を持つ多くの若者が集まることで、無茶々園は一歩ずつその歩みを前へと進めていったのです。
そんな無茶々園は今、農業だけではなく、水産業、町全体での6次産業化や新規就農者支援、さらには福祉事業の設立まで、街づくりそのものを担う存在へと成長しています。
たった3人の畑から始まった無茶々園はなぜ、人を惹きつけ続け、街にとってなくてはならないものになったのでしょうか。
「人と違う」ことの価値が人を引き寄せる
「若い人を残そうと言ったって、働く場がないと意味がない。今ありがちな移住政策はどこかズレているんです」

開口一番、ぎくりとするような指摘が…。発言の主は農業組合法人無茶々園の前代表理事であり、西予市の市議会議員も務める宇都宮俊文さん。
現在社員が関連会社をあわせて100人ほど、町内外でその倍以上の人がかかわるほどになり、西予市内でも最大級の企業になった無茶々園。全国から移住者が集まる背景について宇都宮さんは次のように語ります。
「田舎に人を呼んだけど、来てみたら不便。こういう矛盾を解消しないと本当に人は来ない。それよりも、田舎に人が来て盛り上がるイメージをつくらないと。そのためにはどこか人と違うことを、少し早くやることが大事なんです」

(写真:無茶々園の事務所は廃校になった小学校を再活用している。これも「人と違うこと」の一つ)
冒頭で紹介したように、無茶々園の成り立ち自体が「当時の常識」を覆す取り組みでした。ただし、農業において「人と違う」ということは、その言葉以上に深い意味を持つと、続く宇都宮さんの話から気づかされるのでした。
それは、農作物を「人と同じ」ものにするために、どれだけの負担が人と地域にかかっているのか、ということ。
「日本くらい農薬を使っているところはない。きれいで味もいい、もはや農作物ではなく加工品になってしまっている。(農作物に)虫がつくのは当たり前、食べ物も腐るのが当たり前。何でもかんでも申し訳ありませんという、わがままな消費者にしてしまった世の中はおかしいんじゃないでしょうか」

無茶々園のはじまりでもある、みかんやレモンといった柑橘類に関しては特にその矛盾が大きいのだ、と宇都宮さんは続けます。
「みかんは1年に成分で20回近く農薬を使って、収穫前に防腐剤をかけるのが当たり前です。それは残留農薬の数値ではなく、回数で基準をつくっているから。なぜかというと、柑橘類は皮を使うから農薬を使ってきれいにしなくては、と考えているんです。でも、それは考え方が逆。食べ物だから農薬をできるだけ使わない、とするのが自然でしょう」
そんな矛盾をなんとかしたいと生まれた無茶々園は今、全国に顧客を持ち、地域全体から応援される存在になりました。というよりも、地域全体が変わっていったのかもしれません。

(写真:全国にファンを持つ、無茶々園の柑橘ジュース)
宇都宮さんは、当初から現在まで無茶々園に集まる人は「人と違う」ことに価値を見出し、その価値を育てていくことに意識的であることが特長だと言います。
「(無茶々園に)来る人はやっぱり“気づいている”んです。空き家をどうする、都会から若者を寄せよう…そういう発想じゃなく、ちゃんと現実を伝えてそこに魅力があるから来てくれている。そんな人はやっぱり個性的でおもしろい」

仕事だけではない、「生き方としての」人間関係
11年前にこの地の一員となった村上尚樹さんは石川県出身。大学卒業後、全国各地を転々としながら「農業」というテーマで自分が生きる場所を探していました。そんな2年間を踏まえて選んだのが、無茶々園だったといいます。

「田舎で農業をするということは、仕事と生活が表裏一体、即ち生き方につながる。無茶々園は良くも悪くも適当で。ベースとなる考えがありつつ、いろんな人がいる、生きていく中で仕事だけでない豊かな関係を築いていけると思ったんです」
村上さんは今、無茶々園の中でも新規就農者を研修生として支援する「ファーマーズユニオン天歩塾」という組織を束ねる役割を担っています。昔は家と畑を用意して「じゃあやってね」というやり方だった無茶々園でしたが、それではうまくいかない、ということで立ち上がった仕組みです。

(写真:研修生への指導も村上さんの重要な仕事のひとつ)
「普通の事業と同じなんですよ。何がしたいか、どうありたいか、そのために何をすればいいのかを考えているんです、仲間を増やして生きたい、「こんな生き方いいな」と感じていたいし共感もしてもらいたい、そのために受け皿として仕事や生活の基盤をしっかり作らなきゃ」
自然を相手にする農業は、四季を感じ、天候に左右されながら暮らす生き方。それが合わない人には事務所での仕事があります。

(写真:みかん畑は無茶々園のシンボル)
そんな「受け皿」としてのファーマーズユニオンや無茶々園のあり方について、村上さんはこう語りました。
「ただ単純に会社に勤めるのと違って、無茶々園は単位が“地域”や“社会”になっていて。もし仮に会社で嫌なことがあっても、ふと視点をずらして見れば、地域にはいろんな人がいたり、いろんな行事や集まりがあったり、いろんないい景色があったり、ほんと多元的な価値を見出すことができる、そういうことがなんとなくここで生きていくことを”有り”な選択肢にしてくれるんです」

疎外も、強制もないまち

(写真:左が岩下さん、右が豊吉さん)
無茶々園滞在1日目の夜、町の方々との懇親会で出会った岩下紗矢香さんと豊吉麻未さんは、この地にやってきた多くの「Iターン」者の中でも、特に最近のメンバー。
そんな2人が無茶々園にやってきた経緯を聞いてみると、やっぱり普通の会社や組織とは「ちょっと違う」面が顔を出します。

「東京の生活に疲れてきたときにふと、大学で学んだ農業に関わりたいと思って。インターネットで何気なく、農業関係の仕事を検索していたら、無茶々園だけなんだか雰囲気が違うのが目に留まったんです。“農家として独立をしたい人を募集します”みたいな求人が多い中で、無茶々園は“農業と地域を共に作っていくスタッフを募集します”っていう」(豊吉さん)
そんな募集文面に「おもしろそうな地域の一員になれそうだな」と感じた豊吉さん、直感のまま気が付けば明浜へ足を運んでいたそう。それから東京に戻って1か月間考えたのち、無茶々園で働くことを決めました。
元々「人が集まるところが苦手でマイペースを保ちたい人」だったという彼女。最初に勤めていた会社で働く中、置かれている現実と自分が求める理想とのギャップに違和感を覚えたことが、転職を考えるきっかけだったそうです。
そんな豊吉さんは無茶々園の環境についてこのように語ってくれました。
「地域全体が家族のよう。普通だったら、仕事の時間が終わったら別々じゃないですか。でも皆住んでるところも近所だし、こうやって家に招いてもらって一緒に飲むことも多い。もちろんいろんな人がいるし、いろんな距離感はあるんですけど。一人一人のつながりっていうのは絶対、普通よりも濃い」(豊吉さん)

その言葉に深くうなずいていたのが、4年前愛媛県の国立大学を卒業後、無茶々園に新卒入社した岩下さん。
大学で学んだ「まちづくり」を元に、現在無茶々園で地域に関わる仕事に取り組んでいる彼女は、無茶々園に来ると決めたとき、親の猛反対にあったといいます。

「自分自身、最初は全然給料とかも知らなくて。だから親は大反対でしたね。まずは“なぜ九州に帰ってこないんだ”。2つ目に“なぜそのよくわからない、しかも給料も高くないところに”。昔の考え方なんですよね。最近になってやっと、まあやりがいを感じてやってるんだろうなっていうのはわかってもらえてるみたいですけど」(岩下さん)
2人に共通するのが、それまでの人生上、決して「普通」の選択肢ではない道を選んできたこと。そんな大きな決断について2人は口をそろえて「間違ってなかった」と語ります。それは、無茶々園の人々との適度な距離感が大きく働いていました。

「地域の人柄も、すごくオープンだけど逆に粘着質ではないので。絶対にうちに染まれみたいな強制もない。そこはすごくありがたいなと。疎外もされないし、強制的に引っ張り込まれもしない。たぶん私が来る前に、いろんな人が外から来て、去って行った人もたくさんいると思うんです。そういうことも含めて、受け入れてくれてるような空気がある」(豊吉さん)
「人と違うこと」が原点にある無茶々園だからこそ、これまでも、これからもいろんな人を受け入れる。そしてそれが一人一人の暮らしやすさにつながっている…そんな無茶々園の特長を体現するような宴席とともに、夜は更けていくのでした。

…そんな「違いの価値」を軸に成長してきた無茶々園でしたが、現在新たな壁にぶつかっているといいます。
後編では、その「壁」を乗り越える経緯から見えた、「これからの自治」のあり方をお伝えします。
あわせて読みたい









