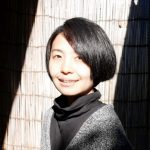「好きなことで生きていく」
まるで夢のような言葉だと思っていたものの、ここ最近「好きなことで生きている人たち」を目にする機会が多くなった。
しかしながら、「好きなことで生きていく」と語っている人たちはどこか僕たちにそれを見せびらかしているようで、誰かの嫉妬を買ってしまって「炎上」させられてしまうことも多々ある。
誰かに見せびらかすのではなく、もっと自然に好きなことで生きていけて、それが勝手にいろんな人のためになるような生き方はできないものか。
そんなことに悩んでいた筆者は岩手県の、とあるカレー屋にたどり着いた。
謎のカレー屋「カレーだJ」とは

岩手県花巻市の国道283号沿いにある「R283だJ」こと「カレーだJ」はカレーのテーマパークを名乗っている。
どんぐりの形をしたログハウス・どんぐりドームとそれに備え付けられたツリーテラス。
海がないのに海の家を名乗っている・海の家ダイヤモンドヘッド。
そして、駐車場に停められた一台のキッチンカー「カレーだJ」この日、カレーだJの創始者・菅原治郎さんは海の家ダイヤモンドヘッドの中にいた。
夏の日差しをこれでもかと取り入れるために大きな窓を境界に、店内はまるで外が海であるかのように、海の家にありそうなものであふれていた。
ところどころ見かける流木は実際に海岸で拾ってきたものを使っているらしい。
また、梅干しカレーやレモンカレーなど、提供しているカレーも独特なものが多く、メニューの説明を聞くと、どれもこれも美味しそうだった。
この日は治郎さんが最初に完成させたカレーだという「レモンカレー」をいただいた。
アクの強めなお店の外観とは裏腹に、さっぱりとした口当たりとコクとスパイスの風味が引き立っているバランスのとれた絶品カレーを口いっぱいに堪能していると、突然店内に「ただいまー!」という声が響き渡る。
すると、学校が終わったらしい小学生や中学生たちがゾロゾロと店内に入り込んできた。
ある子は本を読み、またある子は治郎さんの作った人形「アインシュタイン先生」で遊んでいる。
自分でお金を払ってカレーを食べている子もいれば、250円で食べ放題のかき氷を食べている子もいる。
「うち、学校近いんで、気がついたら子どもたちが放課後によく来るようになったんですよ。」
カレーだJのすぐそばには団地があり、その近くには小学校や中学校がある。
とはいっても学校からこのお店までは徒歩10分ほどの距離がある。これほど店内が放課後の小・中学生で賑わっているのはなんだか不思議な光景だ。
いったい、彼らはどこでカレーだJを知ったのだろうか。
そして、このただならぬカレー屋はどのようにして生まれたのだろうか…。
カレーだJの誕生、下北沢のバーからのスタート。

治郎さんは花巻出身。
しかし、カレーだJ最初の一杯は東京の下北沢で生まれた。
高校卒業後、しばらく地元で働いた後に花巻を飛び出し、沖縄、千葉を経て、東京の下北沢のバーで働くことになった治郎さん。
東京で偶然沖縄の友人に再会し、彼が作ったスパイスカレーに感動して、カレーの研究をすることになった。
それから、カレーを作る修行のために、カレー屋でアルバイトを始めようとしたものの、インドカレー店からは「インド人じゃないからダメ」と断られ、大手カレーチェーン店からは「身だしなみがダメだ」と言われて、途方にくれる。
そんな治郎さんに手を差し延べたのが、働いていたバーのマスター。「お店が空いている昼間に使ってみないか?」という粋な計らいのおかげで、治郎さんはカレーの研究開始後すぐにお店を確保することができた。
ちなみに、カレーだJと命名したのはこのマスターだというから、2人の仲の良さが伺える。
しかし、治郎さんは迷っていた。カレーの研究を始めたばかりの自分が果たしてお客さんからお金をとってもいいのだろうかと。
「自分が自信を持ってうまいと言えるカレーを出しなさい」
知人からそう言われた治郎さんはカレーの研究にひたすら打ち込み、ついに自信を持ってウマイと言える「お金をもらえるカレー」を作り上げることができた。それは、治郎さんがスパイスの研究を本格的に初めて4ヶ月目のことだった。
しばらく順調にカレーを作っていた治郎さんだったが、ある日突然スランプに陥った。
このままでは…と思い悩んでいた治郎さんを元気づけようと、当時の仲間たちが治郎さんのために、あるイベントの開催をもちかける。
それは「下北沢カレー王座決定戦」。今も下北沢名物として続く、「下北沢カレーフェスティバル」開催のきっかけになったイベントだ。
だが、治郎さんは自ら一つの試練を下した。それは「一位になれなかったら、カレーだJを閉店する」というもの。1日に6食分しか作ったことがなかった治郎さんにとって、イベント用のカレーを100食作ることも、そもそもバー以外の場所でカレーを作って提供することも初めてだった。「絶対に一位になる。」と心に決め、寝る間も惜しんで当日に挑んだ。
結果は4位。しかも、参加者4人中の4位という屈辱的な結果だった。約束通り、カレーだJは閉店することになった。
「かっこ悪くても再開」カレーだJ、新天地・花巻へ。

「これこそが俺が作りたかったものだ!」と意気込み、人生を捧げる覚悟で始めたカレー作り。
それを失った治郎さんは下北沢カレー王座決定戦以降、文字通り無の時間を過ごしていた。
だが、ある日「これではいけない」と思い、仲間にリベンジのチャンスを求めた治郎さん。仲間から返ってきた答えは予想外のものだった。
「みんな、お前を元気付けようと思ってやったんだから、ちゃんとみんなに謝って再スタートしてこい」
地元の新聞で「かっこ悪くても再開」という題で報じられたカレーだJの復活。そのとき生み出されたメニューこそ、冒頭で紹介した治郎さん初のオリジナル「レモンカレー」だったのだ。カレーも順調に売れるようになり、自分だけのカレーを作り出した治郎さんはかねてより思いを馳せていた地元・花巻に戻り、カレーだJをスタートさせることにした。
「『花巻は自分に一番あった場所だ!』と思うようになったんです。やっぱり、住むことを考えると花巻だなって。」
しかし、花巻での店舗探しは難航を極めた。決まりかけた物件も補修の関係でダメになり、八方塞がりとなった治郎さんに友人が提案したのはキッチンカーでの営業。
「これで毎日カレーが作れるんだったら安いものだ」
貯金をはたき、キッチンカーを購入。イベント出店を中心にカレーの販売を行いつつ、カレーの研究を再開した治郎さん。
より本気で取り組むために、生活費確保のために行なっていたアルバイトを辞めた。本格的にカレーの研究と店舗探しを始めて3ヶ月後、治郎さんはついに現在の場所にたどり着いたのだった。
いつのまにかに「街を元気にしてくれてありがとう」と言われるようになっていた

治郎さんは一週間のうち4日カレーを売り、その売上を使ってどんぐりドームや海の家、ツリーテラスを作り上げた。
沖縄の村づくりで培ったDIYスキルと、見習い大工として働いていた頃の経験や道具をもとに、ありとあらゆる「作りたいもの」を自分の手で作り上げたのだ。
「見習い大工とはいっても、掃き掃除くらいしかしたことなかったので、全然ですよ。海の家はDIYでしたが、どんぐりドームは完全に手作りで、拾ったどんぐりを見ながら作っていましたね(笑)。」
どんぐりを観察しながら、木を組み合わせて何かを作っている様子は登下校中の子どもたちの目に留まる。見るだけでは満足できなかった子どもたちは、いつしか治郎さんの作品作りを手伝うようになり、彼らの連れてきた友達でお店が満席になることもあるほどになった。さらに、子どもたちは親をお店に連れて来てくれるようになり、カレーだJのカレーが晩御飯という家族も、この町では珍しくなくなってきた。
気づくと、治郎さんは街の人から「こんな何もないところにお店を出してくれてありがとう」と言われるようになっていた。
「自分が楽しまなければ、周りを楽しませることなんてできない。」

「カレーだJは僕の自由研究なんです。カレー屋なんで、カレーを売るのは当たり前なんですけど、それ以外もちゃんとやっていきたいなと思って。」
カレー屋の売り上げを注ぎ込んで手掛ける全力の「それ以外」。この場所にあるもの全てが、自分のやりたいことを全て詰め込んだアートだと治郎さんは言う。
「自由研究って最強じゃないですか!だって、『自由』で『研究』ですよ!」
子どものように目を輝かせて自由研究の素晴らしさについて語る治郎さん。
はたから見ると脈絡がないようにも感じられる自由奔放な人生。その始まりは一冊の旅行記に書かれていた「放浪しちゃえば?」という言葉だった。
「仕事は絶対に辞めてはいけない」という思い込みを捨て、覚悟を決めて直感に従って生きることを選んだ治郎さんにとって、子どもたちはまさに天才そのもの。そんな子どもたちからも刺激を受けている、現在の治郎さんが目指していること、それはカレーだJが「子どもたちと出会える場所」になること。
「ねえねえ、このアッカンベーをしているおじさんって誰なの?」
「これはアインシュタイン先生だよ」
「なんで、この人のTシャツ着てるの?」
「アインシュタインって、僕が一番わからないけどスゲーって思うものだったんですよ!」
子どもたちにアインシュタインのことを一生懸命に伝える治郎さんの姿は、筆者が昔憧れていた先生の姿にどこか似ていた。
編集後記
花巻の「生きる自由研究」であるカレーだJには今日も美味しいカレーの匂いが溢れている。
そこに子どもたちの笑い声や通り過ぎる車の音、鈴虫の声、スプーンがお皿を叩く音が混ざって、カレーだJの音を作っている。
この空間にどんなスパイスを入れられて、どんな「味」になっていくのか。
カレーの売り上げだけで作られたテーマパーク、存在そのものが1つのアートであり、カレーなのだ。
あわせて読みたい