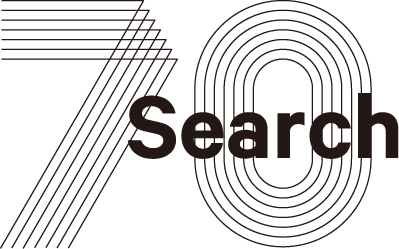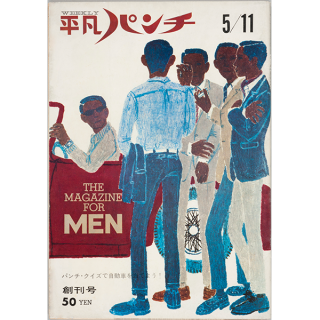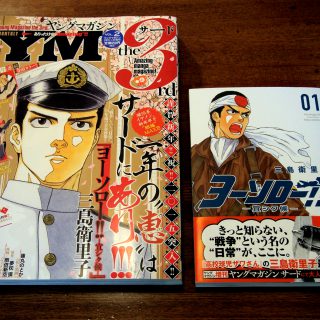「衣服が語る戦争」展が、6月10日~8月31日まで新宿にある文化学園服飾博物館にて開催されている。
衣服を通じてみる戦争の実態はどのようなものなのか。企画展を担当された村上さんにお話を伺いました。(写真提供:文化学園服飾博物館)
― 村上佳代:文化学園服飾博物館、学芸員。「衣服が語る戦争」展コーディネータ ―
戦争に対してのリアリティーが無くなると思った。
‐どうして今回このような企画展を立ち上げたのでしょうか?
やっぱり、今年は戦後70年の節目の年ですよね。
戦争は突然に来るものではなく、じりじりと生活が呑み込まれていくものだということをわかっていただきたいし、私も戦争を知らない世代ですが、戦争を悲惨なものだとしか想像できなくなるのは、戦争に対しての現実味を失うのではないかと不安でした。
‐「現実味を失う」とは?
戦争を第二次世界大戦末期の悲惨なイメージだけからだと、現実からかけ離れたものとして捉えてしまうのではないかと思ったんです。
身近な「衣」を通じてなら、自分がこうなったらどう思う?というのを考えやすいかと思いました。
‐当事者性が持ちやすくなるということですね。
はい。戦争というと、どうしても第二次世界大戦の悲惨な話が多いので、そうではなくて、それより前の時代(明治、大正)の服も展示することで、その頃からどのような影響があったのかを知っていただきたいと思いました。
縁起が良いものとして戦争の柄を好む。
‐大正時代に日英同盟が組まれたときは、柄にイギリス国旗が描かれていますね。
第二次世界大戦の三国同盟のときには、ナチスの柄が入っていたりするのですが、それぞれ単なる意味を持たない図として捉えると、アンティークでかっこよくて洒落ている。
でも、プロパカンダが日常生活にここまで浸透しているのかと怖さも感じました。
今の私たちからすると、戦争の模様が描かれているのは「怖い」とか、どうしてハーケンクロイツ(鉤十字)の模様の着物が作られたのだろう?とか、そういう怖さや違和感などの感覚を持つと思います。
しかし、これらの着物が作られた当時は、戦争に負けたという後々の結果はだれも知らないわけで、憲法も今と違うし、同じ日本人だけど、70年、80年前の人たちとは教育も感覚も違うわけですよね。
今の私たちが感じるものと、当時の人達が感じていたものは全く違うと思うんです。
‐なるほど。
展示は明治時代後半からスタートしています。その頃は初の近代戦である日清戦争、日露戦争で大国に勝利したことに、日本中が熱狂していました。
その感覚は、昭和の初めまでも引き継がれていたと思います。
だからその模様も、戦争に勝利した、強い、という縁起が良いものだったんです。
 ‐プロパカンダとかそういったものではなくて?
‐プロパカンダとかそういったものではなくて?
そうですね、強さや勇ましさを感じさせる縁起が良いものとして受け止めていたと思います。
そういった柄を子どもに着させるというのは、子どもに「健康で強くたくましく育ってほしい」という親の願いでもあるんです。
今でも、戦隊もののTシャツを好んで着る男の子もいますが、感覚としては、さほど変わらないもので、流行の一現象だと思います。
プロパカンダというよりは、流行の一現象ですね。流行の一現象で、大衆が欲するから作られていた。
‐そこからは何が読み取れるのでしょうか?
明治、大正、昭和の始めというのは、戦争を「かっこいい」という感覚で受け入れていったんだなぁ、と。
やっぱり戦争がまだ近くに迫っていないと、それをファッションに取り入れようという余裕もあるんです。
それで、「かっこいい」「憧れる」的なものとして、男の子の服や女性のドレスにミリタリー的な要素が取り入れられます。
‐自分事ではないからこそ、流行に出来たのであり、感覚としてかっこいいというものだったのですね。
そうだと思います。
それに、ちょうど大正時代から染色技術が飛躍的に向上します。今までは藍染の渋い色が市場に多かった。
でも、化学染料が普及するようになり、鮮やかな色が出せるようになって、しかも大量生産品でそんなに高くないとなれば、みんな飛びつきますよね。
‐少しは当時の人たちのことを想像できるようになりました。
「私は軍国主義的です」というメッセージが込められているわけではなくて、ファッションを楽しむような軽い感覚だったと思います。
木綿や羊毛が入らなくなり、ようやく戦争だと気付く。
‐昭和初期までは熱狂が続いていたと言っていましたが、いつから自分事としての転換点となったのでしょうか?
昭和12年ですね。

(写真:昭和12年頃の男性用襦袢。「進軍の歌」の歌詞が表されている。)
‐昭和12年ということは1937年、日中戦争の開戦ですね?
そうです。日本は資源小国なので、日中戦争が始まって国際的に孤立すると輸出入が滞る。
そうすると、それまで輸入していた木綿や羊毛が入ってこなくなる。
この辺から緊迫した状況になっていきますね。
政府も、その後様々な法令を出すようになり、昭和12年がキーポイントとなってきます。
‐なるほど。それでは、例えば代わりに蚕の養殖が盛んになるとか、国からの政策に伴っての変化もあったのでしょうか?
蚕というのは絹ですよね?実は、当時の日本は絹を100%自給できているんです。
それをアメリカなどに輸出していたけれど、その輸出が出来なくなってしまったので、かえって、今度は絹が供給過多になってしまった。
‐そうだったんですね。
はい。アメリカでは、日本の絹というのはストッキングに使われていたけど、絹が入ってこなくなるとストッキングが作れなくなります。
それがゆくゆくは、ナイロンストッキングに繋がっていくんです。
‐驚きました。今はすごく身近なナイロンストッキングが、実は戦争と繋がりがあったものだとは!
そうですね。今ではファッション・アイテムとなっているフライトジャケットやトレンチコートも戦争の中で生まれたものですよ。
‐知りませんでした・・・。話は昭和12年に戻り、当時日本では、絹より羊毛や木綿が多く使われていたのでしょうか?
和服でしたら絹が多いですが、着物の下に着る襦袢などにはモスリンという羊毛地が使われたりもしますし、軍服も羊毛で作っていますよね。
また肌着などにも木綿が使われています。だから、羊毛も木綿も需要としては欠かせないものでした。
‐では、それが昭和12年の日中戦争開戦その後の孤立で、入らなくなると、どのような政策を国は出していったのですか?
まずは、羊毛と木綿が絶対的に足りないので、純毛製品、純綿製品(羊毛100%、木綿100%)の布が一般には出回らなくなる。
法律で、木綿には3割以上、ステープルファイバー(材木のパルプから出来るもの)を入れないといけませんというお達しが出ます。
羊毛に関してもそうですね、何割以上入れなきゃいけないというお達しが出ますね。
‐色とかデザインの面ではどういった変化があったのでしょうか?
布を節約したデザインや、ボタンなどの装飾が減っていきます。
‐確かに展示を見ていくと、ボタンの数が少なくなっていきますね(笑)。
はい(苦笑)。その後、昭和15年には、贅沢品の販売を制限する「七・七禁令」(奢多品等製造販売制限規則)が7月7日に施行されます。
その中では衣だけでなく、生活全般において贅沢なもの、一定以上の高価なものを作る、売るのは止めましょう、と決められ、被服付属金具や装身具なども対象になっています。
‐ボタンやファスナーを使わない洋服となるとワンピースになるんですか?
そうですね、上からかぶって着るものなどが多くなります。
さらに、昭和15年には男性の「国民服」、昭和17年には女性の「婦人標準服」も制定されます。
国が国民服を強制したわけじゃない。

(写真:国民服)
‐「国民服」や「婦人標準服」は制服みたいに毎日着なきゃいけないものだったんですか?
勅令で国民服の種類や形が明記されたのですが、ただ、今の若い人たちはみんな、国民服は着させられたと思っていますよね、お国によって着せられたと。
‐はい。「国によって着せられた」と思っています。
でも実際はそうではなかった。
国民服はこういうものです、と国は決めたけれども、「着なさい」と強制するようなことや、着ないと罰則があったようなことではない。
強制じゃないので、最初のうちはそんなに普及しなかったみたいですけれど、戦争末期になると普及してきたようです。
‐どうして第二次世界大戦末期に普及してきたのでしょうか?
国民服は礼服の役割も果たし冠婚葬祭にも着ていけるし、普段も着られるので、一枚それがあると便利なものでした。
なので、礼服を新調しようというときに、背広ではなくて国民服にしようかという感じで段々と広まっていったと思います。
そうやってみんなが徐々に着出すと違和感もなくなりますし、あの人が着ているなら私も着ないとダメかな、ということで終戦間近にはわりと普及していったようです。
‐国民服の広まりには便利さと、「みんなが着ているのなら・・・」という気持ちがあったのですね。一方、婦人標準服とはどのようなものだったのですか?
婦人標準服は、洋服タイプと和服タイプ、活動衣(いわゆるモンペ)の3種類。
布池の節約と活動性が考慮され、和服タイプは袖の振りが短く、おはしょりがないものでした。
洋服タイプは和服と比べると布地を多く使わないで済みますので、着物をリメイクすることも推奨されました。襟の重なりが着物風になっているのが特徴です。
ただ、洋服タイプに関してはほぼ普及しませんでした。
婦人標準服の制定が昭和17年という、物資も乏しい時期に入っていて、余裕も無かったのだと思いますけれども。

(写真提供:婦人標準服、洋服型)
‐同じ時期に制定されたモンペはどうだったのでしょうか?
モンペは普及しました。婦人標準服の「活動衣」という位置づけだったので、モンペで町内の防空演習に出て行く人が多かったみたいです。
そうすると、「みんな履いているから私も履かないといけないのかしら?」という連帯意識で、普及していったようです。
‐ただ政府としては強制をしていないんですよね?
はい。婦人標準服も、国民服と同じように、こういうものに決まりましたと国民に知らせました。ただ、強制はしていない。
‐意外でした。
当時モンペを着ていた世代の方たちが、戦後になって戦中を振り返った時、「モンペを着せられていたのよ」とお話されることがありますよね。
みんなが着ていたから、空気を読んで私も着ていた、着なければならないような雰囲気だった。
それが国から押し付けられたという印象にすりかわってしまったんだと思いますが、実際には、「これを着なさい」「着ないと罰則があるぞ」ということではなかった。
‐そうすると、「衣服が語る戦争」からは、何が語られるのでしょうか?
そうですね・・・。
まだ戦争が自分の身に降りかかっていないときには、ミリタリーをファッションとして取り入れる余裕があるけれども、戦局が悪くなり日常の生活さえも思い通りにいかなくなったとき、国民一人ひとりの感情が、「みんなに合わせていかなくちゃ」という、着るものさえも自分で考えられなくなってしまう強迫にも似た状態にさせるのかな、と。
‐なるほど。戦争が対岸にあるときはファッションとして取りいれるような余裕もあるけれども、いざ自分事となったときに、思考が停止してしまう。
そのような感じを受けますね。
‐他にも、フランスやイギリスのものも展示されていますが、同じ戦時下の中でも何か違いや共通点はあるのでしょうか?
やはり、その後の勝敗に関係なく、ファッションは戦争の影響を受けます。
ファッション雑誌も、戦争の影響を受けています。
例えば「装苑」を見ても、戦局が悪くないときの記事は、パリの流行を特集して外国人のモデルさんも載せている。
けれど、戦局が悪くなってくると、着物を洋服にリメイクしましょう、などといった内容になってきます。表紙の雰囲気も全然違ってきます。
‐検閲は当時あったのでしょうか?
ありました。昭和16年からは用紙が配給制になり、かなりの雑誌が統廃合されました。
‐今までのお話を伺うと昭和15年の「七・七禁令」や国民服の制定など、昭和15年や16年にならないと中々戦争を身近に感じられないですよね。
そうですね、やっぱり自分の身にふりかからないと。
「戦争柄」から考える平和
‐今回の企画点では、どのような反応を頂いていますか?
「戦争と服、ファッション」という切り口がこれまでにはなかったとか、資源小国であることを実感したとか、やっぱり戦争はいけない、といった感想も頂いています。
‐一方で、この戦争柄をみて、「わーおしゃれだ」とか、「かっこいい」と思うのもありなんですね?
ご覧になる方の感性にお任せします・・・。
私は、戦争の柄を当時の染色品という観点から見ていますが、大量生産品であるけれども、デザインや表現などが凄く工夫されているなぁと思うんです。
例えば、軍艦と飛行機と装甲車を一つの画面に違和感なく描きこんでいるところに目がいくんです。
現実だと、陸と海と空というそれぞれ背景の異なる場所にあるべきものだけれども、それぞれの間にパラシュートや雲、旗などを散らすことでデザインとして一つのまとまりのあるものにしているな、と感心しますね。
婦人標準服のワンピースも、着物のような打ち合わせ(襟の重ね方)になっているので、日本の伝統を取り入れているんです。やはりそういったところに目がいきますね。
‐最後にこの展覧会で伝えたいことは何でしょうか?
やっぱり生活に根付いたところから戦争を考えて欲しいなと思います。
木綿100%のものが無くなったらどうなるんだろう?とか。そして現在、無意識に享受している平和な社会がもたらす恩恵を実感していただければと思います。
あわせて読みたい