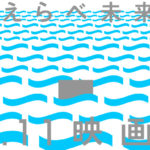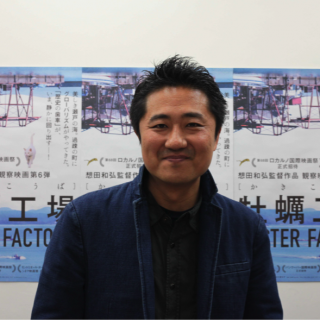「観察映画」というジャンルを知っていますか?そのパイオニア、想田和弘監督の作品「牡蠣工場」が2月20日から渋谷のシアター・イメージフォーラムで上映されます。
今回想田監督がカメラを向けたのは、瀬戸内海にのぞむ美しき万葉の町・岡山県の牛窓(うしまど)。日本有数の牡蠣の産地は、過疎化による労働力不足で中国人労働者を迎えていました。
この作品が問いかけるのは、牡蠣工場という小さな世界から垣間見えるグローバルで大きな問題。全2回で贈る今回のインタビュー、後編では、「牡蠣工場」で起きたドラマチックな出来事を入り口に、一人一人の「立ち方」を語ってもらいました。 (写真提供:Laboratory X, Inc.)
謎のメモ「中国、来る」から始まった「牡蠣工場」のドラマ
‐最新作「牡蠣工場」制作の経緯を教えてください。
「牡蠣工場」を撮ったのは、本当に偶然の成り行きです。舞台となる牛窓は、妻のお母さんの出身地。
それでよく遊びに行っていて、最近は牛窓で夏休みを取るようになって、地元の漁師さんと仲良くなって。
ところが、漁師さんはみんな70~80代なんですね。しかも後継者がいないらしい。
っていうことは、この「漁師さんのいる風景」って、いずれ消えてしまう風景なのかなと思った時に、それをちゃんと見ておきたい。ちゃんと撮っておきたい、と思ったのが最初のモチベーションでした。
‐最初は漁師の映画になる予定だったのですね。
はい。それで2013年の11月に、カメラを持って牛窓に舞い戻り、夏に知り合った漁師さんのところに行きました。
その方は普段は舟でタコや魚を獲っている方なので、僕はそういう映画をイメージしていたのですが、今は牡蠣のシーズンだからと案内されたのが牡蠣工場だった。
だから僕が牡蠣工場を撮るなんて、夢にも思わなかった(笑)。
‐その牡蠣工場でも「台本にないこと」が次々と起こったんですか?
最初はひたすら、牡蠣を剥いている人の姿をずっと面白いなあ、と思って撮っていた。ところが、ふと周りを見渡したら、カレンダーの横に「11月9日、中国、来る」というメモが貼ってあって。あのメモを見たところから、映画の縦糸が立ち上がっていったんですね。
‐映画のタイトルにもなりそうな、衝撃的なメモですね(笑)。
そうです。「『中国、来る』ってどういう意味だろう?」とみんなの会話に聞き耳を立てるわけですよね。
すると、中国人の労働者が2人、11月9日に来るんだ、ということがだんだんわかってきました。
牛窓でも過疎化が進行していて、働く人が不足しているんですね。伝統的には牡蠣剥きは地元のおばちゃんやおじちゃんが担ってきたんですが、ついに外国からの働き手に頼ることにした。
‐それで「中国、来る」と(笑)。
はい。だから、みんな戦々恐々としていて。どんな人が来るんだろう?という期待と不安が入り交じった感じ。
それが僕にも伝わってきたから、これはもしかしたらひとつの映画の軸になるんじゃないか、と。
そう思っていたら別の工場で「うちの中国人が5日で辞めちゃった。」というシーンが偶然撮れてしまうんですね。
‐それは衝撃的ですね…!
あのシーンが撮れた時に、中国人を受け入れるというプロセスが、現実に今「コンセプト」としてではなく現在進行形で起きているんだな、ということがわかったし、そういうシーンが撮れてしまったから、それが映画のキーとなっていた訳ですね。ひとつの縦糸になっていく。
あとは、工場を継ぐ方が宮城県出身で、東日本大震災で被災したことが理由で牛窓に移られたことも、おそらくは物語の軸、縦糸になっていくだろうなということは直感して、意識しながら撮っていました。
‐もし、撮りながら何もないな、と感じる時はどうされますか?
今まで、そういう理由で没にした映画は一度もありません。必ず何か興味深い現象に行き当たります。
それはたぶん「観察」するからだと思うんです。それで「観察映画」と呼んでいます。
「観察」というのは第三者として離れている、という意味ではなくて、僕にとっては「よく見る、よく聞く」ということなんですよ。
ただ、被写体の人はたいてい、「こんなの撮って、本当に映画になるの?」と聞いてきます。被写体の人にとっては、あまりにも当たり前すぎる日常を僕は撮っているので。
‐監督の頭の中では、撮りながら構成もできているんですか?
構成はあえて想い描かないようにしています。あくまで意識としては、「目の前の現実をよく見るぞ。よく聞くぞ」と思っています。
そこで気づいた事を映像に翻訳する。そのために、いろんなカメラワークをしています。
でも、撮っていれば、文句無しにこのシーンは興味深いな、シーンとして強いな、という場面には出会ったりするので、それがもしかしたら映画の核になっていくだろうな、という予感は撮影の時からしています。
‐「牡蠣工場」の撮影期間はどれくらいでしたか?
3週間の予定で牛窓に行ったのですが、牡蠣工場での撮影は1週間です。
残りの2週間は、カメラを持ってうろうろしているときに面白い人たちに出会ってしまい、その人たちを撮っていました。これは別の映画になる予定です。
主人公になるのは、86歳の漁師さん。70年間漁師をしている人で、今でも一人で、小さな舟で漁に出ている
「一億分の一の責任」を分担しよう
‐ 監督にとって、3.11を境に変化したことはありますか?
3.11の時、僕はニューヨークにいました。チェルノブイリの頃から、僕は脱原発の考えで、東京大学新聞の編集部にいた時にも、原発がいかに危険か、という記事を書いたり、専門家の寄稿を集めたりしていたので、福島の事故は本当に怖かったです。ずっと恐れていた悪夢が、現実になったという感じ。
‐チェルノブイリへの関心はなぜ生まれたのですか?
事故当時は高校生だったけれども、ちょっと調べてみると、原発はちょっとしたことでああなることは明らかなんですね。
事故が起きなくても、放射性廃棄物がどんどん溜まって行くことも明らかですし。
そんなことをずっと続けていたら大変なことになる、というのはその当時から感じていたし、頼むから原発をこれ以上建てるのはやめてほしいと思っていました。
それはでも、当時は本当に少数派ですよ。そんなことを言ったら、すぐに「お前、左翼だろ」とか言われて終わり(笑)。
‐たしかに(笑)。
だから、僕は東大を出てからは、ずっとさぼっていたんですよ。
政治運動そのものがばかばかしくなってしまい、反動で政治のことは考えないようにしていたし、政治よりも「人はなぜ生きるのか、どう生きるのか」ということに関心がシフトして「映画を作るんだ。それを表現するんだ」というふうにやってきたから。
でも、3.11が起きた時に、後ろから殴られたような感じでした。ずっとさぼっていたが故にね。
小出先生(※小出裕章 元京都大学原子炉実験所助教)とかにはものすごく申し訳ないことをした、と思ったし。
だって、小出先生たちはずっと孤独な闘いをされてきたわけでしょう。
僕が再び政治的発言をするようになったのは、3.11以降ですよ。さぼっていたことを反省したので。
【写真:日吉映像祭主催 映画『Peace』慶応義塾大学での上映会トークセッション(2016年1月8日)】
‐先日慶応大学で行われた映画「Peace」の上映会で、「知識人」としての想田監督と、「映画監督」としての想田監督を意識的に分けているか、という質問に「知識人というよりも、市民として政治的発言をしている」という回答をしていましたね。
残念なことに、政治的な発言をすることで、僕のことを「敵」だと思う人は少なからずいますよね。
僕は彼らのことを「敵」だと思っていないけれども、その人たちは僕を「敵」と思い、僕の映画を見てくれない。
政治的な発言をすることで、ある種の観客を遠ざけてしまい、色眼鏡で見られてしまうジレンマは感じます。
‐それでも、今後も「市民」として政治的な発言をしよう、と。
そうですね。仕方がないかな、と思って。自分の分はやろうと思っています。「民主主義」って、ひとりひとりに一定の責任があるでしょう。
一億人主権者がいたら、一億分の一の責任を担わなきゃいけない。その程度のことだと思うんですけど。でも逆に言うと、その程度は担わないといけないのかな、と思います。
‐半分は「映画」で、半分は「言葉」で?
映画は政治運動とは関係ないです。映画を作る動機は、自分の見た世界というものを、映画的なリアリティに構築して、それを人とシェアしたい、という「欲求」なんです。
映画「選挙」などは市民運動や教育関係の方々が使ってくれていますし、それは嬉しいんですけど、僕の動機としては、そういう使い方をしてもらうことを想定してあの映画を作ったわけではない。
自分にはこんなふうに選挙が見えた、ということをシェアしたいだけなんです。
映画はぼんやりした存在に「顔」を付けていくこと
‐講演会の質疑応答でも話していましたが、監督にとって、映画を撮る、ということがテロに対する一種の「抵抗」になりますか?
そのつもりはまったくないです。もちろん、もうすでに、映画を撮る事自体が「抵抗」になってしまいかねない世の中ではあると思います。
実際に、映画「選挙2」を撮って、公開するということが、一種の「抵抗」になってしまったので。
映画に登場するある自民党の議員の意向を受けて、「この映像を使うな」という通知書が自民党川崎支部連合の弁護士から届きました。
意図せずして、「選挙2」という映画を作って公開する、ということ自体が、現在の政治の流れに対する「抵抗」のようになってしまったんですね。
‐意図せずして、という点がもどかしいですね。
問題は、権力者から脅された時に、自主規制をしてしまうことなんですよ。
‐それはよく起こりうる話なんでしょうか?
それは、今いろんなところで起きていると思います。僕が「抵抗」したというのは、さっきの「一億分の一」の責任を果たそうとした、ということになりますね。
でも、一億分の一の責任を果たす事は大変ですよ、これからの時代。
‐ 戦後70年を迎えた日本は、ニューヨーク在住の監督に、今どのように映っていますか?
世界的に、今バイオレンスの方向に世の中が向かっていると思います。再び全体主義的な雰囲気に飲まれつつある。
アメリカではトランプが躍進したり、フランスでも極右政党が票を伸ばしたりとか。そういうのは全部「恐怖」に対するリアクションですよね。
その流れの中に、日本もばっちり乗っている。その流れからどうやったら外れていけるのかな、と考えていますが、その点においては僕はかなり悲観的です。この圧倒的な流れに対して、「抵抗」する人の数が少なすぎると思います。
‐ 映画「牡蠣工場」でも、境界線の引かれ方、「恐怖」の対象、比較が国と国の関係として描かれているシーンがありますね。
「牡蠣工場」を撮りながら感じていたのは、中国人は多くの日本人にとって一種の記号なんですね。同様に、中国人から見ると、日本人は記号。
そうすると、記号のもとには、一色の顔の見えない人たちが薄ぼんやりと見える。
‐「中国、来る」ですもんね。
大事なのは、特にドキュメンタリーを撮る僕にとって一番大事なのは、そのぼんやりとした記号だった人たちに、実際の顔をつけていくことです。
顔の見える存在にしていく、距離を近づけるというのは、ドキュメンタリーを撮ることの意義。映画の意義だと思います。映画のいいところって、そこですよね。
僕はイランに行った事がないけれど、イラン映画を見ているとイランの人たちにすごく親近感を覚える。
彼らの日々の奮闘とか日々のイシューが「他人事」ではなく「自分事」になって、近く感じる。そういうことが映画作家としてのやりがいの1つなのかな、という気はしています。
‐「牡蠣工場」ではどのように表されていましたか?
「牡蠣工場」の場合は、実際に二人の中国人の人がやってきて、仕事に馴染もうとする姿を見ていれば、同じ人間だな、と思いますよね。
‐なるほど…。
僕はニューヨークに一種の移民としているから、ああいう経験がわかります。言葉が通じない。習慣が違う。
状況をよく見て、ほうきで掃いている人に対して、サッとちりとりを差し出す。ああいうことは、僕自身にも経験があります。だから、感情移入してしまいますよね。
‐とてもリアリティがありますね。
そういうことを、観客ともシェアできればいいな、と思っている。一方で僕は、牡蠣工場の受け入れ側の人の気持ちもわかるし。
彼らも一生懸命生きようとしていて、中国の人たちにもなるべく快適な生活をしてもらおうとしている。それもちゃんと描きたい、という気持ちもありました。
‐両側の立場に立つ理由は何ですか?
それは側で見ていれば、受け入れる側も一生懸命だということはわかるから。そのこともちゃんと描きたいと思った。
元からあるイメージに支配されるのではなく、実際に現場で起きている事をよく見る、よく聞く、ということをしたいな、と思ったし、それをこの映画でやったつもりです。
想田和弘監督作『牡蠣工場』
観察する男 映画を一本撮るときに、監督が考えること
http://mishimasha.com/books/kansatsu.html
あわせて読みたい