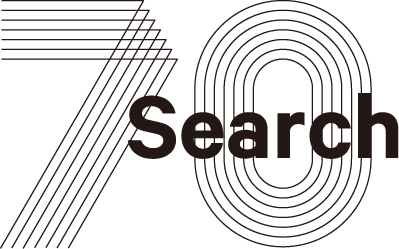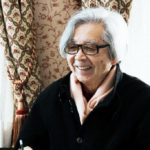1999年に産声を上げ、今年で17年目を迎える米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル & アジア」(SSFF & ASIA)。
世界100以上の国と地域から集まった約5,000本の作品の中から、選りすぐりの約200作品が上映される今年の同映画祭では、「戦争と生きる力 プログラム」が初めて展開されます。
戦後70年を迎える今年、どのような想いでこのプログラムを展開することにしたのか、主催者で俳優の別所哲也さんへのインタビューの模様をお届けします。
ショートフィルムは「削りの美学」
‐今年で17回目になるSSFF & ASIAですが、そもそも「ショートフィルム」にしかできないこと、特有の魅力とは何なのでしょうか。
別:まず、映画は長さじゃないということ。長編映画だと大きな予算で作られていくので、その過程でいろんな方々の思いが詰まっていきます。
結果、ワン・イシュー、1つのテーマについて突き進むということが難しくなることが生まれがちなんですね。
‐なるほど。
別:映像作家と映画監督には大きな線引きがあると思っています。ショートフィルムは画家でいうと「荒削り」なタイプ。
想い、スタイル、哲学、DNA、こだわり、それらを全てつぎ込みます。陶芸家に近いといえますね、一人でできる。
言い換えれば、短くて一人の想いや情熱が突き抜けていくことで、ぎゅっと凝縮されたものになるという良さがある。
ノールールがルールであり、作品の中にあるテーマ性の輪郭がはっきりと提示されていくのは、ショートフィルムならでは。
‐ショートフィルムは「若手の登竜門」的イメージが強いですが、若手にかぎらず、ベテランでも同じような特徴があるのでしょうか。
別:そうですね。ショートフィルムには濃縮する、凝縮していく世界と、そぎ落としていく、短歌や俳句のような「削りの美学」がある。
ストレッチムービー(一般的な長編映画)は、90分とか85分とかでちゃんと配給して、1800円いただくのが通常ですよね。
そうすると、いろんな要素が入ってきて、最初は社会派なテーマで始まったのに急にラブロマンスになったり、最後はアクションになったりして、「あれ、なんでこの作品つくったんだっけ」となる作品もあると思うんです。
‐観る側として心当たりがあります。
それに対して、特に今回の「戦争と生きる力プログラム supported by 赤十字」(以下、戦争と生きる力 プログラム)は、ショートフィルムの映像作家たるショートムービーメーカーが、ワン・イシューに「本当に必要な要素」を「物語の体力の長さ」で表現しているんじゃないかと思います。
「僕たちの国の映画祭が戦後70年にできること」を考えた
‐今年「戦争と生きる力 プログラム」を展開することになった背景を教えてください。
別:映画祭を始めて17年になるけれど、9.11、3.11、環境問題とか、様々なことがありましたよね。
ショートフィルムというのは、その時々の世界的な感覚、皆が感じていることがもっともビビッドに反映されるもの。
もちろん堅苦しい話だけではなく、コメディ、ドキュメンタリ、ファンタジー、アニメもある。それは、その時代時代のクリエイターの想いが出るということ。
やっぱり戦後70年という節目に僕らも触れて生きていて。いろんな捉え方はあるでしょうけど、70年の間、自ら拳を振り上げて戦争をしないで、平和国家を作ってきた日本がいかに素晴らしい国であるか。
あるいは唯一の被爆国であり、3.11でまた原発、原子力という科学の強烈なる存在感というものを否応なしに知った僕たち。
さらには地震、火山という様々な天災、環境の問題も知っている、そんな僕たちの国の映画祭ができることって戦争、平和、環境など、何かあるんじゃないかと。
そんな背景から、このプログラムを是非やりたいということでスタートしました。
‐「戦争と生きる力」というテーマについて、オーガナイズするだけではなく、つくる、演じる、といった立場での関わり方にも興味はありますか?
別:情熱が赴くままに、よい機会や作品があればつくる、演じるということもあるかもしれない。
ただ、映画祭を始めて17年目に戦後70年というタイミングや、自分の国のありようってどうなんだろうと思う機会があってこのプログラムを始めたこと、主催者として積み上げてきたこれまでのこともあり、一番は自分がつくる、演じる、ということではなくて、既に存在する、若いクリエイターのつくったものを世界から結集して見せることが大事だと考えています。
‐今回の「戦争と生きる力 プログラム」は、どんな人に届けたいですか。
別:圧倒的に戦争を知らない、日頃当たり前に平和で、当たり前に明日があると思っている、当たり前のように自分の権利が侵されないと思っている世代。
自分も1965年、戦争が終わって20年という、ちょうど日本が高度成長に入り変わっていく時期に生まれている。
それ以後の世代は、当たり前のように、先輩が築き上げてきた苦難の時代を、ありがたいことに、享受して生きている。その意味を知ってほしい。
‐「戦後70年」にどのようなことを思いますか。
別:世の中には、もう「戦前になってしまった」という人もいる。
映画祭を沖縄でやったり、世界中でやっていると、理不尽に「言論の自由」「表現の自由」を当たり前でなく奪われてしまっている人もいる。
その先に人権の問題、その先に「どうして人は争うのか」という問題がある。
僕はおじいちゃんがフィリピンで戦死していて、父親は父親を知らない世代、戦争によって時間を共にすることができなかった。
そしてそんな世代が、未だにいる。そんな争いが起きないようにどう組み立てるのか、それは、この戦後70年にひとりひとりが考えなくてはいけない問題意識だと。
70年前、東京が何もない焼け野原だったと考えると、「またそうしてはいけない」とみんながそう考える節目にしなくてはいけないのかな、と。
‐最後に一言メッセージを。
別:なぜ世界から争いが消えないのか、なぜ未だに何秒に1人という単位で命を失っているのか、なぜ理不尽に少年兵のように子どもたちが争いに巻き込まれていくのか。
興味を持っている人はいるはず、若い世代は捨てたものじゃないと思っています。「仕方ない」で済ませてはいけない、という問題意識を持っている方にぜひ観ていただきたいですね。
この映画祭はエンターテインメント性の高いものもたくさんありますが、骨太なものもしっかりあるのでぜひ楽しみにしてください。
あわせて読みたい