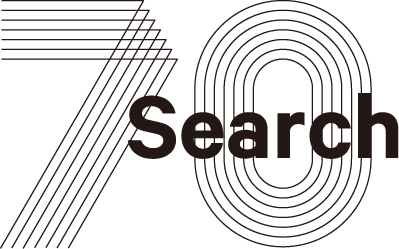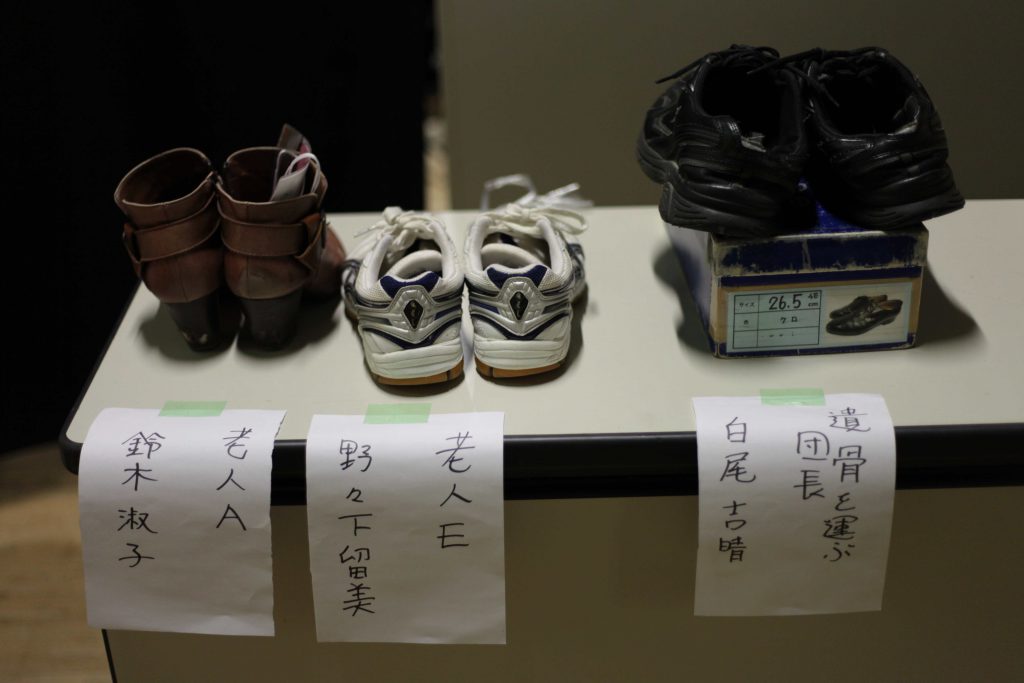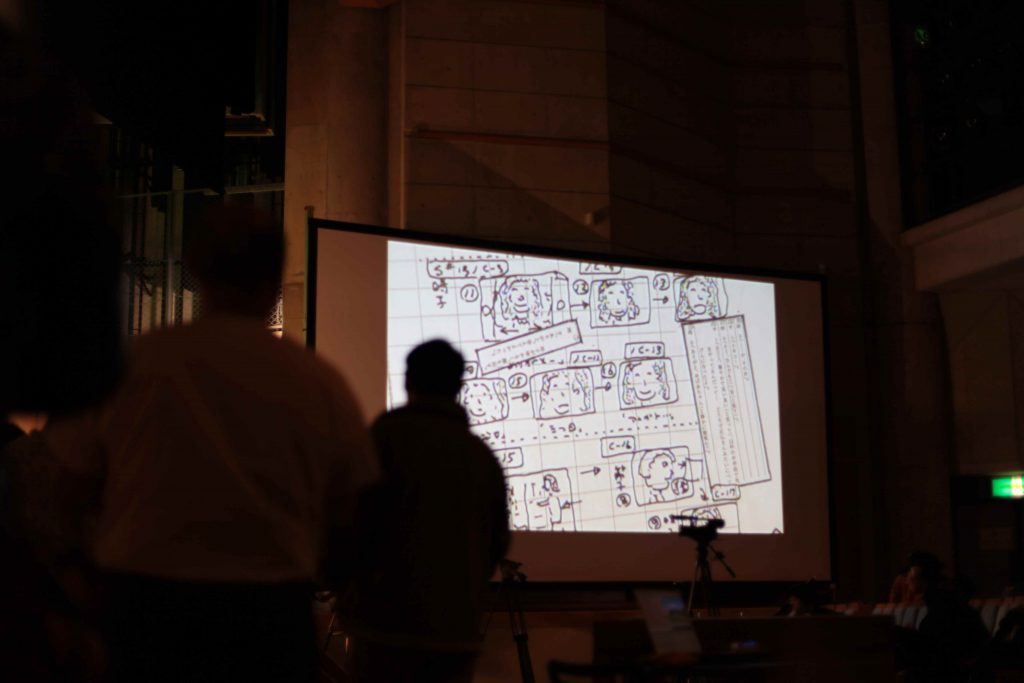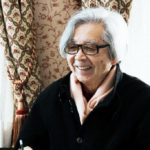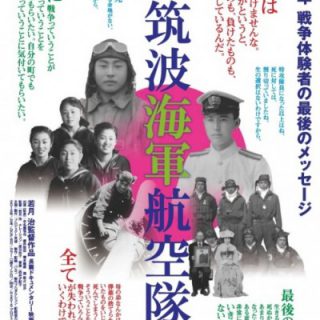2015年2月、大分県臼杵市で大林宣彦監督の「臼杵古里映画学校」が3日間開校された。
映画づくりワークショップでは、臼杵市民作のシナリオをもとにした短編映画を16時間で撮影。
「大林組」流、映画づくりの現場に潜入したレポート後編。 (前編はこちら)。
舞台は「戦中」と「戦後」の臼杵
会場に到着すると、臼杵市民会館のステージには、大規模な映画撮影用の舞台セッティングが施されていた。
観客席でワークショップの様子を見守っている人々の間にも、緊張した空気が張りつめている。
舞台は、まもなく迎える戦後70年目の8月15日、臼杵。
夏服に着替えるため、更衣室へと移動した。
国防服に身をまとった男性、昭和の雰囲気が漂うお下げ髪にもんぺ姿の女の子とすれ違う。
舞台裏には、「遺骨を運ぶ団長」「老人」など役柄の小道具が並んでいる。
そこにはすでに、「戦中」の空気が流れていた。
「絵コンテ通りにすすむとつまらない。」
大林監督はそう語る。
思いがけない場面にどう対応するか。直感を信じる覚悟が大切である、と
シーン展開の間に、映画論ならぬ人生論を説きながらワークショップは進行する。
主人公を演じる常盤貴子さんも、自ら参加者に質問を投げかけ、受け答え。
小道具の解説やスタッフ紹介、と休むことなく駆け回る姿は、女優という役柄を超えていた。
各々の役柄に関わらず、知恵を出し合って、ベストなシーンを撮るために自ら率先して動くのが「大林組」のスタイル。その現場の雰囲気は、終始漂う緊張感の中に、細やかな気配りが張り巡らされ、映画への愛と思いやりに満ちていた。
「役作りのためなら」と出兵役を演じる俳優の細山田さんは、本番直前に坊主頭へと変身。
俳優魂を、間近で見ることができた瞬間であった。
命あるものは、すべて音を出す
夜は撮影舞台上に、本映画主題歌の作曲を担当した伊勢正三さんがご登壇。
「6日分の撮影を1日で行うギネス級の挑戦をしています」と監督は伊勢さんにワークショップの実体を明かし、会場をどよめかせた。
伊勢さんは自作「なごり雪」を通して、「古里」を描く事が「世界」に繋がる悦びであることを知ったという。
映画は言葉である、と語る大林監督は、
「命あるものは、すべて音を出す」と話す伊勢さんと共通の見解を共有。
「人間は、ときに戦争という嫌な音を出すけれども、
人の仕草で一番うつくしいとき、それは良い演技となる。」
すでに8時間、ステージ上に置かれたディレクターズチェアに、大林監督は一度も座る事なく撮影は進行していた。
日付が回って、いよいよクライマックス。
日の丸の旗を振って、出征兵士を見送るシーンの撮影に入った。
過去と未来を生きる
映画の終盤、現代の場面で、主人公・時子が駅構内に向かうシーンがある。
私は「戦争反対」のプラカードを持った一群が、時子とすれ違う群衆の一人を演じた。
わずか30秒ほどのシーンであるが、撮影がはじまる「ヨーイ」の声と同時に、
戦後70年目の8月15日を生きていた。
戦後70年目の夏から半年前の2月を振り返ると、より現実味を持って、演じた役柄をリアルな存在に感じることができるのは、幸か不幸か、映画が未来を予言しているからであろうか。
ラストカットは、空襲の様子をビニールを使って特殊効果で撮影。
ビニールの緑と青色部分が映像では真っ赤な炎に変わる。
緑と青の色を炎であると想像し、焼夷弾が降ってくる場面を描いて演じるワークショップ参加者の演技は、
想像力があればどの時代のどんな場面でも、ステージで表現できることを証明する迫真の演技であった。
「客席からは何も見えない。大事なのはフレームの外。映らない場所でも演技をしている人がいることで、フレーム内での演技が活きる。」
月は煌煌と輝き、朝陽がまもなく昇ろうとする頃、16時間に及んだ撮影はクランクアップを迎えた。
「大事なのはフレームの外にある」と、監督の言葉を反芻しながら、撮影以外の場面でも学び多き一日を振り返りながら、眠りに落ちた。
古里映画サミット
翌朝、大林監督は不眠・不休・不食のまま、古里映画サミットの司会進行を務められた。
長岡市・芦別市・上田市・常陸太田市・尾道市・臼杵市の6つの市が「古里映画」によってつながり、一同が臼杵に集う。
「過疎」と呼ばれる全国の地域が、各々の古里の夢を生き生きと語らい、対話をする。
古里と、古里に生きる人と、誠実に向き合ってきた大林監督がつくる「古里映画」だからこそ可能となったサミット。
世代、立場、地域を超えて、各ロケ地で誕生する「映画」のような夢あるストーリーを、大林監督が指揮者となってタクトを振り、それぞれの「古里」紹介を、ステージの観客に披露した。
サミット終了と同時に、短編映画の上映がスタート。
撮影現場でワンシーンごと作り上げたカットが、映画という形になって表現される新鮮さと驚き。
「戦前・戦中・戦後」と、ワークショップ参加者は物語の中を生きる事で、戦中から戦後70年目の夏を1日半の制作中、確かに生きた。
「長生きするわよ。世界から戦争が無くなる日まで。」
劇中「いつまでも、長生きすると思ったけれどなあ。」と亡くなった祖母を想う主人公・時子の台詞に、
母・節子が返す台詞がある。
「長生きするわよ。世界から戦争が無くなる日まで。」
生を与えられた人間が、死者を想い、問いかける。
語らない死者の願いは、死者を想う限り、死後も死者とともに生き続ける。
映画の世界で「夢」を見る力、その「夢」を実現する力をもつ監督の映画は、
死者との「対話」も可能であることを伝えている。
前臼杵市長は、サミットでこう話している。
「市長になりたいと思ってなったのではなく、やりたい事があってそれをやる手段が、たまたま市長だった。」
大林監督もしかり、映画をつくることが目的で、映画監督になったのではない。
映画を使って、何ができるか。何をしたいのか。
今の時代を生きる上で、それが何よりも大切なのではないか。と問いかけた。
2015年8月15日
明日、真珠湾では、昭和20年8月1日の長岡空襲の犠牲者を追悼する「長岡花火」が初めて打ち上げられる。
「世界中の爆弾を花火に変えて打ち上げたら、世界から戦争はなくなるのにな」
貼絵で長岡花火を描いた画家・山下清が、もし戦後70年目の今を生きていたら、彼は何というであろう。
「大林監督の『古里』映画で世界の『古里』がつながったら、世界から戦争はなくなるのにな。」
と言ったりはしないだろうか。と、想いを巡らす戦後70年目の夏、
大林監督は、ロサンゼルス、ハワイ、マーシャル諸島で2012年公開の映画「この空の花ー長岡花火物語」上映会を行う。
何が正しいのか、ではない。
何が大切なのか、を考えることから始めよう。
穏やかな臼杵の一日の中から、世界を見つめよう。
「なごり雪」クランクイン時に、こう綴った大林監督の戦後70年目の夏は、臼杵からつながっている。
参考:株式会社たちばな出版 「日日 世は 好日 2001 五風十雨日記 巻の一 同時多発テロと《なごり雪》」大林宣彦文
あわせて読みたい