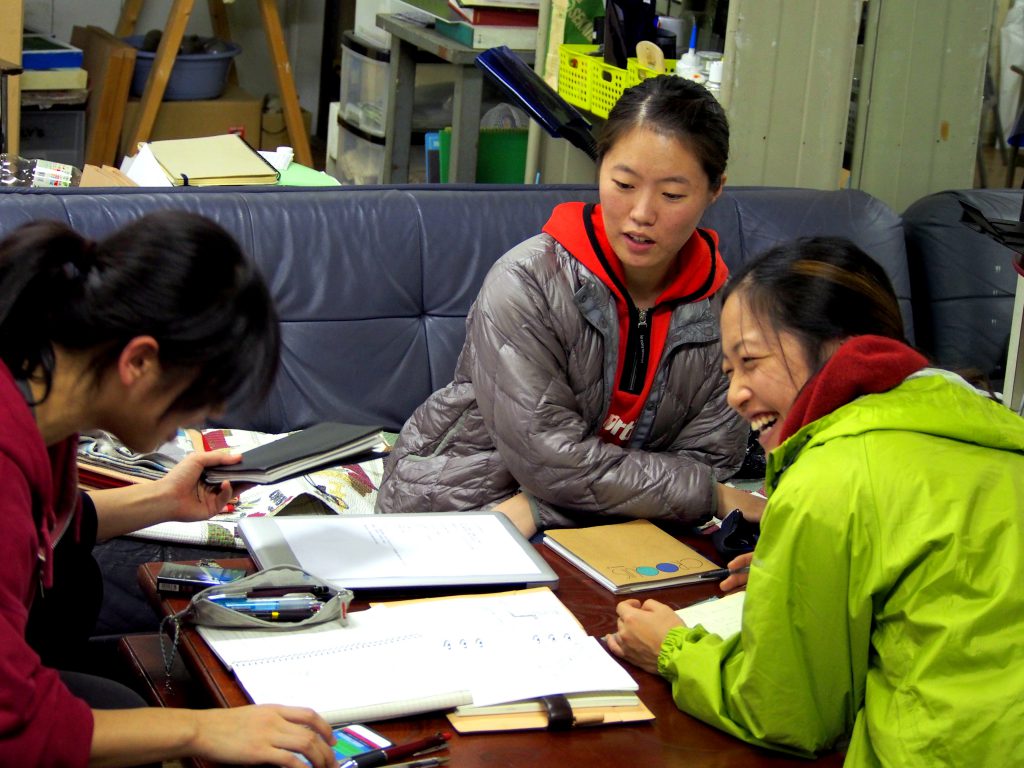ここは東京都小平市、50年以上も前から一枚の塀を隔てて隣り合って存在してきた、武蔵野美術大学と朝鮮大学校。11月13日から11月21日まで、両校を隔てる塀に橋が架かることをご存知でしたか?
上記期間に開催される「武蔵美×朝鮮大 突然、目の前がひらけて」展は、武蔵美のFALと朝鮮大学校美術棟1階展示室を繋ぐインスタレーション。両校の会場では、出来上がった橋だけではなく、この企画が立ち上がってからの対話や進行過程を辿ることで展覧会自体のアーカイブのリプレゼンテーションを展開しつつ、そこでの体験を経た作家たちの最新作、近作も公開する異色の展示となっています。
【写真:左から、朝鮮大学校美術科 鄭梨愛(Chong Ri Ae) 李晶玉(Ri Jong Ok) 武蔵野美術大学、灰原千晶(Haibara Chiaki)】
東日本大震災後の「気付き」から生まれた「渡れるかもしれない橋」
‐お互いの交流が始まったきっかけは何だったのでしょうか?
灰原 2011年、私が袴田(京太朗:油絵学科教授)ゼミで、朝鮮大学校の男子寮に面した壁に「渡れるかもしれない橋」を制作した後、朝鮮大美術科がSNSをテーマにした「NOW」展を開催していたので、ゼミで観に行ったんです。
李 「NOW」展は外に向けて広報をしていたので、多くの人が来てくれました。
そこで、灰原さんと初めて話をして、「橋」を作っていたことを知りました。
男子寮の、女子立ち入り禁止区域でやっていたので全然知らなかったんですよ。
‐2011年というと東日本大震災があった年ですね。「渡れるかもしれない橋」の制作には東日本大震災も影響しているのでしょうか?
灰原 そうですね、あの出来事で、感覚的なものが変わりました。
男子寮の前で作品を制作した理由は、もともと配当されたアトリエが武蔵美の端っこにあって、向こう側の声がよく聞こえていたからだったんです。
でも、実は声が聞こえることを自覚したのは、震災の後でした。
声が聞こえて、向こうにはどんな人が居るんだろう?と思った。
話しかけてもらうきっかけになれば良いやと思って、物理的に渡るための橋じゃなくて完成のない構造体を作ったんです。
そしたら、本当に運よく話しかけてくれて、「何しているの?」とか。
雨が降ってきたときは、「傘持っているの?」とか(笑)。
そんな風に、終わりの無い作品だったんですけど、期間だけ設けて、その間だけずっと作っていたり、記録を残していったり、そうして出来たのが「渡れるかもしれない橋」です。
‐制作中は、塀の向こう側が朝鮮大学校だということをどれだけ意識していたのでしょうか?
灰原 朝鮮大学校だとはもちろん知っていて、世の中には色んな人達が居ますけど、心ない人たちにとっての「的」になっていることも知っていました。
でも、あくまでも個人的なものとして作っていました。
‐社会問題に寄せた作品ではなく、311を体験した後の一個人の心情としての作品ということでしょうか?
灰原 311を体験した後の「気付き」みたいなものです。
自分が作るうえで社会問題に寄せてしまうと、自分の実感とズレていく。
あくまでも自分と相手との瞬間瞬間のやりとりとか、関係性を大事にしたかったんです
「道は塞がったまま、無理やり進んだ」今回の企画展
‐その後、2013年「この場所にいるということ」、2014年「孤独なアトリエ」と合同展覧会が続いていきます。
李 実は、最初の合同展は2012年の4月で、「武蔵美×朝鮮大」とは題していないけど、「同じ作り手としてなぜ作るのか?」というテーマ設定で合同展をしました。
けど、これが終わった後にどうしようかとなって、どうしていくのかが私も掴めなくて、一旦話がストップしたんです。
「この場所にいるということ」と「孤独なアトリエ」展は、袴田先生企画ですね。
‐話がストップした原因、どうしようかとなった原因は何だったのでしょうか?
灰原 作品を作って展示が終わって、じゃ次は何をする?というときに、当時はそれ以上の先が見えなかったんですね。
李 次の展示をどうしようか?という話になったときに、朝鮮大美術科という立場だから、どうしても自分が在日という立場で、灰原さんが日本人という立場からのスタートになる。
そうすると、「在日」という要素を無視出来なくて、お互いの歴史の教科書を交換したりとかしたんです。
そういった、政治的な問題や歴史問題に踏み入ってきたあたりで、だいぶ行き詰っちゃったんですよね。道が塞がっちゃったように感じました。
灰原 私自身、知らないことが多すぎたんですよね。でも、作品を作ることで、歴史の正しさを主張したいわけじゃないし、ちょっと見えないと思って。ただ、すごく気にはしていました。
‐今回の企画展では、その行き詰まり感を打破したのでしょうか?それとも、まだ先は見えないけれども、やるしかない!と腹を括った感じなのでしょうか?
李 私は後者に近いかな。結局この橋も、決して、差異だとか違いを乗り越える、克服するような装置ではないと思っているんです。
道は塞がったと感じたけれども、今回の印象で言うと、塞がったまま無理やり進んだ感じがしますね(笑)。
灰原 今回は「対話」がテーマなんですが、2012年に一回断念したし、今回もいっぱい止まったし、転んだし、いろんなことがありました。
だけど、じゃ、この分かり合えない壁とは何だろうな?と考えるようになりましたね。
壁を「ひょい」と乗り越える行為が想起させるもの
‐分かり合えない壁を共有しながらの対話は想像以上にエネルギーを消費しそうです。それでも、ここまで企画展を進められた背景としては何かあるのでしょうか?
灰原 それは、「孤独なアトリエ」展(2014年)って、武蔵美のFALでやったあとに、朝鮮大学校の美術科で巡回展をしたんです。
FALと朝鮮大学校の美術科展示室って両校の間の区画壁を隔てて近いから、作品を運ぶときにわざわざ武蔵美の正門から出て、道路を通って、また朝鮮大学校の正門から入ってくるよりも、作品保護のリスク的な面でも、時間的な面でも、壁越えをしたほうが良い、という。
それで、私はその展覧会に参加していなかったのですが、後で出展者のチョンオギ(李)に、作品が壁を越える動画を見せてもらったんです。
その作品の壁越えがすごく魅力的に写って、「ひょい」っていとも簡単に行ってしまうその行為が想起させるふり幅に、すごく驚いたし、すごい魅力を感じましたね。
袴田先生から「今年、橋かけちゃう?」と提案されたときに、何かが出来る気がする、って数年前に断念したときとは違う感覚がありました。
両校を隔てる「塀」の正体とは?
‐今回の企画展での「塀」に対する認識がすごく興味深いと思いました。
フライヤーでは「双方の立場を明確にし違いをあえて強調するものならば取り払ってはいけないもの」と書かれています。
李 これは、梨愛(鄭さん)が書いた文章です。
‐今回の企画展で、塀が断絶を象徴するようなものだったら、それを壊すようなデモンストレーションも、またそのようなアート作品も作れたと思いますが、そうじゃなくあえて橋を架ける選択をする。
私個人の考え方ですが、いま、「多様性だ」とか「みんなで仲良く」だとか言っていても、結局マジョリティーがマイノリティーを抑え込んでしまって、かえって違いや差異が表面しづらくなり、問題が地盤沈下するように感じていました。
鄭 それは、塀を取るという案で話が進みそうなときに、書いた文章なんです。
私は、塀を取るという案に対してすごく拒絶反応があって、塀は、壁はむしろあってほしいし、それはいじっちゃダメだと思ったので、それをとりあえず文章にまとめたんです。
灰原 わたしは、塀を取る案が出たときに、「それでも良いじゃん」と思ったんですよ。川が二本流れていて、間のしきりを取ったら溶け合うじゃないですか。
そんな風にしか考えていなかった。塀を取っても、断絶というか、境が意識されなくなるわけじゃないし、って。
でも、日本に多文化主義はないということを前提に、多文化主義とは何か?という講義に参加する機会があって、そこで「同化主義」という言葉が出てきて、ハッとしたんです。
今回の企画展を進めていく対話の中で、何度かしている失敗ではあるんですけど、無意識にマジョリティー側の意識を押し付けているんだと自覚しましたね。
そういうつもりは無かったのに、同化主義的な考えだったんだなって。
(写真:朝鮮大学校側から武蔵美を見て)
(写真:今回の企画展のフライヤー)
‐塀を壊すというのはどういう経緯で出てきたアイデアだったのでしょうか?
李 両大学側を繋いで行き来ができるようにするのはセキュリティーの面で、双方の大学が神経質になるんですよね。
さらに6月頃には武蔵美側で、2メートル以上は違法建築にひっかかるかもしれないから架設は難しいという話が出て、武蔵美側から「もう塀をとっちゃうのはどうか?」という案が出たように思います。
そのときは、断ろうとも考えましたし、今回の企画は何回か頓挫しかけていますね。
‐フライヤーに掲載されている鄭さんの文章では、「閉塞する塀がときには何かから守る壁にもなる」と書いていますよね。
李 自分の中でも、「同化」に対してすごく敏感なところがあって、日本人と在日という曖昧な差異を、むしろ差異化するためにやってきた歴史を安易に地続きにしてしまうのでは、今まで練ってきた企画とだいぶ性格が違うなと思いました。
‐どうやって武蔵美側を説得したのでしょうか?
灰原 大学側とのやりとりの矢面に立ってくれていたのは、武蔵美側は袴田先生なんですけど、学長会議に出る袴田先生に、鄭さんの文章を託して、そこで学長も読んでくれて、それで動きましたね。
「綺麗な交流ではなかった」
‐なるほど、決して何事も順調に進んでいった企画展ではなかったようですね。
紆余曲折を経て、「突然、目の前がひらけて」、今は何が見えているのでしょうか?
灰原 わたしたちもまだ何が見えるかはわかっていないです。暗いところから、光が差しているとして、光源が何かはすぐにはわからない。
でも、今回の「対話」は、展覧会が終わって、数年後、数十年後まで自分の中でテーマとなるようなものを残すかもしれないですね。
李 決して、綺麗な交流ではなかった、というのが一番面白い部分だと思っています。
「橋を架ける」ことをゴールにして、対話を一年間ずっと続けてきたんですけど、そのなかで執拗に全員が分析し続けるんです。
自分の考えだとか相手との差異だとか、相手が何を言っていて、それで相対化された自分の形だとか、本当にしつこく分析していました。
でも、そのプロセスを経たからこそ、作り上げることができたんだと、最近思うようになりましたね。
‐李さんと鄭さんは、一在日朝鮮人で、一女子大生で、一美大生でもあり、色んな側面があるなかで、あえて一在日朝鮮人に拠り立つ意識から始まる「対話」の中から逃げたくなるようなことはなかったのでしょうか?それこそ、どこか知らない土地に行って、1人の人間として過ごしたいと思うようなことは?
李 思いました、ドイツ行きましたし(笑)。
でも、灰原さんも自分がマジョリティーとして見られることへの葛藤を話してくれて、属性をつきつけられることって、誰しもが苦痛を伴うものなんじゃないかと思う。
そういう面ではお互い双方苦しんだのかなと思います。
灰原 ミーティングで、土屋というメンバーが、「属性をとりあえず置いといて個人の意見を聞きたい」と言ったときに、私はその発言を、属性を切り離せるかどうかの解釈の問題だと思って、私は、「属性は切り離せないと思う」と言ったんですよ。
オーストラリアにホームスティ行ったときに、自分が日本人だということやアジア人であることから、自分がこう見られたいという通りに誰しもが受け取ってくれるわけではないと感じた経験もあったんです。
だから、属性はそんなに切り離せるもんじゃない、と思いましたね。
今回の対話には、同時代性のリアリティーがあった。
‐戦後70年という区切りを意識はしなかったのでしょうか?
李 企画のお話が持ち上がったのは去年でしたし、そこまでは。
灰原 戦後70年に繋がるとしたら、自分が歴史の地続きの上に立っていることへのリアリティーの無さ、マジョリティー側のバックグラウンドへの意識の希薄さとかは、今回のなかで考えたりしました。
以前、李と教科書を交換したときに、日本の教科書は戦前と戦後の日本を分けて捉えているような感覚を持ったと言ってくれて、そうかもねと思ったんです。
この日本で日本人として生きているという意識はすごく希薄だと思うんですよ、私だって。
私は祖父母が広島に住んでいるので、夏になると原爆ドームに行くんです。
そこにいるときや祖父母の話を聞くときは、そういう心持で聞きますが、でも自分の家に帰っても何か思うのは、甘いものを食べたいなとか(笑)。
‐私も身に覚えがあります。大事なものなのに、ついオンとオフを切り分けてしまうような。
灰原 それは、同時代性のリアリティーって、その時代に生きた人じゃないと感じられないからなんです。例えば私が祖父の話を聞くとき。
祖父の妹は戦時中に女学生で、敵の飛行機が来るから友達と一緒に走って逃げていたんですけど、機銃掃射で、銃を撃つ「ガガガ」という音の後、隣で走っていた友達は粉々になっていた。
そういうのは、凄すぎて、イメージが追いつかないですよね。
今、自分の国は敗戦国だという意識とどんどん乖離していて、そういう風に大事な国の歴史をリアリティー持って引き受けられなくても、同世代で隔たりがありつつも一緒にいる仲間がいて、お互い身を開いて、対話をして、そこで得られるものには、今の同時代性のリアリティーがあると思うんです。
伝承していくことも、伝承されることも大事だと思うんですけれど、聞いて話してもらってやっぱり驚くし、でもいつの時代でも、同時代の対話のリアルさには代えられないものがあると思います。
積み重ねてきた対話から、何をどう感じ、どう汲み取るのか
‐本企画のフェイスブックページ上では、差別的な好ましくない表現を伴う意見もありますが、それに関してはどう思いますか?
灰原 ヘイトスピーチや、マイノリティーを傷つける言葉の存在を知ってはいましたし、今回の企画展で、そういうものが来るだろうともメンバー内で予想はしていたんです。
でも、いざ来たときに一瞬ヘイトだとは気付けなかったんですよ。
でも、彼女たちの顔を見て、声を聞いて、話をしてやっと気付けた。
ヘイトスピーチが、友人を傷つける行為だという知識はあっても、実感が無かったことがショックでしたね。
想像することが自分の職業なのに、大丈夫?と思いました。
李 ミーティングの後に、「私、想像力が無かったな」と、灰原さんが、そう言ってくれたのが印象に残っていますね。
‐なるほど。しかし、多くの人にこの企画展を知ってもらいたいと思えば思うほど切り離せない厄介な問題と言えそうですね。当初はこの企画展を考えた時に、どれだけの人に広まってほしいと考えていましたか?
灰原 私はまず自分の問題としてやりたかった。
どれだけ広まるかは二の次で、でも広まればいろんな意見も出てくるからもっと面白くなるとは思っていました。
李 私は、この展示を自分のコミュニティである在日社会の人には知って欲しいとすごく思っていて、ミーティングの中で自分の在り方を何度も何度も問い直されて、壁の外に意識を向け続けた。
壁から一歩出て視点を逆転させてみる、というのは自分のコミュニティにも絶対に必要なことだと感じたし、それは在日社会に限ってのことじゃない。
社会的なメッセージになっちゃうのは嫌だけど、本当にそういう面でもなるべく多くの人に見てもらいたいです。
私たちの対話や、やりとりを実際にアーカイブとして展示しているので、批判だとか賛同だとか色んなコメントがあるけど、ぜひ来て見てもらって、何を感じて、「橋」をどう解釈するのか、何かをどう汲み取ってもらうか、感じてほしいです。
鄭 私は、今回身をもって、経験したことが無いぐらい強く、対話の難しさを思い知りました。
辛すぎたんですけど、でもまだ自分は恵まれている時代だなと思いました。今でも色んな膜に覆われてわかりづらくなっているのに、どんどんわかりづらくなって、複雑になってくると思うので、今の小さな子達はどう交流するんだろうと思いましたね。
速いスピードで変わっていく中で、対話をするというのは生易しいものじゃないです。
ものすごい量の思弁をしないといけないし実践に移さないといけないし、だから「素晴らしい!」とか「乗り超えた!」という風に言われると違和感があります。
‐では突然目の前がひらけてはいるけど、ひらけていないみたいな?
鄭 清々しい感じは無いですね。あくまでも、わたしが抱いている感想ですが。
当事者性がある作品を作り続けていく
‐最後に、将来どんな作家になりたいのでしょうか?灰原さんが「想像するのが仕事なのに」と言っていて、ハッとさせられたのですが。
灰原 作品を作るのに、自分は当事者性が必要だと思っていて、例えば見て「木」だとわかってもちゃんとそれを触って「木」だと感じるように、実感を持って、作品を作りたいですね。
李 日本でいまから作家活動をやっていくとなったときに、自分が在日というのを制作の中で取り外せるものでもないし、でも無自覚に扱えるほど自分に溶け込んでいるものでもないから、今、在日の3世ってすごく曖昧な形だと思っていて、だけど、やっぱり在日ということが根本にならなきゃなぁ、と。その上で、奔放でありたいなと。
鄭 うーん。将来像は見えないのですが、生きる拠点はここ(日本)だと思うので、ここで生きていくなかで、今回の企画展を通じて、在日朝鮮人でマイノリティーという立場をちゃんと自覚して、その立場と付き合っていけるような気がします。
(写真:朝鮮大学校美術棟)
あわせて読みたい