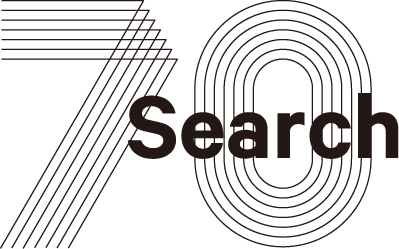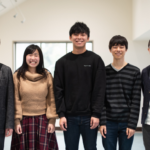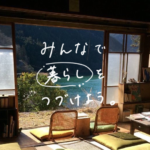市内に300箇所以上の「うちぬき」と言われる、自噴式の井戸がある街、愛媛県西条市。水の良さをもとに、昔から酒造りが盛んなこの土地に140年の歴史をもつ一軒の酒造がある。
今回の主人公は、代々受け継がれる伝統を守りながらも、そのプレッシャーに押しつぶされることなく自分の人生を貫く1人の男性だ。
#1定められた運命、自分で切り開く道

西条市内でもっとも古くから続く成龍酒造。その家に長男として生まれた首藤英友さん。
お酒に情熱を注ぐおとなたちに囲まれて育ち、幼少期から家を継ぐという意識はあったという。
しかし、家の後継に生まれたことによる小さい頃からの周りの期待、跡取りはこうあるべきという姿に固められていることがあまり好きではなかった。
「自由に生きたい。そのことが常に頭の片隅にありました」
大学を決めるとき、醸造学と経済学のどちらを学ぶか悩み、経済学を専攻することにした。
進学先は山口県。
経済学を選んだのも、山口へ行くことを決めたのも、自分がそうしたくて決めたことであり、決められたわけではない。
「全て好奇心で決めてきました」
英友さんが専攻に経済学を選んだのはお酒の造り方よりも、お酒が作られたあとにどういう風に世の中を流れ、お客様の手に届くのかを知りたいとの思いから。山口へ進学したのは、愛媛から出て、外から故郷を見たいという思いから。
就職活動時に実家に戻るかどうかという選択を迫られたときも、東京で仕事をしてみたい、大学で学んだ流通の世界を自分の目で確かめてみたいというという好奇心に従い、東京にあるお酒の卸会社で働くことを決めた。
英友さんが家業を継ぐ決断をしたのは、26歳で帰る1年前のことだった。
#2近くから遠くへ、遠くのものを近くに

現在は常務取締役として働く英友さん。
「経営に関する判断はもちろん、実務としては何でもやる、何でも屋です」
大学や前職で学んだことを活かして、プロモーションやお酒をどうやって流通させるかといったことを日々考えている。冬は酒造りをし、他のシーズンは日本全国、時には海外にも日本酒の魅力を伝えるため走り回る日々。
成龍酒造きっての杜氏、織田さんと兄の敏孝さんという、ふたりのスペシャリスト。彼らの仕事が輝くのも、ジェネラリストの英友さんあってのことだ。だれか一人でも欠けてしまっては成り立たず、織田さんとは血が繋がっていなくともまさに家族のよう。
それだけ距離が近いからこそ一緒に仕事をする上で英友さんは人一倍コミュニケーションを大切にしている。
原料を作るひとたちの考え、お酒をつくる自分たちの考え、それを手に取る人の考えがイコールになることを心がけている。遠くのひとに思いを届けるためにも、まずは自分たちの思いが通じ合っていることが大事なのだ。
「お酒は人の心を響かせるものでなくてはならない」という英友さんは、お酒をもっとわかりやすく伝えられないかと試行錯誤した。
そんな時に出会ったのが切り絵職人の塩崎さん。作品を見て故郷を懐かしみながら酒を酌み交わせるような、地域性を出したお酒を造ろうというコンセプトが塩崎さんと合致し、ラベルを作ってもらうことに。
お酒と切り絵。遠いもののように見える2つのもの。それらが近くなり重なりあったことで視覚的にお酒を伝えることができ、より多くの人へその思いが届くようになった。形は違えど、共通するのはイメージを形にして伝えていくということ。
「コミュニケーションはなにも口と耳だけでするものではないと思うんです」
鼻で感じ、目で感じ、舌で感じる。こうやって伝える手段が増えることで、いろんなものを感じられるようになるとお酒の飲み方がもっと豊かになる、と英友さんは想いを馳せる。
切り絵だけでなく、バッグや水引などを様々なものとコラボをしている。そうすることで酒の造り手である自分たちにはない感性をもらっている。遊びの発想から入ることが多いというが、それができるのも、1つのことにのめり込み過ぎずに視野を広く、様々な経験をしてきた英友さんだからこそなのかもしれない。
#3不変のもの、変えてゆくもの

インタビュー中、ふだんから様々な役割を担っている英友さんがふと見せた本音がある。
「普段と違うことをすると疲れるんですよね」
酒造りは12月から始まり、そこから4ヶ月間はほぼ泊まり込みになるという。常にお酒と一緒の生活だ。
朝5時半から、前の日に洗ったコメを蒸しあげて、その間に別の作業をする。蒸し終わったらスコップで掘って、様々な用途に振り分けていく。午前中にこの作業を2、3回して、昼食後からまたお米を洗い続ける。
そういう時間が夕方まで続くなかで、新酒を絞る作業をしたり、絞った酒かすを取ったり、いろんな作業を同時にする。激務ではあるが慣れてしまえばルーティンだから平気だという。この生活は変わらない。
その一方で、お酒を通じて地元の良さを伝えたい、酒の詳しい人やそうでない人に合わせてうまくお酒の提案をしていけるようにしていきたいという想いを達成するために奔走する毎日。
「伝統を守りつつも、変える部分は変えないと生き残れませんから」
蔵開きのイベントをしたり、いろいろなコラボをしたりと、それまでの型にはめられるだけではない酒造の姿を、英友さんと成龍酒造はこれからも見せ続けていく。
あわせて読みたい