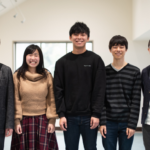サクサクとした軽い食感、お米と砂糖の素朴で優しい甘さがどこか懐かしいポン菓子。
それが今、大都市圏のライフスタイルショップや外資系ホテルをはじめ、全国100店舗以上で取り扱われ、香港などの海外にも販路を拡大しています。
仕掛け人は、愛媛県西条市にある「ひなのや」の代表、玉井大蔵(たまいだいぞう)さん。
子どもたちが小銭を握り締めて買いに行っていたポン菓子が、どのようにしてそのブランド力を上げていったのでしょうか。
仕掛け人である玉井さんにお話しを伺いました。
強く脆かったブランド

愛媛県西条市の山あい、丹原町にある農機具屋の長男として生まれた玉井さん。高校・大学時代は親元を離れ進学しましたが、特にやりたいことは決まっていませんでした。
気づけば就職活動の時期。学生の頃から「ブランド」への憧れが強かったという玉井さんが面接を受けたのは、名前の通った会社ばかり。
「陸上部に所属していた高校時代は、スポーツメーカーなら『アシックスがいい!』とか思っていました」
就職先を選択するうえで重要視していたのも、仕事内容よりもブランド名や知名度でした。晴れて大手電機メーカーへ就職し、自分が憧れていた社会人生活のスタートを切りました。
ところが一転、入社3年目の春、玉井さんの思いもしない出来事が起きます。
一事業部門の分社化と経営統合により勤める会社の社名が変更。玉井さんが思い描く、企業ブランドに誇りをもって働く自己イメージが一気に崩れた瞬間でした。
社名が変わったことにより仕事に対するモチベーションは下がるばかり。実家に戻るたび、無意識のうちに父親に会社の愚痴を漏らしていました。その姿を見た父親からの言葉は「そんなに嫌なら帰ってきたら?」
ブランドは土台があってこそ

いつかは故郷・丹原町に帰って家業を継ぐことを意識していた玉井さんは、思い切って入社5年目に退職。西条市へのUターンを決意しました。
家業の農機具屋を3年間続けた玉井さんでしたが、そのライフスタイルは、玉井さんの理想とは異なるものでした。
「決まった形の仕事を淡々とこなすのは、自分には向いていないんだと思います」
全国的に農家が減少し、跡継ぎもなく高齢化が進んでいる今、農機具のみで生計を立てることに対して日に日に増していく不安。このままではいけないと思い、農産物などの豊かな地域資源を活用して新たな付加価値を生み出す「6次産業化」に賭けてみることに。
「この方法なら、農家の収入が上がり、農家の減少を緩やかにできるかもしれない。この美しい田園風景を残す手段になるかもしれない」
そんな期待が膨らむなか思いついたのが、米の加工品。
「米は、農機具屋のお客さんの中にも作っている人が多くなじみが深かったです。お客さんから『歳をとって米農家を続けられないから、代わりに米を作ってほしい』といわれたこともあって、米を加工してみようと思ったのがスタートでした」
米の加工を始めるとき、アドバイザーの一言で購入した「パン豆機」が手元にあったのを思い出した玉井さん。西条市の位置する愛媛県東予地方では、ポン菓子は「パン豆」と呼ばれ、結婚式の引き出物の定番ということもあり、パン豆で勝負することに。
当初は販路をもっていなかったため、産直市に卸す日々。そんなある日、一般的な砂糖を絡めたもののほか、キャラメル味のパン豆を作りました。
「『ポップコーンにも色んな味があるんだから、パン豆にも色んな味があっていいんじゃない?』って奥さんに言われて作ってみたんです。そしたらそれが意外と売れまして」
これはイケる。「パン豆」一本でやっていこうと決心した瞬間でした。
ブランドへのもどかしさ

一方で、パン豆を始めて間もない2010年ころは、都会への未練や地元の環境への物足りなさを感じていた玉井さん。都会に対する劣等感もありました。でも帰ってきたからにはこの場所で納得のいく仕事をしなければ。そんな葛藤を続けていました。なんとか「パン豆」で都会とつながる方法はないか。
「自分で考えて、自分で動かないといけないと思い始めたのは、『パン豆』を始めてからでしたね」
「パン豆」をどんな「ブランド」にしたいのか。お客さんにどんなイメージを持ってもらいたいのか。そう考えたとき、よく読んでいたライフスタイルマガジンに掲載してもらえるような、クオリティの高い目を引く商品にしたいと思ったこと、それが「パン豆」のブランドイメージの軸になりました。
そうは言っても、いきなり都会への販路はありませんでした。転機は、地元の特産品を紹介・販売する「西条市食の創造館」への卸売。ここにたまたま立ち寄った、お隣の県、香川県高松市にある人気雑貨屋のバイヤーがパン豆を気に入り、雑貨屋に並べてもらえることに。
「このころ香川県では、瀬戸内海の島々を舞台にしたアートフェスティバル『瀬戸内国際芸術祭』が初めて開催された年で、国内外からの観光客にとどまらず、都市部に店舗を持つ有名なショップのバイヤーたちも高松の地に集まりました。『パン豆』が置かれた雑貨屋にも多くの人が立ち寄り、うちの商品を見つけてくれました。運が良かったんです」
こうして「パン豆」は都会へと羽ばたきました。
揺るぎない信念とともに

「ひなのや」が目指すべきものは何なのか。その答えは「シビックプライド」でした。
「『シビックプライド』は、『郷土愛』とは少し違った概念で、自分自身が地域づくりに参画する、地域を構成する一員として関わっていくということだと解釈しています」
「シビックプライド」と出会ったことで、気づいたこと。それは、「ひなのや」が地域にとってどういった役割を果たすべきか。モノを売るだけがお店ではないということ。
「僕はきっと創業当時から菓子職人ではなかったんです。例えば、パティシエなら今あるケーキをより美味しく作り上げることを突き詰めていくと思うのですが、『ひなのや』の土俵はそこじゃない。どれだけ地域の雰囲気や良さを商品に乗せられるか。『パン豆』があることで、地域と外のまちの交流人口をどれだけ増やせるか。それこそが僕のライフワークだと確信しました。
好きな『ブランド』の本社があるまちを想像してみてください。行ったことがなくても、素敵なまちに違いない。そう思いませんか?」
西条というブランドのために

同じように、西条、愛媛、四国に行ったことはないけれど、「ひなのや」があるまちはきっといいまちだ。そう感じてもらえるお店にしたいと凛とした眼差しで語る玉井さん。
商品づくり、ブランドづくりは、地域の一員として地域と関わっていくこと。そう思うようになってから、地域の素材を取り入れていくようになったといいます。西条の田園風景や里山風景が、パッケージや包装紙、フレーバーなどの重要な要素になっているのです。
「ひなのや」が大切にしているもの。それは地域の人たちや「パン豆」を買ってくれた人に「ひなのや」というブランドを好きになってもらうこと。自分の住んでいるまちにはこんなに素敵なお店があって、それがまちの自慢になることだといいます。
最後にこんなエピソードを聞かせてくれました。
「100歳近くのお母さんを亡くされた70歳近い息子さんが、お葬式の前にパン豆を買いに来てくれました。お母さんの棺桶に入れたいというんです。老衰して食事もままならないお母さんが、うちのパン豆を食べたいといいながら亡くなったそうです。『ひなのや』を最期の最期まで好きでいてくれたことが本当にうれしくてたまりませんでした」
続かなければブランドではない

このほど西条市に着任した、起業型地域おこし協力隊「Next Commons Lab西条」が立ち上げるプロジェクトのアドバイザーとしても活躍する玉井さん。これから創業する若者にアドバイスはありますか?と尋ねたところ、こんな答えが返ってきました。
「お店を続けられる体制づくりが必要ですね。ひなのやの目標は、まちの自慢として定着するために、100年続くお店にすること。100年続けるためには、自分がいなくなった後もお店を守り続けなければならないということです」
「組織に属していると、自分が抜けても社員全員の力でカバーしあいながら業務を進めることができます。でも、個人での創業は自分たった一人のことが多い。一番重要なのは、自分がいなくても会社が回って、安定したサービスを発揮し続けられる体制づくりなんです」
都会に対するコンプレックスがあったという玉井さん。
「でも、そんなに気負う必要はないんです。だって、『パン豆』でも都会の一等地に置いてもらえるんだから」
それでもまだまだ道半ばという玉井さん。
地域内外からのお客様の受け皿として滞在できる販売拠点を整備したいと話す玉井さんの瞳には、ひなのやを中心に地域や「ひなのや」が好きな人が集まり、さらに好きな人が増える。そんな、「ひなのや」が理想とするちょっと未来の姿が、はっきりと映し出されているようです。
ひなのや
Facebook https://www.facebook.com/hinanoya/
あわせて読みたい