「自分を愛するための音声メディア」をご紹介する本企画。筆者自身が考える音声メディアの魅力をお伝えした前回に続き、今回からは実際に番組をいくつか紹介していきたい。
初回に取り上げたいのは「VOGUE JAPAN Podcast」。編集部の方がゲストを招き、恋愛やファッション、自己愛について語り合う内容だ。その中でも、私の心を幾度となく救ってくれた西加奈子さんの回についてお話ししたいと思う。
西さんは人の弱さも醜さも、ありのままを受け入れる力を与えてくれる。「諦める」の本来の意味は「明らかに見る」であるように、人の不器用さを美化するのではなく、「悩んでてもいい」「自分を好きになれなくてもいい」と、そのままの私たちを優しく見つめてくれる存在だ。
そんな西さんの包容力と明るさは、いつも私の背中を押してくれた。今回は、お仕事において「失敗してはいけない」と過度なプレッシャーを感じてしまう方にとって、少し肩の力が抜けるような視点を西さんの言葉と私の実体験を織り交ぜながらお届けしたい。
うつ病になった父のこと
私がこの番組を何度も聴くようになったのは、父が仕事を休み始めた頃だ。父は30年間、大手の証券会社の営業マンとして働いていた。単身赴任で北から南まで移動を繰り返す日々を終え、56才、事務職への異動が決まった。辞表が出てからたったの2週間で、今までとは全く違う仕事を始めなくてはならない。働く場所も内容も、会社に委ねられる大企業ならではのシビアさにも、父はすっかり慣れきっていた。
本社で行う細やかな作業。営業畑にいた父にとって、けして得意と言えるものではなかった。年下の社員たちからの「なぜ、できないの?」という厳しい視線、ため息が聞こえてくる日々。営業の最前線で働いてきたという自負を持つ父には、かなり堪えただろう。
それからの父は徐々に会社に行けなくなり、うつ病という診断を受ける。サラリーマン人生初めての長期休みをとることとなった。
半年間休んでもなお「できない自分」「こんなはずじゃなかった自分」を受け入れられずにいる。市役所でのちょっとした手続きでさえも、準備した通りに事が進まないとパニック状態に。
職場での適応障害の影響もあっただろうが、きっとそれはきっかけにすぎない。この30年間、あまり友人も持たず、ひたすら結果にコミットしてきた父にとって、人との関わりは商談であり、勝負の場となってしまっていた。何でも器用にこなして、しっかり結果を出してきたサラリーマンとしての父の末路は、「失敗は許されない」という呪縛に囚われた姿だった。
そのプレッシャーは誰のせい?
この「失敗は許されない」という感覚は、父ほど深刻ではなくても、私も何度も体験してきたように思う。大切な仕事の前には、眠れなかったり、ご飯が喉を通らなかったり。このプレッシャーの積み重ねが“人との関わり=勝負の場”という方程式を徐々に定着させてしまうのかもしれない。最初は誰かにかけられていたプレッシャーも、いずれ自らに浸透させてしまうのだ。
この漠然とした不安感は自分で乗り越えなければならないものだという意識をどこかで感じていた。どうしたら和らげるか、なぜここまでプレッシャーに感じてしまうのかを考えてみても、「慣れるしかない」「気を楽にして」という応えしか浮かばず、遠回しに「自分自身の問題だよ」ときつい言葉を自分に投げかけていたように思う。
苦しそうな父を見る度に「なぜ、こうなるもっと前に肩の力を抜いてあげられなかったんだろうか」と後悔が募る。この厳しいストレス社会で、父や私たちは、どうしたら自分に優しい言葉をかけてあげられるのだろうか。
自分に優しくあるための“代替可能な私たち”
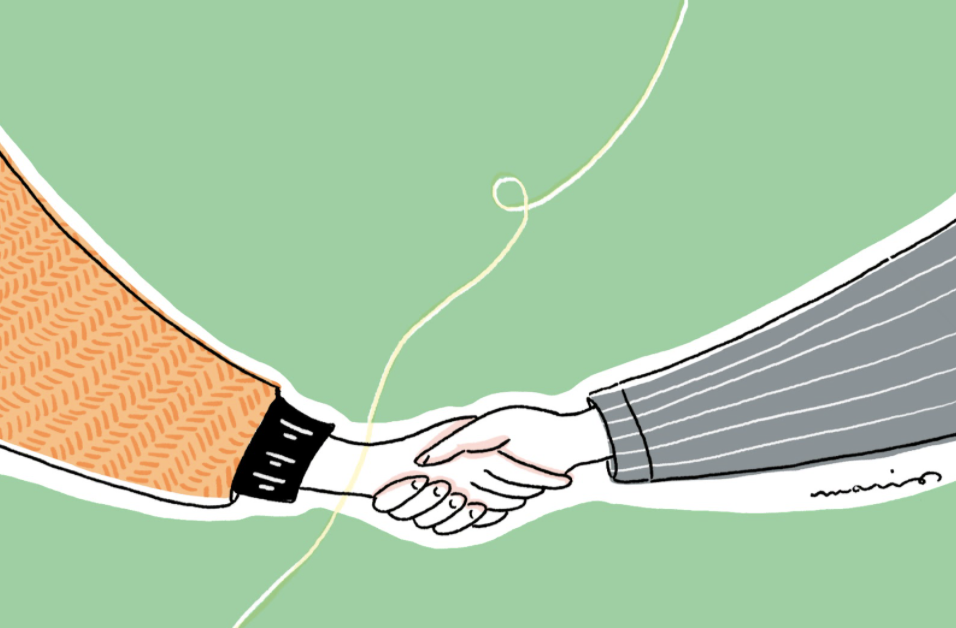 父にできることは何だろう、そんなことを考えていたある日、出合ったのが西さんが出演する「VOGUE JAPAN Podcast」だった。視聴者から寄せられた相談に、西さんがおすすめの書籍と共に応えていく番組だ。
父にできることは何だろう、そんなことを考えていたある日、出合ったのが西さんが出演する「VOGUE JAPAN Podcast」だった。視聴者から寄せられた相談に、西さんがおすすめの書籍と共に応えていく番組だ。
どの回も生きづらさを少しゆるやかにしてくれるような、西さんらしい言葉と視点があふれている。特に印象に残ったのが「#5 私たちはみんな取替可能なたったひとりの自分 ーーそう考えると生きやすくなる。」というテーマの回だ。
「プライベートは自分だけのことだから平気でも、仕事は周りに迷惑をかけると思うとプレッシャーで眠れなくなってしまう」という20代の女性からのお悩みに、西さんは「十分がんばってるよ」と優しい声で応え始める。
「あなたはすごく真面目で誠実な方だから、『人に迷惑をかけたくない』『仕事は自分だけの問題じゃない』とおっしゃる。でも、仕事ってあなたが言うのとは別の意味で、自分だけの問題じゃないはず。仕事はチームや会社で行うもの。あなたがここまでプレッシャーを感じるのは、仕事の体制に何か問題があるんだと思うんです」
「話が大きくなっちゃうけど、個人の失敗が許されないとか、あなたのせいでチームや会社に迷惑がかかるとか、そんなことを考えなくちゃいけない社会自体に問題があると思います。チーム、会社、そしてもっと大きな社会全体で考えなければいけないことです」
そして、西さんは松田青子さんの『スタッキング可能』という小説を紹介しながら、私たちの代替え性について話していく。何者かになりたい私たちは、自分にしかできない仕事をどこかで求めているのかもしれない。しかし、私たちは皆、代替え可能であり、それはけしてネガティブなことではないと言う。
「私は自分のことが大好きで、小説売れたいなって気持ちがあるんですけど、当たり前だけど、私の小説だけ売れる世界には絶対に住みたくなくて。あらゆる人の本が読める本屋さんにいたいし、その中のひとりであることがすごく大切なんです」
「いろんな人がいるからこそ、私は自分が好きな小説を思う存分書くことができる。もし自分しかいなかったら、社会を代表するような気持ちで書かないと!って、プレッシャーになりますよね。のびのびと自分らしくあるためには、いくらでも代わりがいる状態が必要だと思うんです」
自分を大切するためには、チームや会社、社会の中で代替可能な状態を作っておくこと。逆に、誰かが苦しんでいるときは、その人が楽になるように、“代替可能な私たち”が流動的に役割分担していく。そんな社会のあり方は、常に誰かとつながることを選択してきた私たちにとって、けして夢物語ではないように感じる。
「代替可能な私と、たった一人の自分は矛盾しないんですよ。私たちはたった一人の自分を大切にするために、世界に優しくするんです」
世界に優しくするのは、人の心が美しいからではないのかもしれない。「いつでもバトンタッチするよ」という優しい眼差しを与え合う社会であれば、自分の身に何かあったときも、頼もしい“代替可能な私たち”がきっと手を差し伸べてくれる。世界に優しくあることは、自分に優しくあることと同義なのだ。
父の代わりにできること
自分に優しくあることと、世界に優しくあることを両輪で回していく。これまで自分に対してはもちろんだけれど、周りにも厳しい目を向けてしまっていたと反省させられた。
あまりに自分にしかできない仕事を追い求めていくと、チームや会社の仲間であるはずの人たちが、私の仕事を奪いかねない敵に見えてきてしまう。本当だったら、互いの凸凹を生かしながら手を差し伸べ合えたはずなのに……。
父も今では、あまりにも簡単なことでイライラしてしまっていた自分に気づくようになったという。レジが並んでいたり、満員電車で誰かとぶつかったり、自分の向かう先だけを考えていたら、それらは障害に思えてしまう。しかし、レジにいるその人も電車にいるその人も、同じ社会を構成するひとりであり、手を差し伸べ合う“代替可能な私たち”のひとりなのだ。
これまでは、“逞しい父親”という役割を私も父自身も求めすぎてきた。今よりも家族像や働き方の選択肢が限られていた時代を過ごしてきた父にとって、「父親はこうあらねばならない」という意識はとても根深いものだろう。それでも、私が大人になった今、私たちは家族というひとつのチームだ。父がこれまで私を助けてくれたように、今度は、代替可能な私が手を差し伸べる。そうやって、役割に縛られず、流動的で温かな社会への眼差しは、プレッシャーに押しつぶされそうになる気持ちを少し軽やかにしてくれる。
■紹介した番組
VOGUE JAPAN Podcast
西加奈子さん「#5 私たちはみんな取替可能なたったひとりの自分 ーーそう考えると生きやすくなる。」
あわせて読みたい











