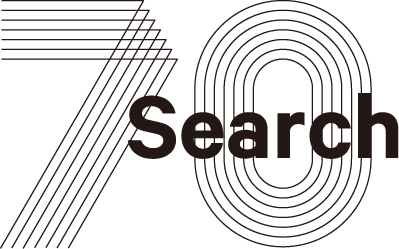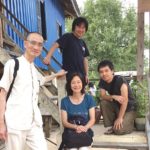私の祖母は今年で96歳になる。いまだにボケる様子もなく、口も達者で、自分で歩けないこと以外はピンピンしている。
でも、そんな祖母は最近、口を開けば「死にたい」と漏らす。
その言葉を発する頻度が増えたのは、今からちょうど3年前。祖母が、老人ホームに入居した年からなのは明らかだった。
施設の人は親切で一生懸命だし、施設を手配した母も全力を尽くしたと思う。それでも、人の世話を焼くのが好きで、自分でなんでも仕切るのが大好きだった祖母にとっては、「世話をされる」だけの老人ホームの環境は、活力を失うばかりのようだった。
祖母に会いにいったある日の帰り道、なんとなく、未来に希望を見出したい気持ちになって「老人ホーム 楽しい」「老人ホーム 取り組み 画期的」などのワードで検索した。
そこで見つけたのが、今回取材させてもらった、伸こう福祉会の取り組み ——「仕事付き高齢者住宅」だった。
高齢者でも安心な「職場環境」

「今日お天気がいいから、ちょっと暑いかもしれないんですけど」
そう言いながら、伸こう福祉会の広報担当・荒川多恵子さんが連れてきてくれたのは、介護付き有料老人ホーム「クロスハート湘南台二番館」から車で5分ほどのビニールハウスだった。この場所で「仕事付き高齢者住宅」の「仕事」のひとつ——「野菜づくり」が行われている。
ほんのりと汗ばむ気温のビニールハウスの内側では、ルッコラやフリルレタスなど、たくさんの野菜が育てられていた。目を引くのは、腰の高さまである畑の床。東レ建設(株)が、「女性・高齢者・障がい者・療養中の方でも作業しやすいように」と開発した高床式砂栽培の農業施設『トレファーム®』を利用しているのだ。これなら車椅子の人でも、腰を曲げるのが難しい人でも作業ができる。
この日、仕事に参加していた入居者の方は、御年80歳のご婦人だった。
「今日やるのは、レタスの苗を畑に植え替える作業。こうやって、果物用のフォークを使うとやりやすいのよ」
興味津々で作業を眺める私に説明をしながら、慣れた手つきで苗を畑に植えていく。聞けば、これまで畑仕事の経験はないものの、この取り組みが始まった当初から参加し続けているので「もうすっかり慣れたわ」とのこと。
終始和やかな雰囲気で進んだ仕事は、20分もしないうちに終了した。それ以上やると、帰ってから身体に痛みが出たり、ぐったりしたりしてしまうので、毎回、作業時間は15〜20分で終えるようにしているそうだ。
どんなアクティビティよりも「仕事がしたい」

「老後の介護不安から介護付き有料老人ホームに入居した高齢者夫婦が、今度は、自分たちの預金と月々の年金収入のみで入居を続けられるかが不安だと言っている。こういった高齢者を雇用して、なんとか月5万円ぐらい稼がせてあげられないか?」
伸こう福祉会が「仕事付き高齢者住宅」の取り組みを始めたのは、高齢者と施設をつなぐソーシャルワーカーさんからの、そんな相談がきっかけだった。
この相談を聞いて、伸こう福祉会の理事長・足立さんが思い出したのは、自分たちの介護サービスを利用する高齢者からの「仕事がしたい」という声。「やりたいことは何?」と聞くと、少なくない数の高齢者がそう答えるという。
「仕事には、“自分は誰かを助けたり、喜ばせたりする存在だ” と感じられる喜びがある。すぐに5万円稼げる仕組みを作るのは難しいかもしれないけれど、仕事をしてもらうことが利用者の生きる力となるかもしれない。よし、やってみよう」
こうして、「仕事付き高齢者住宅」のプロジェクトは動き出した。
入居者にとっていいことは、施設のバリューにつながる

実現までのプロセスで、困難はなかったのかを荒川さんに尋ねてみると、「あんまりないんですよ」と、拍子抜けするような答えが返ってきた。
「仕事」への参加は義務ではなく、あくまで本人の希望に基づいた任意参加。「高齢者に仕事をさせるなんて」という声があってもおかしくないだろう、と思っていたが、むしろ入居者の家族から「ぜひ母にやらせてあげたい」と喜ばれることのほうが多かったそうだ。
多少のコストはかかるが、新しい取り組みをすることは、施設のバリューとなる。伸こう福祉会では、「広告宣伝費をかけて入居者を集めるよりも、施設としての価値を高めたほうが結果的に三方良しとなる」と考えているのだそうだ。
「アクティビティ」と違ってサポートを基本としない「仕事」なら、スタッフの稼働も最小限でいい。今は、ボランティアのスタッフや、介護スタッフ以外の施設スタッフが送り迎えなどを担当しているという。
仕事の内容は、保育園の補助業務や、施設の補助業務、企業向け介護・健康セミナーのスタッフなどを、ひとつひとつ手探りで試してきた。その結果、もっとも事業として形になっているのが、ビニールハウスで行われていた「野菜づくり」だ。
成功の要は、農業施設『トレファーム®』。同施設の活用を模索中であった、製造元の東レ建設と相談しながら、仕事付き介護住宅への利用に活路を見出した。その後、経済産業省による「健康寿命延伸産業創出推進事業」のモデル事業として名乗りをあげることで、補助金をもらいながら進めることができた。
「できた野菜は、近くの農家レストランに販売することで利益を出しています。そこからビニールハウスの維持費などを差し引いても、参加者への報酬として1回の作業につき300円ほどを支払うことができているんですよ」
月5万円にはまだ届かないが、入居者が自らの手で「稼ぐ」仕組みもできているのだ。
「仕事」がくれるのは、懐の安心だけじゃない

現在、「野菜づくり」に定期的に参加している入居者は、ぜんぶで10名ほど。
「単純にお金が目的で働いている人はほとんどいませんね。基本は「働きたい」「畑仕事をやってみたい」という純粋な興味で参加していて、報酬があることで、もともとあるモチベーションが2割程度上がっている印象です」
伸こう福祉会では、「仕事への参加希望者を、介護度によって切り捨てないようにしている」という。その理由は、この事業が目指しているのが、高齢者の「生きがいづくり」だからだ。
参加を希望する人の中には「ほとんど作業はできないだろう」と感じるほど介護度が高い人もいた。しかし、そんな予想を裏切るかのように、しっかりと仕事をやってのける人が続出したそうだ。やりたいと願って取り組むことは、その人が持てる以上の力を発揮させてくれるものなのかもしれない。
もちろん、すべての作業がスムーズにいくわけではなく、できないことは仕組みでカバーしている。たとえば、保育園の補助業務では最初、子供たちの見守り業務を任せていたが、子供の目線に合わせてかがむ動作や、とっさの動きが難しいことが分かり、業務内容を転換した。任せる仕事内容を、見守り業務ではなく保育士さんの周辺業務に変えたのだ。
「実際にやり始めてみて一番嬉しかった変化は、入居者さん同士のコミュニケーションが増えたことですね。普段、施設が提供するアクティビティでは、あまり交流が発生しないのですが、仕事では『次はこうしたらどう?』などの積極的なやりとりが生まれたんです」
ほかにも、「今、何の仕事があるか、フロントに貼り出してみたらどう?」「次はあの野菜を作ってみようよ」など、仕事に参加した入居者が、提案をする機会が増えたそう。そのような変化を通して、あらためて気づいたことがある、と荒川さんは言う。
「本当はみんな、誰かに必要とされたがっているんですよね。 仕事は、“自分が必要とされる居場所づくり” そのもの。だから、そうした居場所を増やしていくために、入居者さんのさまざまな特技や技能を活かせる仕事の種類を、もっと増やしたいと思っています」
実現の壁は、今ある「社会の制度」
「仕事付き高齢者住宅」の取り組みが、今後もっと拡充してくれたら、「無理なく働き続けられる老後」が現実となる。そこには報酬面だけでなく、「自分も誰かに必要とされている」と実感できる精神面のメリットもあるはずだ。
ただ、この取り組みが普及するためには、まだまだクリアしなければならない課題が山積みだという。
「ひとつは、『誰が雇用主になるのか』ということです。今は稼いでいる額も少ないので、有償ボランティアという形でお支払いしていますが、本格的にやるとなると、誰かが雇用しなければなりません。送り迎えは誰がするのか、雇用保険は誰がかけるのか。それを私たちがするのは違うと思っています。また、介護保険をもらっている高齢者が再び働く場合、現状の制度では保険金が受け取れなくなってしまいます。願わくは、老後に少しだけ働けるような社会の仕組みができればいいと思っています」
やろうとしていることは、国の社会保障制度からはみ出ること。実現への道は一朝一夕にはいかないようだ。
しかし、希望はある。「仕事付き高齢者住宅」は、経済産業省が推し進める事業。伸こう福祉会での取り組みがうまくいけば、今後、国の仕組みが変わっていく可能性がある。また、先駆者がいれば、そのあとに続く人が現れるものだ。社会が必要とすれば、国は変わる。
「仕事は、自分が必要とされる居場所づくり」

本当にその通りだ。私だっていやだいやだと言いながら、つい、いつも夜遅くまで仕事をしてしまうのは、その仕事の先にいる“誰か”に、喜んでほしくて仕方がないからだ。そんな楽しみが年をとったらなくなってしまうのは、とても悲しい。
施設に入ってから、祖母は、私の帰り際に必ず「これ持って行きな!」と、くしゃくしゃのビニール袋に入ったお菓子を渡すようになった。私は毎回「ありがとう」とお礼を言い、祖母の気持ちをカバンに詰め込んで帰る。
伸こう福祉会が取り組む「仕事付き高齢者住宅」は、高齢者でも、制度や仕組みを整えれば働けることを証明してくれた。もしかしたら数十年後には、「誰かを喜ばせたい」という人の根元的な欲求が、施設に入ってからも叶えられる未来がくるかもしれない。
あわせて読みたい