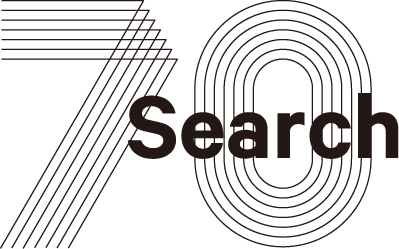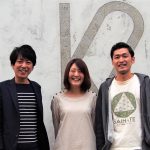前後編で紹介する「CAMPFIRE×LOCAL」の取り組み。
国内有数の大手クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」が地域特化型の活動を行う理由、そして個性あふれるメンバーが「CAMPFIRE×LOCAL」チームに加わった熱い想いが語られた前編記事。
後編では、クスッと笑える地域でのディープな体験談、そして、リアルに”お金”と関わるクラウドファンディングを推進する彼らだからこそ話せる、地域の人とのコミュニケーションの取り方について教えていただきました。
ホテルは取らない!?濃すぎるローカル体験
―様々な地域で活動を広げているわけですが、なかでも印象深かったエピソードや出会いはありますか?
渡辺:「CAMPFIRE×LOCAL」を立ち上げて、一番最初にパートナーになりたいと言っていただいて行った初めての出張が、ヒッピーが暮らすと言われている熊本のサイハテ村というパーマカルチャーを体現している村で。そこで一泊させていただきました。
―へぇ…日本にヒッピーが集う村が。
渡辺:とはいえ、住人たちは大工、家具職人、歌手、などみんな幅広いスキルを持ったクリエイターたち。
東日本大震災を機に「電気ガス水道・政治経済が止まっても笑っていられる村」をコンセプトに立ち上がり、住人の個性豊かな才能・知恵が村づくりに活かされてる場所です。

- (写真提供/三角エコビレッジ サイハテ)
サイハテ村は地方創生のまったく新しいモデルだと思っています。言ってみれば「お金」ではなく、魅力的なコンセプトで「人」を集めて作られた村なんです。
廃村を使ってルールもリーダーもいない「お好きにどうぞ」で村づくりをしよう!って。そしてそこの住人が村づくりに必要な企画をクラウドファンディングして具現化しているんです。みんなが村づくりに参加できるように「最高のゲストハウスを作る!」とか。
ー面白い取り組みですね。はじめは、ヒッピーや”サイハテ”と聞いて、もっとサバイバルな世界を想像していました(笑)。
実際に現地に訪れて、人や生活に触れてみないとわからないことも多そうです。
荒井:呼んでくださった方はホテルを取ってくれていることも多いんですが、僕たちが地方へ行くときは誰かに紹介してもらって地元の人の家に泊まらせていただくこともあります。僕は高知県の五右衛門風呂がよかったかな。
ー五右衛門風呂いいですね~。
荒井:地域おこし協力隊の方に紹介していただいた家が、ガス・水道が通っていない古民家で。火は全部薪を使って水は川から引いてきて。
トイレだってバケツでしたよ。仕切りがあって、大小でそれぞれバケツが置いてありました。おがくずみたいなものをかけておくと分解されて肥料になるって言われましたが、僕はちょっと恐れ多かったので小だけしました。

渡辺:ここでトイレの報告する!?(笑)
荒井:でも、そういうのも含めて、満天の星空に五右衛門風呂とかって宿泊予約サイトで検索してもなかなか出てこないような経験じゃないですか。
菅本:もちろん、地方創生に関わっている方が語られるようないい話もたくさんあるんですけど、驚かれるような変わった体験も多いですよね。
震災とクラウドファンディングの関係性
―CAMPFIREさんらしいような気もします。菅本さんは何かありますか?
菅本:つい先日、津波で流されたけど奇跡的に助かった人が女将を務める『宝来館』という釜石の旅館に訪れました。
その女将さんはいろんな夢を持っていて、実際に震災後も地域の復興のための活動をされてきたらしいんです。
でも、国から出る助成金というのは、基本的に命に関わるような問題や住居などに優先されていくので、観光誘致のような取り組みにはなかなかお金が出てこない現状があったらしくて。
―そのへんは難しいですよね…。
菅本:それを理解しながらも、だからこそ自分たちの身銭を切ってこれまでやってきたそうなんですが、限界があると。
そんなときにクラウドファンディングのような仕組みがあれば、全国に発信できるし、全国にいる応援したいと思ってくださる方々からお金を集めて、この町に実際に遊びに来てもらうきっかけづくりもできるね、と言ってくださったんです。そのように感じ、活動していただけていると知り素敵だなと改めて感じました。
荒井:名物女将らしいので、釜石行く機会があったら是非。
―はい、直接お話も聞いてみたいです!そう思うと、震災支援の形としても本当に有効な手段ですね。
菅本:プロジェクトの実行者がどれだけ本気でやりたいと思えるかによっては有効的だと思います。熊本では、震災後にたくさんプロジェクトが立ち上がったんです。
その様子を入社前から見ていましたが、企画内容だけに頼ってしまうと、震災関連でもエリアに関係なく支援は集まらない。
なぜやるのか…実行者が想いを持って、コミュニティを巻き込んで努力しないとお金も人も集まらないんです。
荒井:そうそう。ただ震災関連や、地域にとってこんなにいいことが起きますよ、みたいなプロジェクトでも支援が集まらないことも多いです。
菅本:これは私たちの課題でもあるんですが、クラウドファンディングはプロジェクトを立ち上げたら自然とお金が集まる仕組みではないですっていうのをしっかり伝えないといけないなと思います。
支援を集めるためには、実行者の想いと行動が絶対に必要です。

地方創生ではなく、「地方生成」へ
―そのコミュニケーションの取り方って、”よそもの”として難しいことだと思うんですが、気を付けていることや大切にしていることはありますか?
荒井:クラウドファンディングを東京の僕らががんがん押し進めるよりは、「こんなツールがあるんですが、どういう使い方だったら地域が盛り上がりますかね」みたいに、どちらかと言えば問いを返していただいて。
その地域で、どういう形が一番いいのかを一緒になって模索していますね。
菅本:何かを教えてあげるとか盛り上げてあげるという感覚は全くないですね。
むしろその逆で、地域の人たちから学びながら、その地元でしかできない体験を色々させてもらって、「これめちゃくちゃいいじゃないですか」って純粋に気持ちで伝えます。
敢えてそこにコンプレックスを感じ過ぎなくてもいいかなと。ここに住んでいないからこそ分からないことがあって当たり前で、知らないからこそ地元の人が気付かないような魅力を感じることができると思っています。
荒井:地方創生っていうと、新しいものをつくってまた生んでいくという文脈が強いんですけれど、地域をつくってきたそれまでの魅力は先代の力があってこそのことだと思うんです。
なので、その地域の良さを壊すんじゃなくて、クラウドファンディングを通じて新しいコミュニティや新しい価値の発信に使ってもらいたいなと。
地域で生まれてきたものからまた生まれてくる、”地方生成”のほうが大事なんじゃないのかなって思いました。
―”地方生成”ってグッときます。今後の展望や挑戦したいことはありますか?
菅本:私は、クラウドファンディングを通じて、人と人とをつなげたいと思っています。
地域の内と外の人との結びつきだけではなく、地域の内側にいる人同士のつながりも大事にしていきたいです。
地域の人同士が結びつくと、強い絆ができてその地域に誇りを持つことにもつながるし、地域に誇りを持てれば発信したくなる。それが、結果的に地域のファンになり得る外の人に伝わる重要なきっかけになると思うんです。
渡辺:僕は、その地域で活動する人の実現したいことが実現できること、その積み重ねがその地域の特色になると思っているので、その人たちがやりたいことを実現できる環境を整えることをやっていきたいなと。
僕はそもそも、クラウドファンディング自体あくまでもひとつの歯車でしかないと思っています。
行政、金融機関、地元の事業者を含めたコンソーシアムみたいな仕組みをつくって、そこにクラウドファンディングの歯車を入れたら回っていくような、インフラをつくれたらいいなと思っています。
―エコシステムのような?
渡辺:そうですね。例えば今やっているように、パートナーと1対1で組んで、そのパートナーが地域でクラウドファンディング事業のコンサルして、事業者さんが営業活動をして…というのだと、ぽつん、ぽつんとプロジェクトはできてもストックにならないと思うんです。
事業者さんの体力がなくなってきたらそこで終了。そうやって終わってしまうものではなく、ちゃんと継続性をプラスにしていくようなモデルをつくりたい。

―私もクラウドファンディング全体の課題なのかなって感じたのは、プロジェクト終了後、消息不明みたいになってしまうことなんですが、対策は考えてたりするんですか?
荒井:クラウドファンディング全体が手数料で収益を得るビジネスモデルになっているケースが多いですが、そうじゃなくて、お金を集めたあとにどういった形でフォローができるかが出口だと思うんですよね。
そこを厚くしていくことは会社としても考えていて、『CLOSS』っていうファッションに特化したサービスでは、2年間のビジネスサポートがあります。
―なるほど。
荒井:「CAMPFIRE×LOCAL」としては、まだまだクラウドファンディングを浸透させていくフェーズですし、全国のパートナーシップ獲得にむけて今はまだ走り続ける必要があるんですけど、それが達成できたら、今よりもっといろんな地域からいろんな声が上がってくると思うんですよね。
今すでにすごく感じているのが、1つの地域が頑張ろうとしてもなかなか思うように届かないこと。
なので、地域同士が僕らを通じて横に連携し、成功体験を共有し合ったり、企画を一緒にやってみたり、CAMPFIREトラベルみたいに他の地域も回れる仕組みをつくってみたり…
1つの地域だけで頑張るわけではなく、地域同士がつながっていく、そこでまた新しいものが生まれるようなことをやってみたいですね。
―点を面にしていくんですね。今後も楽しみにしています!ありがとうございました。
取材:鈴木賀子 編集:藤田郁
【取材コメント】
東京の新しいビジネスモデルを地域に展開するのは、そう簡単ではありません。ましてや、直接的にお金と関わるクラウドファンディングであればなおさらのこと。CAMPFIREが地域の人たちから受け入れられたのは、チームメンバーが心から地域での滞在を楽しみ、その課題に向き合ってるからなんだと感じました!
そんなCAMPFIREにて、70seedsのキュレーションチャンネル「CAMPFIRE×70seeds」が開設されました!”ハートに火をつける”ウェブメディアとして、取材などで関わってきたキーマンの新たな動きを応援するべく、70seedsがサポーターとして企画・運営を担当します。プロジェクト第一弾の舞台は、隠れキリシタンの島「生月島」!是非応援よろしくお願いします!
あわせて読みたい