関東や関西の若手研究者から成る『「満洲の記憶」研究会』という研究会があります。
自発的に立ち上がったこの研究会で、若手研究者たちは何を思ってこの活動に取り組み、「満洲」や「記憶」とは、彼/彼女たちの目にどのように映っているのでしょうか。
戦後70年を迎える2015年、菅野さん、佐藤さん、湯川さん3名へのインタビューを通じて、「満洲の記憶」研究会の成り立ちから将来像まで、また各々の問題意識を伺いました。
(上部写真 左から、菅野さん、湯川さん、佐藤さん)
―
菅野智博:一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程、日本学術振興会特別研究員。
湯川真樹江:学習院大学国際研究教育機構PD共同研究員。
佐藤量:立命館大学立命館グローバル・イノベーション研究機構専門研究員、博士(学術)。
―
偶然の出会いが「満洲の記憶」研究会のきっかけに

‐「満洲」というのは現在のどの辺りを指しているのでしょうか?
菅野:一般的には現在の「中国東北地方」を指しています。
‐「満洲の記憶」研究会はどのようにして設立されたのですか?
菅野:私が所属している一橋大学の佐藤仁史ゼミの一環で、2011年から2012年にかけて、中国残留邦人の西田瑠美子さんへインタビューを行ったことがきっかけでした。
私自身は、満洲と呼ばれていた地域の長春市で生まれ、自身のルーツを探す意味もあり、主に19世紀末から1950-60年代に至るまでの中国東北地方の農村社会を研究テーマとしています。大学院に進学した際、佐藤ゼミのあるゼミ生が中国残留邦人を研究テーマとしており、彼が(一橋大学のある)国立市にある「中国帰国者の会」でボランティア活動を通して、先述した西田さんと知り合いだったことが始まりです。
西田さんや他の中国残留邦人の方々は「満洲国」期のみならず、戦後直後や1950-60年代の農村社会を体験されたため、彼/彼女たちの話からは歴史史料から読み取れない貴重な情報が多く含まれており、私にとって大変良い勉強になりました。
その後も佐藤先生のもとで文献史学やオーラルヒストリーの手法で研究を続けていましたが、研究「会」にしなくちゃいけない、と強く感じたのは2013年になってからです。多くの引揚者との出会いを通して「自分一人じゃ無理だ」と思ったのです。
引揚者の多さとその高齢化に背を押され
‐1人では無理だと感じられた理由は何でしょうか?
菅野:2013年4月に満鉄会へ資料調査に行った際、偶々日本長春会の磯部荀子会長とお会いして、「長春生まれなら来てみないか?」と長春会総会への参加を誘われました。総会というもの自体が初めてでしたが、何より驚いたのが、引揚者とその関連資料の多さでした。
その時に、引揚者が多くの資料を所持していること、またそれが関東地域のみならず日本各地に分布していることを実感しました。さらに、若い院生が満洲に興味を持っていることに対して、満洲体験者の方々がすごく喜んでくださり、いろんな貴重な体験を教えてくれたと同時に応援してくださったことも嬉しかったです。何よりも、これらの満洲体験者の高齢化に伴い、貴重な資料や「記憶」が失いつつある状況にあったので、1人で資料収集やインタビューを続けていくのは無理だと感じ、以前から知り合いだった湯川さんに声をかけ、さらに佐藤先生に相談しました。
‐転機となったのが長春会だったのですね。
菅野:そうですね。西田さんのインタビューを通じて、日本で行うインタビューの意義を感じていましたが、こんなに多くの引揚者と出会って、さらに彼らが高齢だということを実感することで、「早く口述調査をしなきゃいけない」と差し迫ったものとして認識しました。
‐そこからはスムーズに研究会として成立出来たんでしょうか?
菅野:佐藤先生が、同世代の院生だけで集まって勉強会などをやるのは大事だとずっとおっしゃっていましたので、すぐに賛同して下さり、アドバイザーとして入ってくれました。
多くの同じような問題意識や関心を持った大学院生と出会えたことも、スムーズに成立したポイントでした。本当に心強かったですね。
湯川:佐藤先生からは多くのアドバイスをいただいており、例えば2015年3月にニューズレター『満洲の記憶』を創刊した際にも、ISSNを申請し、一橋大学機関リポジトリに登録できるように手配して下さいました。そうすることによって、国会図書館等でも検索でき、多くの研究者や一般の方々に読んでいただくことが可能になりました。さらに、私たち研究者としての業績にもなるので、嬉しかったです。

戦後も国籍を超えてつながり合う、多様な「満洲」
‐湯川さんは、菅野さんと一緒に佐藤先生の下で調査をするなど活動をともにしていましたが、研究会の話をもちかけられたときどのような理由で参加を決めたのでしょうか。
湯川:私は満洲の農事試験場での水稲品種開発について研究をしているのですが、満洲をフィールドとしていると、日本史の中に描かれる満洲に中国人が殆ど出てこない一方で、中国では、侵略者としての日本人と被抑圧民族といった構図で歴史が語られるなど、歴史観の違いを常に感じていました。また、専門的にインタビューの手法を学んで、史料に記載された情報の背景を知りたいと思っていたことも理由のひとつです。
‐関西にいらっしゃる佐藤さんはどのような問題意識をもって入られたのでしょうか。
佐藤:僕は、これまで大連や日本でインタビュー調査をやってきたんですが、やっぱり1人だと限界がある。どんどんとインタビュー対象者は高齢になって亡くなっていく。誰かとやりたいとずっと思っていました。
‐菅野さんと同様の問題意識を持っていたわけですね。佐藤さんはどのような研究をしていらっしゃるのですか?
佐藤:満洲の学校についてです。小中高、大学、女学校とか。内容は、同窓会のことを。
‐対象は日本人の学校ですか?
佐藤:はい。ただ満洲の日本人の学校には、日本人以外の人たちも通っていました。例えば、富裕層や知識層の中国人やロシア人なども通学していて、そのため同窓会も結構トランスナショナルなんですよ。その後、戦争が終わって、満洲が無くなって、日本と中国で国交がない時代でも繋がり合っていた、そのような民間交流について研究しています。
中国からみた満洲と、日本からみた満洲というのが同窓会というところでぶつかり合う。同窓生同士はすごく仲が良いけれど、それぞれ国を背負っている。そのゆらぎ、戦後の生き様、どうやって歴史を消化しているのかをインタビューしています。そのため僕は、日本からの視点だけではなく、複数の視点から満洲を研究したいと考えています。
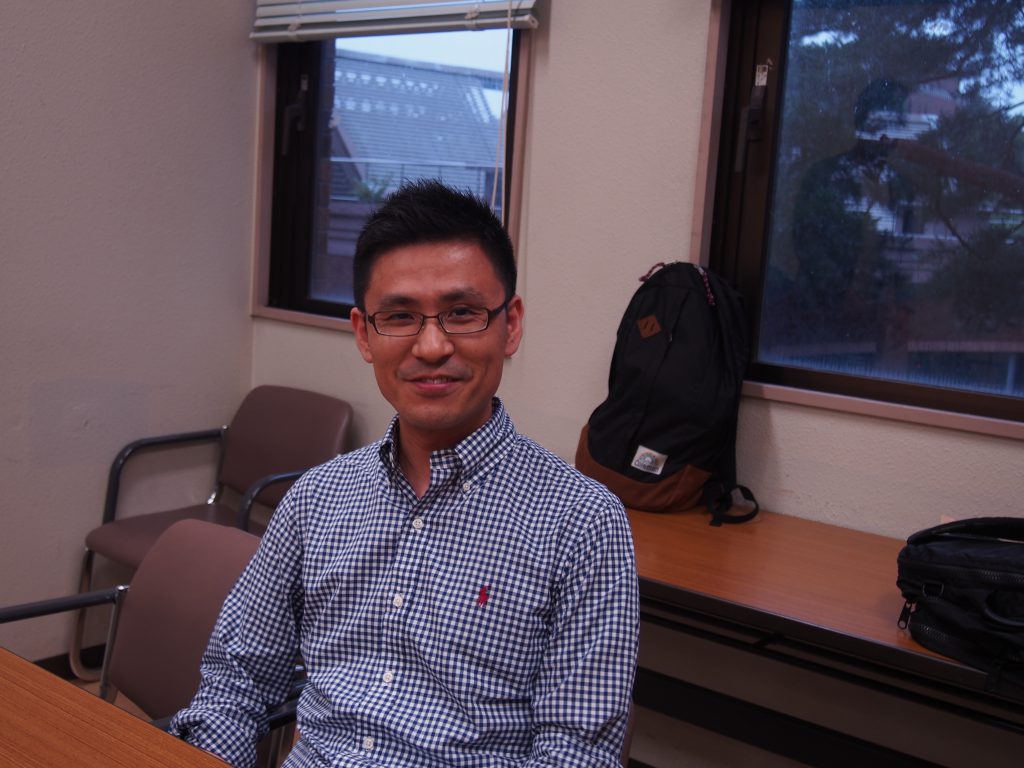
「記憶」の意味するもの
‐あえて記憶に「」をつけているのには、どのような理由があるのでしょうか。
湯川:私個人の考えですが、おじいさんやおばあさんに当時の話を話してもらうとき、それは彼/彼女の記憶なんです。実際にあった満洲の歴史というよりは、彼ら/彼女らが見た、消化した、思い出したものを話してくださっているので、私たちが扱うのは、個々の記憶なんだということ、そこにちゃんと注意をしたいということで「」を付けたのだと思っています。でも、それぞれの記憶がただのお話だとは思いません。各々の記憶の集合体が歴史を作っているんだと考えます。
佐藤:満洲には当時いろんな人たちが居たんです。日本人だけでなく、ロシア人や中国人。その人たちの立場、住んでいる場所も多様だったんです。だから「記憶」も多様なんです。
‐では「引揚者の記憶」ではなく、なぜ「満洲の記憶」研究会としたのでしょうか?
菅野:そうですね。「満洲の記憶」といっても本当に多様な記憶が含まれており、引揚者もいれば、中国残留邦人もいます。さらに、戦後台湾や朝鮮に渡った方々も多くいます。本来ならば、これらの多くの方々にインタビューをしていきたいですが、やはりまだ十分にできておらず、どうしても今は日本に多くいる引揚者や中国残留邦人に集中しています。また、現段階満洲に焦点を当てているのは、満洲に渡った日本人が「数」として一番多いからです。だからこそ、日本で出来るような資料収集やインタビューを満洲体験者の方々がまだ元気なうちにしっかりやっていきたいという思いもあります。将来的にもっと広げていきたいですね。
多様な姿を見せる「満洲」、それは戦後生まれの私には想像もできなかった姿でした。
しかし、多様な「満洲」からは多様な「記憶」も生まれています。
若き研究者たちは、そんな一人ひとり違う「記憶」をどのように受け止めているのか。
そして、「記憶」をどう見つめて行くのか。
次回では3人が向き合う「記憶」についてより深く掘り下げていきます。
あわせて読みたい









