鉄道大国と言われる現代の日本では、多種多様な形の鉄道が走っています。
リニアモーターカーや新幹線といった次世代の鉄道が次々と運行されていく中、戦時中に誕生した蒸気機関車に出会える場所があることを知っていましたか?
今回お話を伺ったのは、「D51-498」(デゴイチ)と「C61-20」という2台を所有するJR東日本高崎支社で、長年「デゴイチ」の運転に携わってきた後閑さんと検修に携わっていた時澤さんのお二人。
SLに長年関わってきたお二人から「デゴイチ」に関するエピソードを聞いてきました。

運輸部企画課 後閑治人
昭和54年4月1日 日本国有鉄道 入社
昭和62年4月1日 東日本旅客鉄道株式会社 入社
電車運転士、SL運転士として活躍した後、研修センターにてSL関係の講師を経て、現在は運輸部企画課勤務。
高崎車両センター高崎支所 時澤文夫
昭和53年1月1日 日本国有鉄道 入社
昭和62年4月1日 東日本旅客鉄道株式会社 入社
入社当初より、車両技術係としてSLに関わり、現在は高崎車両センター高崎支所で技術継承の一躍を担っている。
戦時中の軍事輸送の要だった「デゴイチ」
![[07D101] 120707~0012dp1s](https://www.70seeds.jp/wp-content/uploads/2015/08/07D101-1207070012dp1s-1024x683.jpg)
(写真:D51-498と12系客車 ©JR東日本 高崎支社)
-まずD51-498の誕生について教えて下さい。
後:私たちが運行している「D51-498」は1100台近くが生産された、「デゴイチ」シリーズの一つです。
「498」の誕生は戦前の1940年ですが、「デゴイチ」は太平洋戦争中に大量生産されています。
-それだけ多くの台数が生産された背景には何があったのでしょうか?
後:「デゴイチ」は貨物輸送の蒸気機関車用として設計・生産されました。
そして、太平洋戦争中には軍事物資の輸送需要が非常に高まり、それに合わせて「デゴイチ」が大量に作られたという背景がありました。
-鉄道に詳しくない人々の間でも「デゴイチ」という名前は親しまれていますね。
後:1100台近く作られた蒸気機関車は他にはありませんからね。
「デゴイチ」の生産自体は、戦争が終結すると同時に終わってしまうのですが、戦後も全国各地で活躍していました。
なので、とても多くの人の目に映った「デゴイチ」の走っていた姿が今でも語り継がれているんじゃないかと。
-戦後も蒸気機関車はしばらくの間生産されています。
時:戦後に誕生した蒸気機関車は、主に人を運ぶための「旅客用」として再設計されています。
例えば、私たちが運行している「C61 20」は1949年に作られた機関車なんですが、ボイラーは「デゴイチ」の物を再利用しています。
そして、車輪などの造りを見直すことによって、新たに人を運ぶための設計になっています。
-というと、貨物輸送のための機関車と旅客輸送のための機関車では車輪の形が違うということでしょうか?
時:D51とC61の車輪を見比べてもらうとわかるんですが、D51は車輪が小さく、C61は車輪が大きいです。
車輪が小さいと速度は出ないものの、荷物を引っ張ることのできる力は大きくなります。逆に車輪が大きいと、速度も出せますし、乗り心地もよくなります。

後:わかりやすく言うと、D51とC61の関係はトラックとバスなんですよ。
トラックはいっぺんに多くの荷物を運ばないといけないし、バスは多くの人を快適に運ばないといけない。蒸気機関車も同じ考えで作られています。
-なるほど!あまり詳しくない人からでも、デゴイチというと力強い機関車というイメージがありますが。
後:私が運転士をしていた時にも「デゴイチはきつい坂を登っていても、絶対に止まることはないから安心しろ」と先輩から言われたことがあります。
また、誕生してから全国で貨物を引っ張る機関車として活躍していました。
だから運転に関わる立場からも、普通の人々にも「力強い」というイメージが残っているのではないでしょうか。
復活の狼煙が上がった「D51-498」

(写真:復活した「D51-498」 ©時澤文夫さん)
-戦後しばらくして「デゴイチ」は一回現役を退きます。
時:1977年に「D51-498」は一旦登録を抹消されてしまいます。この頃になると、全国で新幹線が次々と開通していきますから、ひと昔前の技術である蒸気機関車は、残念ながら徐々に全国から姿を消し始めます。
-現役を退いたD51-498はなぜ復活することになったのでしょうか。
時:「D51-498」は現役を退き、車籍こそ抹消されたものの、みなかみ町にある上越線・後閑駅にて大切に保存されていました。
その後、埼玉県にある秩父鉄道にて別のSLが運行され始めるのですが、その姿を見た当時のお客さまから「地元でもSLが走る姿が見たい!」という強い要望があり、「D51-498」が復活することになったんです。
-なぜ「デゴイチ」は高崎で運行できるようになったのですか?
時:SLが全国から姿を消した後も、高崎にはSLの運転や整備に関わった経験者が、偶然にも残っていました。
また、群馬の方々はSLが復活することに対してとても寛大だったことから、地元の住民からの理解も得やすかった。
SLを走らせるには、とてもいい環境だったんです。
後:高崎には戦後も蒸気機関車が多く残っていましたし、「498」が現役を退く前の最後の運転も、高崎と八王子を結ぶ八高線という路線で行っています。
以前から群馬の人たちは、SLに対して非常に親しみを感じてくれていたんだと思います。
その想いが「498」の復活という形に繋がったと思っています。
蘇った「デゴイチ」と「SLみなかみ号」
(写真:D51-498とC61-20 S ©JR東日本 高崎支社)
-1988年に「D51-498」はいよいよ復活します。
時:上越線後閑駅に保存されていた 「D51-498」は、工場の設備が整っている「JR大宮工場」(現:大宮総合車両センター)に運ばれ、半年近い時間をかけて営業運転に向けた修理を行いました。
-最初の営業運転の営業運転について教えて下さい。
後:復活してからの最初の営業運転は、「オリエント急行」の牽引で上野〜大宮間を走行したのが最初になります。
世間を賑わせていた「オリエント急行」を復活した「デゴイチ」が牽引するということで、これ以上とない絶好の機会でした。
-復活した当初はどんな様子だったのですか?
後:オリエント急行としての運転の後「498」は主に「SL奥利根号(現在はSLみなかみ号)」として、上越線の高崎〜水上間を運行が中心になります。
復活した当初は、座席が毎回満席になる満席御礼の状態が続くほどの人気でした。
-現在もハイシーズンになると、SLに乗るための切符が取れない事も少なくないと聞きます。沿線住民の方々からはどのような反応がありますか?
後:上越線や信越線(高崎〜横川)の沿線の方は非常に好意的に考えて頂けているようで、ありがたいことにボランティアでSLに協力してくださるような方々も沢山いらっしゃいます。
また、上越線SL運行の終点であるみなかみ町の方々も非常に好意的で、観光促進の企画への取り組みを一緒にやらせてもらっていたりしています。
-現在「D51-498」は主に「SLみなかみ号」として運行されていますが、その他の地域でも運行されているのでしょうか。
後:群馬県以外だと、「SLばんえつ物語」を運行している新潟などで運行される事があります。
それから、2011年に起きた東日本大震災への復興を支援するためのキャンペーンをきっかけに福島でも運行が始まりました。
その他、JR東日本管内で観光のキャンペーンを行う時には、各地へ貸し出したりする事があります。
-様々な場所で運行することも簡単なことではないと聞きます。
後: SLを走らせるにはどうしても煙と汽笛の音がありますから、沿線住民の理解を得ながら、様々な意見や環境の変化を踏まえ、SLをどう共存させていくのか、これは今後の我々の試練だと思っています。
今の若い人たちにSLが継承されている事実が大事
![[07D100] 120701~9680dp1s](https://www.70seeds.jp/wp-content/uploads/2015/08/07D100-1207019680dp1s1-1024x683.jpg)
(写真:並走するD51-498とC61-20 ©JR東日本 高崎支社)
-後閑さんがSLに関わるようになったきっかけを教えてください。
後:まず、私が国鉄に入社したのは、1979年になります。「D51-498」が一旦現役を退いた後の入社なんです。
生まれは1960年なんですが、物心ついた頃には既にSLはピークを終えて、あまり見る機会も多くありませんでした。
それでも、当時は両毛線(新前橋〜小山)でSL走っている姿を見ていて、憧れを持っていましたね。
-入社されてすぐにSLに関わるようになったのですか?
後:入社してからしばらくは、普通に電車の運転士をしていましたし、その時はまさか自分がSLの運転士になれるなんて全く思ってなかったんですよ。
でも、電車を運転していると後閑駅に眠っている「D51」が目に入り気になってはいました。
そして何より先輩運転士達のSLを動かすかっこいい姿に憧れを持っていて、SLの運転士になることを決めました。

(写真:現在は一線を退いているという後閑さん だが、運転台に登った時の姿は現役そのものだった。)
-時澤さんはどのように関わることになりましたか?
時:私は小さい頃から鉄道が好きだったんです。学校を出てから一旦他の会社へ入社したのですが、その後技術者として国鉄に入社することになりました。
-最初からSLに関わると決めて入社されたのでしょうか?
時:SLには憧れがあったものの、関わると決めて国鉄に入ったわけではありません。
しかし、入社してから周りにSLの整備に関わらないかと勧められ、関わることを決意しました。
SLの仕事に関われたことは、自分でも非常に運がよかったと思っています。
(写真:「時澤さんがいたから今のSLがある」高崎支社の人々は時澤さんをそのように語る。)
-SLに関わるようになって、何か自分の中で変わった点はありますか。
後:SLの運転士を始めて思ったのは、ただお客さまに目的地までご乗車いただくだけの乗り物ではないということです。
電車の運転士は、機械を制御してお客さまをより安全で快適に目的地までご乗車いただいておりますが、SLの場合、それに加えて運転するのに生き物を扱う気持ちで運転しなくてはなりません。
-SLが生き物、ということですか?
後:これは私に限らず、SLの運転士誰しもが思っています。SLを動かすための蒸気は、その日の天候などによって生まれる量が変わってしまいます。
例えば、夏と冬に同じ量の石炭を入れて燃焼させた時に発生する蒸気の量は、一緒ではないんですよ。
また、機関車自体の状態によっても様々な場所を操作しないと、いつも通りの運行ができなくなります。
だから、私はSLを生きているものとして取り扱っています。
そして、SLのお客さまは、ただ鉄道に乗って目的地に向かうだけでなく、SLへ乗ったり見たりする事を非常に楽しみにしているんです。
そういうお客さまにどうやったら楽しんでもらえるか、というのを実際にSLを動かしながら考えるようになりました。
-技術者の立場から何か変わった事はありましたか?
時:私のような技術者は、後閑さんのような運転に直接関わっている人々のように、人の目に触れる事はないんです。それが、SLに関わるようになってから運転に関わる人たち、それに社内の様々な人たちと関わるようになって、みんなでSLを動かしていくという楽しみに変わりました。これは非常に幸せな事だと思っています。
後:SLが運行している時にお客さまから常に注目されるのは運転士や車掌です。
SLは決して運転士や車掌だけでは運転できないものだと思っています。
例えば、運行のイベントを行った時にお客さまから花束を渡されたりするような役目はすべて運転士ですが、その裏には時澤さんのような技術者がいつも整備をしてくれているからこそなんです。
だから私は、いつも後輩の運転士に「お客さまから感謝されただけで舞い上がっちゃいけない。
時澤さん達の人たちのような裏方で頑張っている人たちがいることを忘れるな」と常々言い聞かせています。
-誕生から70年が経った機関車を走らせ続ける意味とは一体何なのでしょうか?
後:「デゴイチ」という戦時中に誕生した物が今もこうやって走り続けているのは、当時の歴史を後世に残してくためだと思っています。
鉄道で言えば、新幹線は次世代の技術が次々と投入され、日々進化をしていっています。
一方でSLという鉄道の原点が残り続けるのは、今後の鉄道の歴史にも非常に意味あることだと思っています。
SLが歩んできた様々な歴史が若い人たちに継承されていくのは非常に大事なことだと思っていますし、今後も技術の継承を続けていきたいと思っています。
時:SLという機関車を残すためには、語り継いでいくだけでなく、色々と体感してもらう事が大事だと思っています。

(写真:SLの補修パーツを作る様子)
例えば、SLの補修に使うためのパーツは、普段SLがいる高崎車両センター高崎支所で作っています。
パーツをなかなか他で作れないという理由もあるのですが、なによりSLの近くにいる技術者達に体感してもらうことで、SLが残されている意味を身をもって感じてもらう。
教科書やマニュアル通りではうまくいかないが、昔あった技術を継承していくためには、そういったことが大事なんじゃないかと思っています。
後:時澤さんのような人がSLの技術を継いだからこそ、今の形を残し続けていられるんだと思います。
そして、これからもSLが残せていけるよう、技術の継承だけでなく、人々がSLに触れる事ができる機会をもっと増やしていけるように、今後も運転を続けていきたいですね。

(写真:運転士だけではなく、縁の下の力持ちがいないとSLの運行は成り立たない。その言葉がとても印象的だった。)
あわせて読みたい
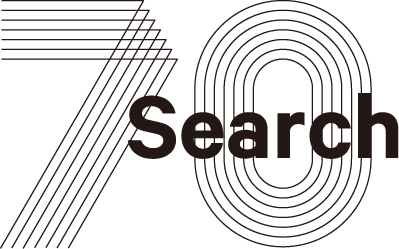



![[50D104] 110923~8310cs3](https://www.70seeds.jp/wp-content/uploads/2015/08/50D104-1109238310cs3-1024x682.jpg)






