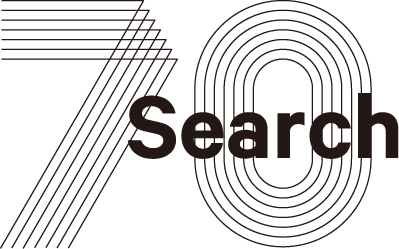みなさんは、介護や福祉の業界についてどのようなイメージを持っていますか?
なんだかあまり触れてはいけないようなテーマなような気もする、介護職の「3K」に人手不足、自分には関係の無い話だ…
果たして、本当にそうなんでしょうか?実はみんな知らないだけなんじゃ?
そんな疑問に答えるべく、登場したのはこちらのファンキーなお兄さん、NPO法人Ubdobe代表理事・岡勇樹さん。

医療福祉とエンターテイメントを融合させ、福祉に関心のない若者へ呼びかけるイベントや業界のブランディングを図るデザイン・プロデュース事業を担っています。
そこには、医療福祉とエンターテイメントが共存する知られざる世界がありました。きっとあなたの見方も変わるはず…
福祉職はクリエイティブディレクター
‐医療福祉業界に旋風を巻き起こすUbdobeですが、岡さんは業界や介護・ヘルパー職をどのように捉えて活動しているんでしょうか。
逆に質問してもいいですか?今日ってなんでオムライス頼んだんですか?
(※本記事はランチを食べながらの取材)
‐えーと…特に理由はないですが、最近食べてなかったし美味しそうだったから…。
なるほど。まぁ僕もそんな感じなんですけど、普通あまり考えないじゃないですか。あ、うまそー、今日はカレーじゃなくて久々にオムライスにしてみよう、くらいの感じで。
その選択をできる状態の人と、全くできない状態の人がいて。オムライス食べたいとずっと思ってるのに、毎日カレーしか出てこないのだと嫌じゃないですか。
‐はい。
例えばだけど、その人がどうやったらオムライスを食べれるようになるかを考えてその状態を作るのがヘルパーの仕事なんですよ。
本当は食べたいものがあるけど、噛む力が弱い、スプーンを持つ力がない、そもそも発語できないから食べたいものを伝えられない、というように自分がこうしたいって考えた先に立ちはだかるのが障害だと思ってます。
って考えた時に、まずはその人が今日はこれが食べたいって気持ちにさせる努力をしなきゃいけない。
毎日同じものを食べててそれが当たり前だと思ってる人には「本当にそれでいいの?あれもこれもあるよ」って他の選択肢を提示しないと。
それで食べたいってなったら、そこに向かってどうやって進んでいくかをプロデュースする。
その人のやりたいこと、人生や生活をトータルでディレクションする、もちろんご本人と一緒に。言わばクリエイティブディレクターのような仕事だと思っていますね。

‐そのような着眼点を持てたら、業界に対する認識も大きく変わりますね。そのために大事な資質ってなんでしょうか。
福祉の教科書にはよく”対話”って言葉が登場しますが、僕はエゴイズムこそ必要だと思ってます。福祉の世界ではあまり良しとされてないけど、僕はむしろそれしかできてません。
対話ってすごく相手のことを伺うじゃない?どうなのかな…?みたいな。それでは相手の世界を広げることにはならないんですよ。
‐それはどういうことでしょうか?
例えば、自閉症の子の移動支援で毎週動物園に行くプログラムがあったんですけど、僕は動物園好きじゃないし、その子はあまり返事とかができない子だったから、「今日は映画行こうぜ。いいよな?」って聞いたら頷いてくれたんで映画館に行ったんですよ。
親御さんに映画に行ったことを報告したら、その子が奇声上げたり騒ぐと思ってたらしく「この子、大丈夫でした?」って心配してた。でも全然大丈夫だったの。
「大丈夫でしたよ」って言うだけで今度から家族の可能性が広がるじゃない。エゴの押し付けを1回してみて本当に拒否されたらやらない方がいいけど、まずは連れてってみる…その連続ですよ。
だから、提案とかディレクションっていう意味ではすごく面白い仕事のはずなんだよね。
それに気付いてない人も多いし、そのケアを受けてる人も、ただお世話してもらう人って感じで気付いてない。本当はいろんなことを一緒に創っていける存在なのになぁ…。
「なんかこの業界おかしくね?」
‐先ほどのクリエイティブディレクターの話がよりしっくりきました。そもそも、岡さんが今の活動を始めたきっかけはなんだったんでしょう?
最初は、19歳のときに作った「ウブドベ共和国」っていう民族楽器とDJパーティをする音楽集団で活動してたんですけど、学生時代はクラブやバーに入り浸りで結構荒れた生活してたんですよ。
でも、母親が病気になってしまったので3年くらいで辞めちゃいましたね。病床の母の願いもあって、就職活動してリラクゼーション関係の会社に内定が決まったんですけど、その数カ月後に母は亡くなりました。
胃がんでした。その後、じいちゃんが認知症になってその会社も辞めましたけど。

‐まだお若い頃に大変な経験をしたんですね。そこからなぜ福祉に関心を?
じいちゃんの認知症が重度化して、入ってるとこも施設じゃなくて精神病院だったんだよね。精神病棟だったので、決していい環境ではない。
お見舞いに行くとなんとなく悲しい姿してて。僕のことを誰かも認識できないような状態でも、昔一緒に聴いてた曲を流すとじいちゃんがふと我に返るような、そんな反応が見られて。
これは何か役に立てることあるんじゃないかと思って、会社を辞めて音楽療法の学校に入りました。
そこから訪問介護とか障害者支援の仕事を始めるようになりました。
‐そのなかで、岡さんから見た業界の課題感が見えてきた。
例えば高齢者施設でも、すっげーつまんなそうだし、障害者施設も異常なまでに隔離された場所にあったりしたんで、「なんかこの業界おかしくね?」と思って。
一番のきっかけは、実習先として行った離島にある施設の子どもたちが完全なる隔離状態にあったことにすごく違和感を覚えました。
親も全然面会に来ない、ほぼ捨てられてるような子どもたちが3割くらいいたことを見て、聞いて、嫌だったのね。
誰もそんなこと知らないし興味も持たない。この子たちは、ただここの島に来て、一生その島から出れずに死んでいくんだなってことを考えた時に、超ファックじゃんと思って。
‐離島で隔離状態…そんな現場もあるんですね。知りませんでした。
そう。だからそういったことを少しでも多くの人に知ってもらうイベントをできたらいいなと思って。
学校の仲間たちを集めて、障害のある子どもと健常者の子どもたちの何が違って、何が同じなのか、というのを遊びを通して知れる何かをやろうと決めました。
そこで生まれたのが、国籍・年齢・障がいの有無・性別などの垣根を越えて、全ての子ども達が芸術活動を通してコラボレーションを実現する音楽とアートのイベント第一弾として2008年に開催した、「Kodomo Music and Art Festival」。そのときに手応えを感じて、2009年の次のフェスでは、規模を一気にデカくして、2000人ぐらいお客さんが来たの。
呼んだアーティストも、ラッパーのShing02や曽我部恵一さんとか有名なアーティストの人で。

「構えさせない」イベントづくり
‐現在もUbdobe全体で大きな一翼を担っているイベント事業ですが、リアルな場で扱うには少しヘビーなテーマですよね。
だからこそ、僕たちは医療福祉のカジュアル化を目指してやってきてるわけで。Ubdobeの創業メンバーも音楽療法の学校出身だからエンタメがベースにあって、その上乗せで福祉なんです。
恐らく、他の福祉従事者とは順番が違うんじゃないですかね。お客さんも含め、面白いことならみんな関心を示してくれるし、ついてきてくれると考えてます。
‐反応がこわかったりはしないんでしょうか。
医療福祉をテーマに、踊って学べる音楽イベント「SOCiAL FUNK!」で僕の友人で難病の娘さんを持つ女性に登壇してもらいました。
入口としてはクラブイベントで、バーーンって音楽が流れた後に、その子のドキュメンタリー映画、トークイベント、最後はみんな踊るみたいな流れ。
本当にキュッと間にテーマを詰め込めた感じなんですけど、トーク中も登壇者も含めてみんなお酒飲んでるし、場の雰囲気としてはフラットだけど、楽しむときは楽しんで、真面目に聞くときはちゃんと聞いて、聞いた後もまた楽しむ、みたいな。シンプルに構えてない。
‐そのままを受け入れてくれるような。
うん、今はこういう時間みたいな。さっきまで「うぇーい!」とか言ってた人が、話聞きながら「なるほど」ってなる。
その後娘さんを連れてみんなが踊ってる場所に行った時は、知る前と知った後の目線は違うんだけど、「どうしたらいいんだろう」じゃなくて「いぇーい」って絡んでくる感じ。
友達じゃないけど知ってる子みたいに接してくれるので、変な教育で入るよりはすごく親しみがあると言ってましたね。
‐それが狙い。
まさに。本当の一番の狙いは、お客さんが家に帰った時に何を話すかっていうところまで見ること。
僕の場合は、2年母親が癌ってことを隠してて、本当はどんどん痩せてったはずなんだけど、一緒に住んでるから全く気付いてあげられなかった。
イベント後に家帰って、親に対する目線をちょっと変えて一年前の写真見てみたら、あれ?なんかすげー痩せたんだな、みたいな人もいるかもしれない。
「最近体調どうなの?」って一言声掛けるだけで、言うか言わないかの選択肢が生まれるし、その結果その人の人生の長さも変わってくるかもしれない。質もね。
ほんのちょっとの会話のシフトチェンジのきっかけにしてほしい。僕はそれができなくて、母は2年間隠したまま亡くなっちゃったから。今は治療法もいっぱいあるし、オープンに話せたり聞けたりできればいいなと思ってます。
‐イベント以外でも、その間口を広げようと幅広い事業を展開していますね。
イベント以外には、デザイン、ショップ運営、メディア事業があるんですが、これから新しくメディアを立ち上げようと思ってます。

- Ubdobeが運営する、ユニバーサルデザイン商品と医療福祉情報のセレクトショップ「HALU」には、誰でもが楽しめるお洒落な商品がたくさん!こちらは買い物袋をコラージュした名刺入れ。
‐どんなメディアを?
医療福祉従事者に読まれない医療福祉Webマガジンっていうの作ろうとしてて。医療福祉ってシリアスだし、堅いじゃん。
実際、現場ではシリアスだし、特に人の命に関わる部分はそうなんだけど…でも、全部が全部そうである必要はなくて、深刻なだけが人生じゃないっていうか。
どんな難病や障害があっても、「楽しい、最高!」みたいな時間ってもちろん誰でもあるし。働いていても楽しい瞬間はたくさんある、そんな現場も見せていきたい。
あとは、自分がそうだったように、親が癌とか聞いてもなんの反応ができないなか、そもそも癌ってなんなのか、どういう症状があって、治療の選択肢はどれぐらいあるのか、とか。
普通に暮らしていて全然分からないような医療福祉の情報をカジュアル化、一般化していきたいと思います。
ハーフパンツでも無問題!「楽しい」は行政をも巻き込む
‐楽しみにしています!でも、それこそ医療福祉ってちょっとお堅いような行政機関なんかと深く関わりがあるかと思うんですが…
もちろんありますよ。公邸でイベントもやったことあるし。厚労省の大臣がいる会議で話したり。
‐失礼ですが、岡さんのそのファンキーなノリで?(笑)何がきっかけでそういう人たちにも話を聞いてもらえるんでしょうか。
一番最初、厚労省のすごく偉い人と知り合って飲んでたら、「これから20年、日本の福祉に必要なものはなんですか?」って聞かれて、パーリ―ですねって言ったもん(笑)。
「テキーラショットとDJとサウンドシステムさえあえば、バリアフリーでユニバーサルです、ヤーマン!」みたいなことを言ったら、「うん、何言ってるかさっぱり分からないけど楽しそうだし、一回私の会議があるから出てくれ」って誘われたんです。

‐その人の反応も面白い。会議はどうだったんですか?
僕、20~30分程遅刻して行ったんだけど、普通の会議室かと思ったら300人くらいバーッと踊る大走査線みたいに並んでて。
全国の都道府県行政の担当課のトップが全員集結した国家会議だったんですよ。
‐それは大変でしたね…。
え、今日パーティーの話でいいんすよね?みたいな。本当は持ち時間20分だったんだけど遅刻した挙句、1時間。でも、その切り口いいかもって反応もらえて、そこから行政とのコラボが始まった感じですね。
まさかこんな僕みたいなのを、Tシャツとハーフパンツで国家会議に呼んでくれるとは(笑)。議事録も残ってるんだけど、ひどいよ。ファックとか言ってんの残ってるからね。これは消せよ、みたいな(笑)。
‐一語一句真面目に議事録とってる(笑)。でもそのような状況のなかで、お役所の人たちがポジティブな反応を見せるのは意外です。
みんな本当は楽しくやりたいんですよ。楽しいことが人に伝わっていくとわかっているけど、その楽しいイベントやかっこいいデザインをどう作ったらいいかがわからない。
僕は人生ほとんど遊んできているので、そういう表現しかわからない。その凹凸がうまくはまったんですかね?
地域から日本の中心へ、そして全世界へ
‐なかで働く人も気になります。Ubdobeにはどんな人材が集まってるんですか?
自分大事精神を大切にできる人かな。自分が楽しいっていうのを一番ベースに大事にしているところ。ちょっとでもやらされてる感出てたら、もう怒る(笑)。
今日ボーっとしちゃって駄目なんですよね、とか言われたらもう飲みなよって言う。うち事務所ビールいっぱいあるし。それで仕事とかイメージが膨らむんだったら、その方がいいじゃん。少なくとも今は。
これが200人の会社になってきたらそれをできるか分からないけど…できる限り、そういう状態には保ちたいなとは思ってる。

‐業界のカジュアル化を目指すからには、ということですね。今後の展望はありますか?
最終的には、国連事務総長になりたいと思ってます。
‐おぉ…。
その前には、国際展開の話もあるけどそれは当たり前というか。僕たちは概念を広げていくのが仕事だから、海外であっても同じ。
それを今度深めていくために、今地域化も進めて全国に支部長を作ってます。みんな有志で担当しくれてるんだけど、そういう彼らが一番強い想いを持ってるんです。
現場で働いてる子たちとか、自分が何かしら障害とか難病を抱えてる当事者が一番の悩みと原動力を抱えてるから、それをどうスパイラルさせて、地域から出た課題や意見を中核となる政府に伝えていくかっていうことをやりたい。
一般化して広げるっていうことと、それを深めて末端にいる人たちの意見を吸い上げて、中央に伝えてくことを全世界でやんなきゃいけないと思ってます。だから僕は国連で働きたい。

【取材コメント】
自分の親の介護が必要になるまでは、縁遠いかな…と思っていた福祉の世界。でも、いつなんどき自分の大切な誰かに何が起こるか分かりません。「今はまだ関係ない」と思えている今だからこそ、知れることがある、できることがある、そう感じた取材でした。
あわせて読みたい