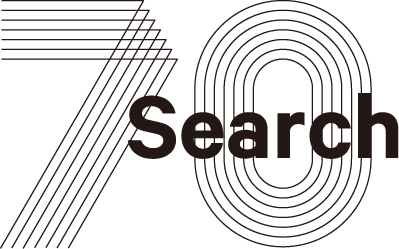年間数千億以上の国予算が組まれ、日本中で推進されている「地方創生」。あらゆる場所で推進されるプロジェクトの裏には、地方の可能性や地元への愛など、さまざまな想いを抱えて関わる人々がいます。
全国各地のプロジェクトに触れる中で、70seeds編集部が特に魅入られたのが「地域×デザイン2017」で出会った福井県福井市のプロジェクト「XSCHOOL」。あたらしい地方創生の可能性を感じさせる彼らの取り組みの「その後」を追って、東京で開催された中間発表から1ヶ月後、福井新聞社ホールで開催された最終成果発表会に行ってきました。(Photo by Kyoko Kataoka)
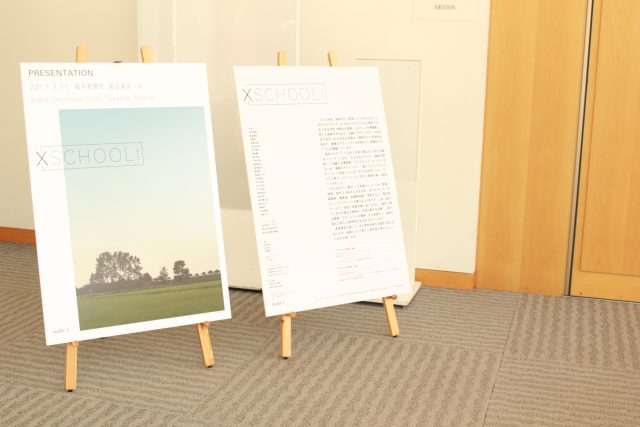
XSCHOOLの詳細は中間発表会のレポートを御覧ください。
今回の「その後」記事で取り上げるのは、発表会後に開催されたレビュアーのみなさんによるトークセッション。
メンバーは、ゲストの塩瀬隆之さん、ドミニク・チェンさん。そして受講生とともに120日間並走したデザイナーの原田祐馬さん、萩原俊矢さん、高橋孝治さん、XSCHOOLの企画をしたRE:PUBLICの共同代表である内田友紀さんです。
キーワードは「風の人、土の人」
トークセッションで全員が言及したのは、「風の人、土の人」という言葉。オギュスタン・ベルクの『風土の日本』や和辻哲郎による「風土論」になぞらえて、外から関わる人を「風」に、その土地に根づく人を「土」に例えて話題が進みました。
この「風の人、土の人」という考え方、元信州大学名誉教授であり、農学者だった玉井袈裟男氏(1925〜2009)が立ち上げた「風土舎」の設立宣言にその考え方がよく表れています。
風土という言葉があります
動くものと動かないもの
風と土
人にも風の性と土の性がある
風は遠くから理想を含んでやってくるもの
土はそこにあって生命を生み出し育むもの
君、風性の人ならば、土を求めて吹く風になれ
君、土性の人ならば風を呼びこむ土になれ
土は風の軽さを嗤い、風は土の重さを蔑む
愚かなことだ
愛し合う男と女のように、風は軽く涼やかに
土は重く暖かく
和して文化を生むものを
魂を耕せばカルチャー、土を耕せばアグリカルチャー
理想を求める風性の人、現実に根をはる土性の人、集まって文化を生もうとする
ここに「風土舎」の創立を宣言する”
(玉井袈裟男)
地方創生のシーンでは、風の人=よそもの、土の人=地元の人として、よく言い換えられます。今回のXSCHOOLでは、どういう風にとらえられていたのでしょうか。セッションのようすから紐解いてみたいと思います。

チェン:「地域おこしには地域のものを必ず使わないといけない」とか、「地域の人が常に参加しなければいけない」というように、条件がきびしくなっていくと、身動きがとりにくくなっていく。それを思うと、XSCHOOLは多様性が失われていなくて良いなと思いました。
面白いシーンでは「よそ者、若者、馬鹿者」がいると良いと言われていて。僕もチームビルディングでどうやってよそ者をいれるかっていうのは課題です。その場を知っている、好きでいる人だけであつまるとどうしても思考停止してしまうから、風穴を開けるというか、その部分を担う人物が必要になるんですよね。
参加者が日本全国から福井に来て、そして120日間通うことで、なんというか純粋なよそ者じゃなくなっていて。XSCHOOLのメンバーが新しい風の人と土の人の境界線上の立場になっていたのが印象的だなと感じましたね。
塩瀬:地域おこしには風と土が大事だと多くの人が言っていますよね。風は他所から来るが、土にはなれない。土は風を無視するのか、話を聞くのか。XSCHOOLでの風と土の関係を考えたときに、その関係が綺麗なプロジェクトだったと思います。

地域創生に関わるデザイナーの役割
内田:今回広義のデザインをテーマに取り組んだわけですが、広義のデザイナーと産業が、どのような役割を担い、どのような関係性になってゆくと良いか、塩瀬さんのご意見を伺いたいです。
塩瀬:伝統産業の事例として都市圏のプロダクトデザイナーが決め打ちのデザインを持ち込むとわりと失敗するんですよね。うまくいく人は聞き上手。話を聞ける人がいるプロジェクトは次につながっているなと思うんですよね。XSCHOOLは時間をかけて土地の人の話を充分聞いてスタートしているのが、すごくいい形だと思います。土地の人が気づけない良さを聞き出して見つけているから。その聞くための時間をしっかりとって、福井と伴走した120日。良い時間だったんだなと思います。
あと「最初の小さなアイデア」って都市圏で多くの人の目にさらされすぎると潰れてしまう。応援してくれる人だけに見せると大きくなると思うんですよね。だから今回のようなスモールスタートできるシステムっていうのも、地域創生にはすごく重要だと思います。

今回並走した講師陣の中で、特に企画段階から関わった原田さんもXSCHOOLを通じて感じた地域プロジェクトにおけるデザイナーのあり方を語ってくれました。
原田:僕のようにいろいろなところにお邪魔してご一緒するデザイナーとしての役割と、地に足をつけて取り組んでいるデザイナーって少し違うかなと思っています。今回の8つのプロジェクトの中で面白いなと思ったのは、ロゴを地元のデザイナーに依頼したチーム(あさひるばんじょう)がいたんですね。それが僕の中で新しくって。外から関わるデザイナーが自分たちでできるところを、そうではなくて地元のデザイナーといっしょにやった。デザイナーも風と土っていると思うんですよね。地元に生きるデザイナーとともに仕事がうまれるという流れがあって、今回は学びがありましたね。
120日間で培われた福井に対する当事者意識
内田:まれびとや風の人という立場で参加したXSCHOOLのメンバーがどのように変わっていったかも気になりますよね。それを講師の立場からご覧になった荻原さんはいかがですか。
荻原:僕もふだんは東京で活動していて、風の人なわけですけど。このプロジェクトを通して福井に知り合いができたり、ずっと福井のことを考えたり、まぁ福井のことを好きになっちゃったわけなんです。(笑)まさに他人事じゃなくなってしまって。ふだんインターネットに関する仕事をしているんですが、このプロジェクトに参加して「インターネットはすぐに世界につながるという良いところがあるけど、あんまり地域とはつながっていなかった」と気づきました。今後、もっとこういう機会が増えるといいなと思っています。
原田:メンバーと話していて「福井で感じたことをどのように外に展開していけるか」が大切だと思っていて。福井に縁ができる人がたくさん増えていければすごく良いです。
チェン:今回プロジェクトの最終発表をみて、全員当事者だったと思うんですよね。やっぱり120日間発酵させてきた発酵熱が感じられてすごく良かったです。当事者意識が自走している人は大丈夫だと思うんです。福井らしさが意識的から無意識になるまで、体に染み渡らせてプロジェクトを遂行していっていただければと思います。
次代の“事業の種”を生み出した受講生にとって、最終発表会はやっとスタートラインとのことでした。XSCHOOLが終わったあとも、アイデアの実現に向けて、福井にとっての「風の人」として、受講生達は走り続けるのでしょう。今後も70seedsではXSCHOOLを追いたいと思います。
各プロジェクトの最新情報はこちらで。
公式Facebookページ https://www.facebook.com/makefukui/
あわせて読みたい