犯罪が起きたと聞くたびに、きゅっと心臓が縮むような気分になる。
私自身が11歳のときに、誘拐未遂事件に巻き込まれたからだ。
あの日、マンションの階段で腕をつかまれたときのこと。
今でも覚えている。
私を脅した男はまだ若かったはずだ。
当時の事件は、「少年犯罪」「性犯罪」のひとつとしてカテゴライズされるのかもしれない。
階段で1階まで連れて行かれた。
恐怖が限界に達し、男の腕を振り払って私は逃げた。
あのとき、腕をつかまれたままなら。
今、私はここにいなかったかもしれない。
振り返るたびに心がきしむ。
事件から二十年以上経ち、「どうすればこの犯罪は起きずにすんだのか」まで考えを深めたいと思うようになった。
法律家でも警察でもない私は無力だ。
しかし私だけではなく、犯罪を防ぐためにできることを考える人が増えれば、十年後、二十年後に起きるかもしれない犯罪が少しでも減るのではないだろうか。
そのために、私自身が自分の身に起きたことを、もう一度振り返り伝えたい。
そして「犯罪」は遠い場所で起きるひとごとだと感じている人たちが、自分ごととして考えられるような方法を模索したい。
願いをこめて、全3回で犯罪についてのコラムを連載する。
原稿を書くためにパソコンに向かうと、当時の記憶が生々しく噴き出す。
第1回は、実際に犯罪に巻き込まれたときの私個人の経験を綴っていきたい。
場面緘黙症の子どもだった私
 当時、私は小学生だった。
当時、私は小学生だった。
小学生の頃の私や妹たちの姿を映した映像がある。家庭用のビデオカメラで撮影したものを、母がDVDにして残しているのだ。
よくしゃべる子どもだった。かんしゃくを起こすことも多かった。それにも関わらず学校に行くと話せない。私が言葉を発するのは授業中、先生の質問に答えるときだけだ。それが原因でずっといじめられていた。
大人になってから母が、小学生の頃の私は「場面緘黙症」という症状だったと教えてくれた。場面緘黙症の人は、言語能力は正常だ。ただ自宅では会話できるのに、学校などの特定の場面では話せなくなる。子どもがなることが多い。
同じマンションには同級生が5人いて、なかでも4階に住んでいる「ともちゃん」は、学校が終わった後、いつも一緒に遊ぶ親友だった。ただともちゃんはクラスが違うし、学校で何も話せない私を不思議に思っていた。だけど遊びに行くときはいつもやさしくしてくれた。
その日も授業が終わった後、ともちゃんと約束があった。もしかしたら、宿題が多かったのかもしれない。詳しく覚えていないが、とにかく私は早く家に帰ろうと急いでいた。
つかまれた腕と投げつけられた言葉
住んでいたマンションは広く、外からエレベーターまで行くのは子どもにとって遠かったので、私はよく外から入ってすぐの階段を使って、7階の自宅に帰っていた。
いつも通り家に帰ろうと階段を上がる。すると前に見たことがない男の人が歩いていた。
子どもの目から見ても若そうだ、10代後半くらいだろうか。ちらっと振り返る。鋭い視線だった。男が着てる服が、上下とも黒い無地なのが気になる。そんなファッションの大人を見たことがない。でも、早く帰りたい欲求のほうが強かった。
恐怖が生まれたのは、男が3階の踊り場で立ち止まり、振り返って素早く私の腕をつかんだときだった。
「泣くなや。泣いたら殴るぞ」
小さくて低い声といっしょに、つかまれた腕に痛みを感じた。
何が起こっているのかわからなかった。だが、その男の言っている「殴る」の意味がしだいに脳にいきわたった。信じられないくらい強い力で、この男は私を殴るかも。本気で殴られたら私は…
男は繰り返した。
「ええか、泣いたら殴るからな」
私の目にはいつからか涙がいっぱいたまっていた。正確に言うと既に泣いているのだが、男の言う「泣くな」は、声を出して泣くことを指しているようで、彼は私を殴らなかった。殴られないように、一生懸命、声を出さないようにした。
だがどうしても嗚咽してしまう。そのたびに男が私の腕をつかむ力が強くなった。
もし連れ去られていたら
男は私の腕を引っ張り、ゆっくりと階段をおりていった。誰にも会わない。
怖い。
怖い。
怖い。
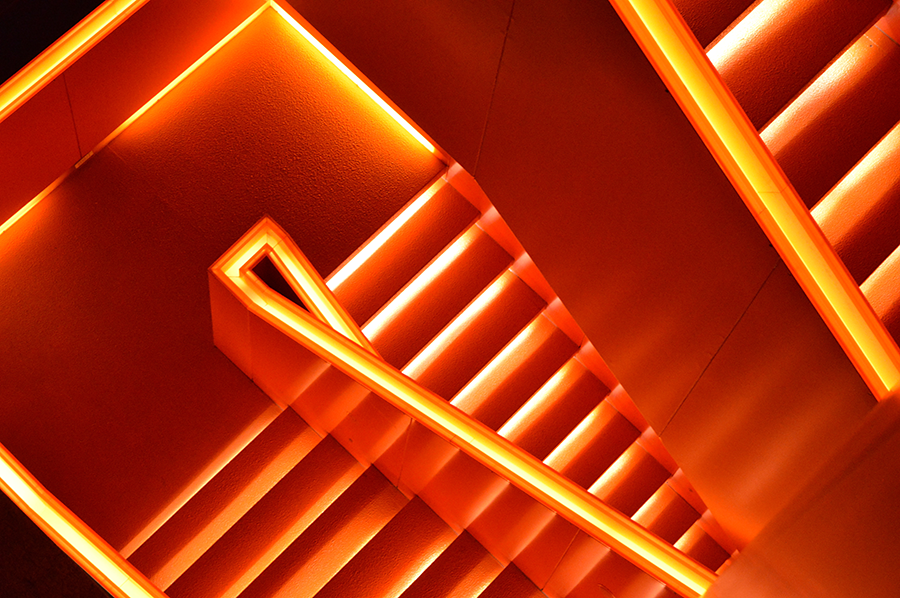 目の前の男の人が、すごく怖い。1階まで降りた。男は私を外に出そうとしている。外に出たら、どうなるのか。私の中で、何かがはち切れた。
目の前の男の人が、すごく怖い。1階まで降りた。男は私を外に出そうとしている。外に出たら、どうなるのか。私の中で、何かがはち切れた。
「ぎゃあああああああ」
泣き叫んで、男の手を振り払っていた。「そんなことをしたら本当に殴られるかも」と考える余裕もなかった。
エレベーターに向かい全速力で駆け出す。振り返れば、男が追ってきているかもしれない。前だけを見て走った。
エレベーターに着くと、私の家のちょうど1階下に住んでいるおばさんがいた。赤ちゃんのように泣き叫ぶ私を見て、「どうしたん?」と心配してくれる。
知っている大人がいた。もう大丈夫だ。説明できずに、わあわあ泣き続ける私を、おばさんは自宅まで連れて帰ってくれた。
時間が経ってから深まった心の傷
私の両親は共働きだ。だから、その日は自宅にお手伝いさんがいたと思う。母が帰ってきたのは夕方だっただろうか。そのあたりの記憶はあいまいである。
「1階下の方、子供たちのはしゃぎ声がうるさいってよく電話をかけてくるのに、ほんまはやさしい人なんやな。運が良かったなあ」
母がそう言った。とにかく母がおばさんの話をしたということは、きっと何があったか自分で説明できたのだろう。
泣き疲れた私は、自分の部屋で、好きな漫画を読み始めた。窓から降り注ぐ夕日で顔が暑かった。恐怖は嘘のように消えていた。
「夜に警察が事情を聞きに来るよ」
母がそれを知らせに来たとき、私がいつもどおりなので、驚いたと同時にほっとしたらしい。その後、母は小学校の担任の先生に連絡して、私に何があったか説明した。
正直、小学校は大嫌いだった。いじめられた経験を書いた手紙を担任の先生に渡したことがある。
「これクラスの皆に知ってほしい。学級会で読むで」
先生は私を呼び出してそう言った。
「いやです」
子どもなりに必死で反論するが、先生は首を振り、教壇に立ってクラスメイト全員の前で私の手紙を読み上げた。そんなことがあってから、担任の先生も嫌いになった。先生は、私の心の傷について心配していたそうだが、心底「どうでもいい」と思った。ただ、自分が心に傷を負うような事件に巻き込まれたのだと感じた。
当時住んでいたのは大阪市内だった。通っていた小学校の近辺は治安が良くない。言われてみると、毎月、学校のニュースレターには「今月は〇人ゆうかいされそうになりました。みなさん気をつけましょう」と必ず書かれていた。
夜に警察の人がふたり来た。日々を送る生活空間に警察の人たちがいる。あまりにもそぐわなかった。いろいろと話を聞かれるのかと思ったが、警察の人たちは五分ほど質問した後、「実は近所で変死事件が起こっていまして、そちらで今忙しくて」と謝り出て行った。
変死事件。「犯人は私を連れ去ろうとした人かな」とふと思った。再び恐怖が体中を駆け巡った。直後より、後になってからのほうが怖くなることもあるのだと知った。
怯えた私を見て、母がともちゃんのお母さんに電話をした。翌日から、毎朝ともちゃんが迎えに来て、いっしょに登校してくれることになった。ともちゃんも同い年の女の子なのに。大丈夫かな。そう思いつつも、親友のやさしさが嬉しかった。
次の日は、外に出るのが怖くて泣いていたが、ともちゃんが手をつないでくれたので小学校に行けた。
以来、引っ越すまで、あの階段を使うことはなかった。
「今、私はここにいなかったかもしれない」
 誘拐未遂事件…として扱われたのだろうか。その後、あの男…つまり加害者が捕まったかどうか知らない。記事を書くにあたり両親に聞いてみたが、二人も知らないらしい。「助かってよかった」という気持ちは日に日に強くなっていった。
誘拐未遂事件…として扱われたのだろうか。その後、あの男…つまり加害者が捕まったかどうか知らない。記事を書くにあたり両親に聞いてみたが、二人も知らないらしい。「助かってよかった」という気持ちは日に日に強くなっていった。
印象的な出来事がある。事件があってから3日後、家庭教師の大学生がいつもどおりうちに来た。きれいな女の人だった。11歳の私からすると、大学生は立派な大人である。彼女は勉強以外の話も聞いてくれるので、好きだった。休憩時間に、事件の話をすると、家庭教師は「うわあ」と声をあげた。
「そいつ、ロリコンやね」
ろりこん。知らない言葉だった。家庭教師のお姉さんが帰ってから、「ロリコンってなに?」と聞くと、母は激怒した。次から別の女子大学生が家庭教師になった。
「ロリコン」がどうしても気になる。ただ学校では場面緘黙症のせいで話せず、ともちゃんも「ロリコン」は知らなかった。親のいないときに、インターネットで調べて、その意味をようやく理解した。
そのときの衝撃を、大人になった今、どのように言語化すればいいのだろうか。「戦慄した」がいちばん近いかもしれない。
きもちわるい。
怖い。
二度と会いたくない。
後に私は、「セックス」という言葉の意味を幼なじみの女の子から教えてもらった。同時に「レイプ」の意味も知った。あの男は、幼い私をレイプしたかったのではないか。レイプした後、殺そうと考えていたかまではわからない。だけど、私の想像は間違っていない気がする。事件から20年以上経った今も、そう思っている。
加害者の男は、どうなったのだろうか。想像するだけで、11歳の頃の恐怖が生々しく蘇る。
性犯罪の判決が下されるたびに感じる悔しさ
心の傷は、後の性格や自分の将来に影響を及ぼしたかもしれない。事件の半年後、私は両親に「進学先は絶対女子校に行きたい」と自ら中学受験を願い出た。場面緘黙症は中学校に上がる頃には治っていた。中学生時代は不登校になったこともあったが、希望どおり中高大とすべて女子校に進んだ。
高校時代は「男の人とセックスしたことがある=かっこいい」という青春期ならではの価値観がクラス中に漂っていた。私はと言えば、街中でナンパされても怖くて無視してしまうし、物を買うときも店のレジ担当が男性なら買うのをやめる。きょうだいもいとこも、みんな女性だった。だから、クラスメイトから男の子の話を聞くたびに不気味さを感じて背中をまるめた。
大学2年生の終わりからアルバイトを始め、同年代の男性のバイト仲間と徐々に会話できるようになった。彼氏もできた。ただ異性と話すときはずっと緊張しているし、顔は真っ赤になる。「ぶりっ子」と女性店員の間で噂されていたらしい。もちろん、すべてが「事件のせい」と言い切れない。
だけど、あのまま逃げなかったら、今の自分はここにいなくて、両親や妹たちは被害者遺族として暮らしていたのではないか。だからなのだろうか。日本の性犯罪に対する判決が下るたび、悔しい。殺人罪もそうだが、あまりにも刑が軽すぎると感じる。被害者は人生を壊されたかもしれないのに。
あるドキュメンタリーとの出会い
 そんなことを思いながら、30代になった。最近、『塀の中の少年たち』というアメリカのドキュメンタリーを見た。おさえきれない感情があふれ出してきた。
そんなことを思いながら、30代になった。最近、『塀の中の少年たち』というアメリカのドキュメンタリーを見た。おさえきれない感情があふれ出してきた。
昔のアメリカは、未成年に対しても終身刑の判決が下されていた。だが2012年、法律が変わって、今まで少年時代に犯した罪で終身刑になった受刑者たちは再審請求ができるようになった。
『塀の中の少年たち』は再審を望む受刑者やその家族、被害者、遺族などを追ったドキュメンタリーである。彼らが罪を犯したのは未成年の頃だが、現在は40代以上になっている人もいる。
加害者やその家族は「判決が不当だ」と言う。被害者やその遺族の多くは「再審なんて許せない。また裁判所に行って傷をえぐられるのはいやだ。加害者には終身刑が妥当」と話す。これは善悪を決めるというよりは、視聴者が自分ごとにして、問いを深めるためのドキュメンタリーなのではないかと感じた。
『塀の中の少年たち』を見ながら事件のことを思い出した。あの瞬間、男の手を振り払っていなかったら、今の私はいなくて、男は「塀の中の少年」になっていたかもしれない。そして、日本では未成年の加害者にアメリカのような厳罰はくだらない。彼は捕まっても捕まらなくても、今、平然と街を歩いている可能性がある。
いやだ。
許せない。
被害者や遺族に事件を思い出すことを強いるのは残酷だ。だけど、私の場合は心の傷が比較的浅い。
被害者だからこそ、考えられること、伝えられることがあるのではないだろうか。
加害者はどうして罪を犯したのか
 ドキュメンタリー『塀の中の少年たち』をきっかけに「事件のとき、私を襲った加害者は何を考えていたのか」と、初めて加害者の背景に思いを馳せることができた。
ドキュメンタリー『塀の中の少年たち』をきっかけに「事件のとき、私を襲った加害者は何を考えていたのか」と、初めて加害者の背景に思いを馳せることができた。
もちろん、犯罪で被害に遭った方やその家族を含めたすべての人が辛い記憶を掘り起こす必要はないし、そんなことはしてほしくない。被害者やその家族が「加害者に厳罰を」と願うのはもっともだ。どんなに厳しい刑罰も、被害者が被害に遭う前に時を戻してはくれないのだから。
だが、犯罪を自分と切り離して考えている人たちには、できれば「犯罪が起きる前」のことを少し想像してみてほしい。私は、今もときどき11歳のときに起きた事件を思い出す。もっと酷い事件で心身を傷つけられた人の苦しみは想像もつかない。
理不尽な犯罪で苦しむ人を減らしたい。すべての犯罪を防げるわけではない。だが、何かが違えば起きなかった犯罪も少しはあるかもしれない。身の回りの誰かが、被害者、そして加害者にならずに済む道があったのではないだろうか。
そのヒントを見つけるために、次回は、『塀の中の少年たち』で取り上げられたいくつかの例を振り返ってみたい。これはアメリカのドキュメンタリーだが、国を超えて、視聴者が考えるきっかけを得られる映像作品だ。
このドキュメンタリーを考察することによって、「犯罪を未然に食い止めるためにはどうすればいい?」という問いを深められるのではと考えている。
あわせて読みたい












