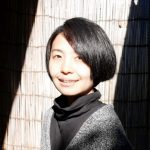「もう一度、地域の魅力を地域の人の手でつくりあげよう」。
そんな想いで始まった、青森県三戸町の「地域商社」づくり。「地域商社って何?」という手探りのスタートから、商品発表までのストーリーを行政側の視点で振り返った前編記事では、行政と住民、それに外部人材という三者の連携が生まれていった様子を届けた。
今回の後編記事では住民側の視点から見た「地域商社」立ち上げの過程に迫る。そこから見えてきたのは、不安と希望が混じりあったリアルな「町の未来」だった。
「よそもの」と「地元」の間で

(写真:右が吉田さん)
三戸町の地域ブランド「三戸精品」お披露目会が始まるおよそ1時間前のこと。
段取りの最終確認が行われる輪の中に、実行委員会メンバーの1人である吉田広史さんがいた。
福島県生まれの吉田さんが三戸にやってきたのは10年ほど前。Iターンで移住してにんにく農家を始めた彼は、インターネット販売やにんにく料理店「だるま食堂」の立ち上げなど新しいことにどんどん取り組む、三戸ではちょっと珍しい存在だった。
「農家は季節労働なので、安定雇用をするためには農作物をつくっているだけでは足りなかったんです。だから僕は畑にいるよりも営業に出ている方が多かった(笑)。さらにネットショップを始めて検索対策にいち早く力を入れたりも。とにかく、いつかやりたいと思っていたことを実現していきました」
挑戦の甲斐あって、彼の事業は成長を遂げる。その経験をもとに、今回のプロジェクトにも積極的にかかわっていくことに。
そんな彼は三戸の町の人たちや、そこで挑戦することについてこう語る。
「本当はやりたいことがあるけれど踏み出せない、でも背中を押されればできるかもしれない人たちなんです。ただ、人口1万人の町で目立ったことをするのには、それなりの覚悟もいる。自分は、ある意味アウェーだからできている部分はあると思いますよ」

にんにくの商品価値を上げたり、それまでになかったお店をつくったりということを通じて、地域に安定雇用をつくり続けてきた吉田さんは、「課題解決が趣味のようなもの」と笑う。
「受け入れられるためには結果を出すこと。結果を出すと周りの人が必要としてきてくれるようになります」
生産者の所得を上げていけるやり方を
今回立ちあがった地域ブランド「三戸精品」の中でも、特に中心で取り扱われた産品、それはリンゴ。「サンふじ」「紅玉」「百年紅玉」という3種類のリンゴが、ジュース、コンポーネント、ドライチップスなどに加工されていった。

そんなリンゴをつくっている生産者の1人として、実行委員会に参加したのが西野雄介さん。1983年生まれの若手だ。

西野さんは青森第二の都市、八戸市にある高等専門学校を卒業後、東京の建設会社に2年ほど勤め、その後地元に戻り測量会社に勤務。23、4歳の頃に「自分の体に一番合っている」家業の農業を継いだ。
何か新しいことをやらなくては…と考えていた中、町役場の佐々木さん(前編リンク)に声をかけられて、今回のプロジェクトに参加することになったという西野さん。当然、「地域商社なんて知らなかった(笑)」という地点からのスタートだった。

「5年くらい前から、変わっていかなくてはいけないという意識は持っていました。今までのやり方だと収入はそんなに多くないから、所得を上げていけるやり方をしなくてはいけない。家で作っているものを使って外に売れるものができたらどうなるか、やってみたいと思っていたんです」
変化への思いを抱えていた西野さんだったが、これまでは何かやりたいと思ってもなかなか実行に移すことはなかった。たまに若手同士の酒の席で盛り上がっても、結局は毎年同じことを繰り返していく…そんな日々に、変化をもたらしたのが今回のプロジェクトだった。
「やらない選択肢はなかったです。やっぱり、町がやろうと言ってくれたことは大きかったですね。それに外部の力も借りながらやったので、いい刺激になりました。最初はなかなか見えてこなかったけど、商品づくりに入ってからはみんなで意見を出しながら進められましたから」
売れなくて失うものはない
西野さんと話していると、時折、出来上がった商品に対して「生産者」という立場からのこだわりが顔をのぞかせることに気づいた。
「ジャムとかはいいと思います。でも、個人的にドライフルーツはあんまり好きじゃない。生産者としては生の方が絶対うまいぞって(笑)。これをきっかけに三戸町のりんごを食べてもらうきっかけになればうれしいですね」

(写真:お披露目会で商品の説明をする西野さん)
作り手と売り手では、知っていることに違いがあるという事実を、あらためて町内のメンバーが共有できたことも1つの収穫だった。商品づくりの段階から「もっと早く言ってくれないと、その時期にその品種はもうないよ」ということもあったのだとか。
せっかくいいものをつくっても、もし売れたとしても「欲しい」と言われたときに「ものがない」とは言いたくない…そんな意地が、生産者としての誇りなのだという西野さんは、今回の取り組みについて最後にこう語ってくれた。
「売れなくて失うものはない。ダメな場合を考えたこともない。ダメだったらダメだったでそこからまたやればいいだけです。これで三戸に興味を持ってくれて、行ってみたいとか、もっと違うものも欲しくなったりしてくれたらいいと思います。農家の後継ぎもいないなか、こういう加工品という形でそれなりの収入になれば、農家をやってもいいという人も出るかもしれないですし」

「三戸町は好きです。静かだし、落ち着くんです」と話す、西野さんの笑顔が印象に残っている。行政と住民がそれぞれにリスペクトしあって進む三戸町の「地域商社」づくり。ようやくスタート地点に立ったばかりのこの取り組みが、これからどんな未来を描いていくのか楽しみでならない。
【関連記事】
・四国の片隅、「居場所をつくるまち」の話-たった3人から始まった挑戦の今
・増税してでも守りたいものがある-「日本一小さな村」に子育て世代が集まるワケ
・元転勤族のモヒカンブロガー・勝手につくば大使が見つけた「地元の風景」
あわせて読みたい