「ないなら作ろう」。
シンプルな発想の中に、どれだけの可能性があることでしょう。
岐阜県恵那市で、地域の人々を巻き込みながら“泊まれる古本屋”「庭文庫」を営むのは中田実希さんと百瀬雄太さん。2017年に不定期での出張開催から始めた古本屋は、念願の「場所」を手に入れ、2018年4月から古民家での営業をスタートすることになりました。
「4月7日〜9日には東京の友人たちが古本回収の旅をするんです。東京から東海道を車で走って、集めた古本を庭文庫まで届けてくれるって。自発的に企画してくれたんですよ」

(写真:庭文庫を運営する中田さんと百瀬さん)
そんな中田さんの言葉の通り、たったひとりの発想から生まれた「庭文庫」は、たくさんの縁がつながって育ってきた場所でした。
今回のインタビューは、そんな「仲間と居場所」をつくるヒント満載のお話です。
「ないなら作ろう」で始まった庭文庫

‐出張古本屋として始まった「庭文庫」、なぜ始めようと思ったのですか。
もともと読書が好きなのに、私が移住した恵那市には古本屋がなかったんです。新刊を扱う本屋さんは3つあるのですが、べストセラー本が中心で私の好きなものは置いていなかったりとか。
もう1つのきっかけは、若い人との交流がなかったこと。
移住してから半年間は、本を読んだり、おばあちゃんたちの草木染めサークルに参加したりしていたのですが、若い人との交流がありませんでした。同世代で、本が好きな友達ができる場が欲しいなと思ったんです。
‐そもそも中田さんは沖縄出身なんですよね?なぜ恵那・中津川エリアに移住してきたんですか。
きっかけは、婚約者の百瀬(以下・ももちゃん、トップ写真左の男性)が恵那市出身だったことです。彼がたまたま東京に遊びに来ている時に友人の紹介で出会ったんですが、彼は既にUターンをしていて。
私は私でソローの『森の生活』という本をきっかけに、山や森の近くで暮らしたいと思っていたんです。なのでこれはもう移住しちゃおう!と。
‐ずいぶん思い切った決断でしたね!お仕事はどうしたんですか?
はじめは彼の実家に転がり込んで移住生活をスタートしたんですが、半年後、恵那市で地域おこし協力隊の仕事をはじめることになりました。
だから業務は市役所内の仕事が中心。地域の方とのつながりも限られているんですよね。
それで地域の方とつながる場を自分で作ってしまおうと考えて、出張古本屋を始めたんです。
2週間で出店準備。持ち主の軌跡が伝わる販売をしたい
‐「市役所の中田さん」が急に古本屋を始めるとなると、変わり者扱いされませんでしたか。
されましたね(笑)。はじめはなかなか周りに言いだせませんでした。草木染めサークルのおばあちゃんたちにも言えなくて。本当に仲良くなった人にこそっと言えるくらいだったんです。

そんな時、「おヘマガ」という恵那・中津川エリアのローカルWebマガジンを運営している園原さんという方に助けられたんです。
‐どんな方なんですか?
地域のハブのような存在です。Twitterで園原さんのことを知り、会いに行くことにしたんです。それ以来、庭文庫を応援してくれています。
地域のさまざまな方に、私の想いも話してくれているんです。彼女の知り合いに出会うと「あ〜、君が古本屋をやりたい子か!」と既に知ってくれていることもあったくらい。
‐ある意味、いつのまにか外堀を埋められていた感じもしますね(笑)。
そうなんですよ(笑)。古本屋をスタートさせたのも、園原さんの古民家オフィスなんです。3ヶ月に1回開催しているマルシェに出店させてもらいました。
2016年末に園原さんにマルシェでの出店を勧められて「まずは出張古本屋をやろう!」と決め、年が明けて2週間後には出店というスケジュール。その間にTwitterで古本募集のツイートを流して、ホームページも作成して、屋号も決めました。
‐話したことで一気にスピードが上がっていったんですね。告知はどうしたんですか。
当時、私のTwitterフォロワーは100人程度だったのですが、古本を募集するツイートが200リツイートくらいされたんです。
南は熊本から北は東京まで、古本が入ったたくさんのダンボールが届いて、約300〜500冊くらいの在庫が集まりました。
それをきっかけに月1回の出張古本屋を始め、地域の新聞にも取り上げていただきました。

(写真:先日行われた古本回収の旅「庭文庫への旅」で集まった古本たち。)
‐現在はどのような古本が集まって来ているのでしょうか。
小説や漫画、美術書なども集まって蔵書は約3000冊にもなりました。出張古本屋をやるうちに毎回「じゃあうちの本も!」と言って、地域の方に声をかけてもらえていて、回収にうかがわせてもらっています。
本にはそれぞれの方の個性が反映されています。美術書をくれた方は、昔海外によく行っていた方でした。各地で買い漁っていたら何千冊にもなってしまった、ぜひ庭文庫さんで売ってくださいという話をしてくれたり。
‐嬉しいですね!本自体もそうですが、人のつながりが膨らんでいく感じが素敵です。
本当にバラエティ豊かな本が集まっているので、もともとの持ち主の軌跡が伝わるような販売をしたいなと考えています。庭文庫を応援してくれる方の一人に隣の市に住む女子大生がいるのですが、その子にはポップを書いてもらったこともあるんですよ。
1年間の出張古本屋で、形づくられたコミュニティ
‐4月からは古民家で営業を始めるそうですが、もともと場所を持って古本屋をやりたいと考えていたのでしょうか。
出張古本屋を始める前から、この古民家とは出会っていて、ここでやりたいと考えていたんです。ただ大家さんとなかなか話がまとまらず、約1年間説得を続けていました。昨年の10月にやっと貸してもらえることになったんです。

開店準備として、2017年12月には古民家のお掃除会を開催。地域の方や県外の方にバケツやほうき持参で手伝ってもらいました。女子大生から60代の方まで、20名くらい集まったんですよ。
‐20名も!
大家さんは「うちから日当を払ったりお昼を用意してあげなくてもいいのか? 掃除道具も参加者に持ってきてもらうなんて、一体どういう会なんだ?」と驚いていました(笑)。
実際にはみんな「私、五平餅焼きますよ」「シフォンケーキ持ってきました」という感じで、盛り上げてくれて。
‐それはすごい…!みんな、なぜそこまで集まってくれたのでしょう。
前々から掃除イベントがあれば行きたいという声はあったんです。もし人が集まらなくても、私とももちゃんで掃除をする日にすればいいかなと思って募集をかけてみたら、意外と集まった、という感じでした。
‐最近、さまざまな方にお話をうかがう中で「助けて!」と声をあげるのが、逆に武器になのだなと感じることが多いのですが、まさに中田さんもその一人ですね。
たしかに、そうかもしれないですね。お掃除会の告知をするのも、最初は集まらなかったらどうしようかと考えていました。
園原さん、ももちゃん、五平餅焼いてくれる農家の方、古民家をしてくれた不動産屋の娘さんも来てくれるって言っている。5人いれば最低限いいかなと思って、開催を決めたら予想以上に集まっていただいて嬉しかったですね。

(写真:お掃除会の様子。)
「いつでもそこにある場」としての庭文庫
‐今後「庭文庫」をどのような場にしていきたいですか。
場所を持つことで「いつでもそこにある場」になるので、また新しい広がりを作っていけるといいなと考えています。
今までは出張という性質上、次の開催場所をFacebookで告知したり、ネットができない高齢の方には地図を書いたりしながら直接伝えたりしていました。場所を持つことで、SNSを見ない人でも訪れやすくなって、新しいつながりができるのではないかなと。
‐今度は「来てもらう」場所になっていくんですね。
また、これは構想段階なのですが、2018年秋くらいには宿泊もできるようにしたいと考えているんです。お布団を用意して、農家さんにご飯を作ってもらって、地域の暮らしを体験できる宿。これめっちゃいいじゃん!って思いついたんです。
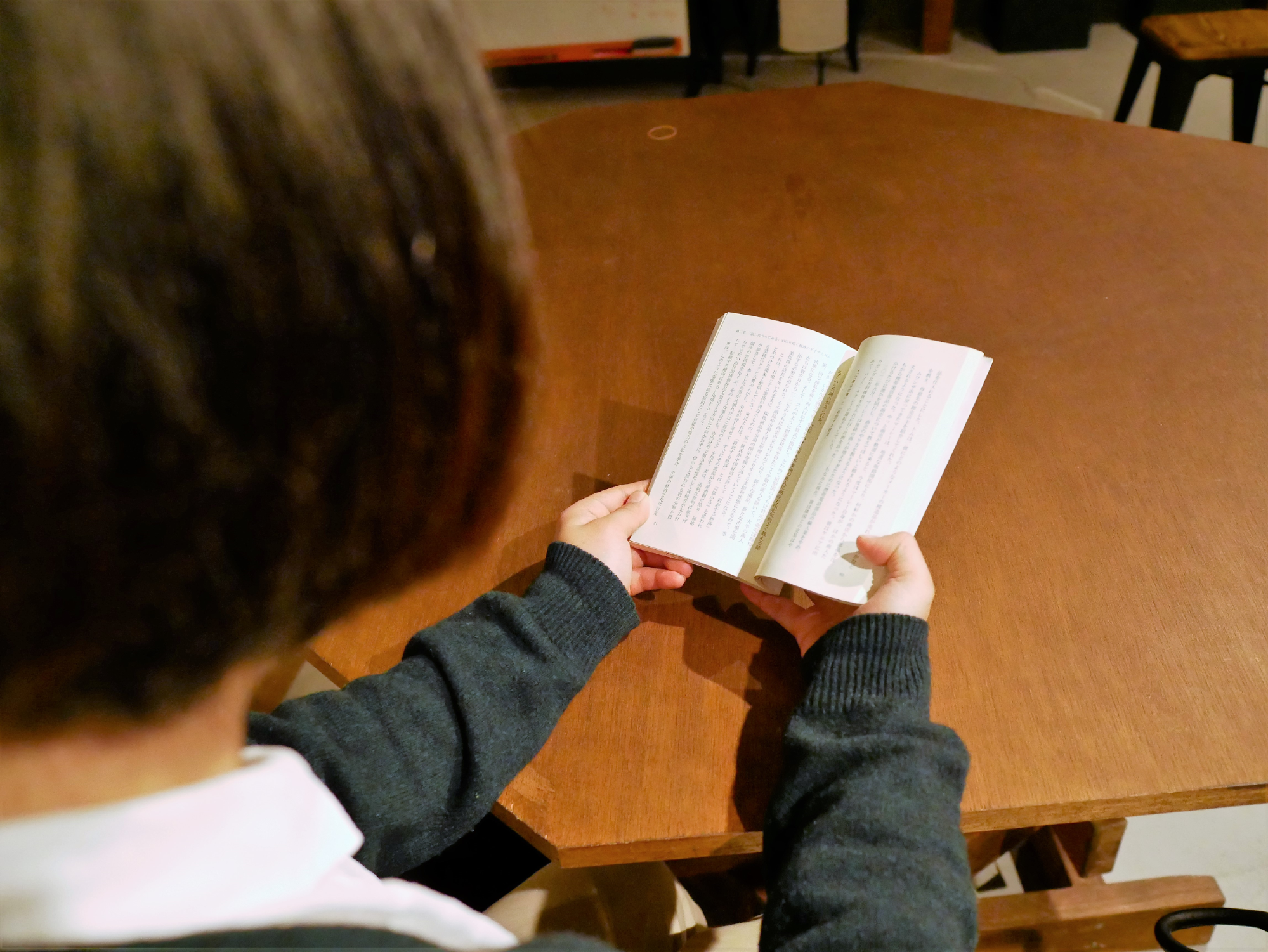
‐地域の暮らしを体験できる宿、素敵ですね…!
外から来る人も地域の人も「恵那市の自然、いいかも」「この町、好きかも」とゆっくり感じられる場所ってあまり私は知らなくて。特に、地域の方に恵那市のことを好きになってほしいなと思っています。
‐地元の人ほど、町の魅力に気づけていなかったりもしますものね。
移住してきた当初「何もないところによく来たね」と多くの方に言われたのですが、本当は恵那市の方も恵那市のこと、好きな部分はあると思うんです。それを謙遜せずに「ここっていいとこなんだ!」という光景を見たい。
庭文庫の運営については、ももちゃんと固く決めている約束があります。それは「楽しくやろう」ということ。私たちがしんどくなってしまったら意味がないですから。
楽しくやる、ということを忘れずにできたらいいなと思っています。

【関連記事】
・「月給3,000円」の息子へ―銀行マン、チョコレート工房をつくる
・生活と旅を一度に味わう「ローカルファストフード」の挑戦~取材、その後。
あわせて読みたい









