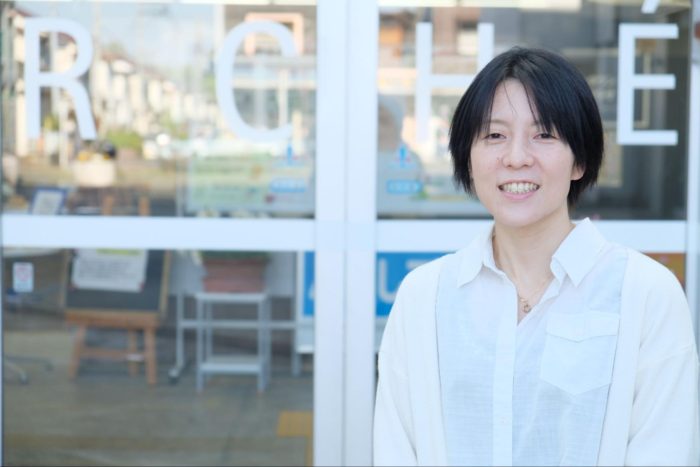地域とつながりながら、自らの手で仕事を生み出す。埼玉県比企郡に移住し、そんな「生き方」を選ぶ人々を紹介する本連載。
多様化する今の時代、「自分らしい生き方」に正解がないからこそ、多くの選択肢を知ることが生き方の模索につながるのではないか。「おもしろい人が集まる町」という噂を聞きつけて地域を巡ると、まるで70年代からタイムスリップしてきたようなカラフルな洋服に身を包んだ、ある女性に出会った。
鳩山町に暮らすアーティスト
今回スポットライトを当てるのは、2017年に比企郡鳩山町に移住した菅沼朋香さんだ。住民の集いの場となっている『鳩山町コミュニティ・マルシェ』のコーディネーターをしながら、元空き家である自宅を活用したアートプロジェクト『ニュー喫茶幻』の運営や、空き家の庭にある果実から作るお土産品『空家スイーツ』などの活動に取り組んでいる。
比企起業大学・大学院を運営し、地域の起業家育成に取り組む関根雅泰さんは、彼女についてこう語る。
「今でこそ、あえて比企郡を選んで移住してくる若者や、地域で何かやりたい!と意欲的な方が増えましたが、数年前は違いました。そんな頃から移住し、“おもしろい町”と呼ばれるまでの土壌を耕し続けてくれたのが、菅沼さんです」
関根さんの言葉を伝えると、菅沼さんは嬉しそうに「あの頃は泣いてましたね……」と遠くを見つめた。

「だって私、ニュータウンが嫌で嫌で仕方なかったんです」
ニュータウンとは、地方から都心へ人々が働きに出るようになった時代に、企業に勤める人々の住宅不足に対応するために建設された市街地のこと。切り開いた土地にきれいに家々が並び、人の手によってしっかりと計画されたことがわかる。
菅沼さん自身、愛知県の大規模ニュータウン生まれ、ニュータウン育ち。多様性からは程遠い、均一で同質のものが集まる町が大嫌いだった、と渋い顔で切り出した。
ところが現在、菅沼さんが移住し活動の拠点としているのが、『鳩山ニュータウン』と呼ばれる、同じように設計された町だ。定規で引いたような真っ直ぐな道に、同じ色形の家々が整然と並んでいる町並みは、生まれ育った場所にそっくりだと言う。
ニュータウンが嫌いだった彼女は、どうしてこの地に移住しアーティストとして活動する「生き方」を選んだのだろうか。

生まれ育ったニュータウンが“嫌い”だった
菅沼さんが移住してすぐに立ち上げを始めた『ニュー喫茶幻』は、「鳩山ニュータウンで夢がみれる店」として、移住者や若者が集い、飲食をしながら語り合う場所だ。空き家だった一軒家を買い取り、クラウドファンディングやセルフリノベーションの末にオープンした。
「ニュータウンって、基本的には会社勤めする人たちのために作られた町だから、自営業の人はほとんどいないんです。『ニュー喫茶幻』のように自宅を解放して、地元の人たちが集えるお店って、今までのニュータウンにはなかった場所なんですよね」
愛知県のニュータウンで、22歳までを過ごした菅沼さん。某大手企業に勤める人たちのために作られた町だったため、住民のほとんどが同じ企業勤め。学校も、同企業に勤める家庭の子どもばかりだった。
「子どもたちはみんな、『大きくなったら親も勤める某大手企業に就職すること』が夢で、成功の形としてベースにあるんです。他の仕事をしている人なんてニュータウンにはいないから。でも、私は全然そういう考え方じゃなかった」
「みんなと同じ」より「自分が好き」なことを表現したい欲が強かった子ども時代。周りが良いと思うものと、自分が好きなものとの差が埋められずに窮屈さを感じていたという。
「みんなが同じような家に住んで、同じような暮らしをして、同じような夢をみて。そういう“ニュータウン”っぽさが合わなかったんでしょうね」
幼い頃から表現することが好きで、絵を描いたり歌を歌ったり、学芸会で演じることも好きだった。その流れで高校は美術科のある名古屋の高校に進学、名古屋芸術大学を経て広告代理店に就職した。
「せっかく大学に行かせてもらったんだから就職しなきゃって頑なに思っていました。でも卒業制作ではアート作品を作って賞をいただけたこともあって、やっぱりアートが好きだなって想いもありましたね」
就職と同時に一人暮らしを始め、ついに“脱ニュータウン”を果たす。どこで、どんな暮らしをしてもいい。自由を手に入れた菅沼さんは、ここから自分らしい生き方を模索していった。

救ってくれたのは「高度経済成長期」?
「初めて一人暮らしをしたのが、名古屋の大須。商店街や古着屋さんがたくさんある賑やかな場所です」
お店を切り盛りしながら人々が暮らす商店街。多種多様なお店があり、店主もお客さんも、いろいろな人が混ざり合う活気溢れる町は、菅沼さんの肌には合っていたようだ。
「会社勤めの人が多いニュータウンとは対極のような町の雰囲気に、自然と惹かれましたね」
菅沼さんはその後、名古屋で一番古い商店街と言われている円頓寺商店街に引っ越し、さらに商店街の魅力にハマっていった。昭和の香りが色濃く残る商店街で、菅沼さんの心を射止めたのが『昭和レトロ』。苦しかった会社員の日々を癒してくれたのは、純喫茶であり、レトロな洋服であり、切なげな歌謡曲だった。
昭和レトロ熱は収まることなく、その後会社を辞めて名古屋芸大の助手をしながら、スナックでバイトを始めることに。当時の様子を、写真と共にこう振り返った。
「髪型も『八代亜紀にしてください』って美容院に写真を持っていって、パーマして。昭和レトロを満喫していましたね」
カラフルな花柄のシャツを来て、昭和を彷彿とさせるアイテムに囲まれながらそう話す菅沼さん。昭和レトロの何が、彼女を夢中にさせたのだろうか。

「町中に残る昭和らしいものを探すようになると、多くは高度経済成長期に作られたものだったんですね。高度経済成長期って、テレビや冷蔵庫などの暮らしを豊かにする家電が初めて庶民でも買えるようになった頃。未来はどんどん良くなるんだって信じて疑わなかった時代だったと、私は捉えているんです」
経済が上向きで勢いがあり、人々が明るい未来を描いていた時代。その明るさに菅沼さんは元気をもらい、励まされたのだ。また、兼業農業も多かったこの時代は、自然とともに生きていた人々が今より多かったとも語る。四季折々を楽しむ気持ちが、この頃に流行したカラフルな色合いや花模様に表れているんじゃないか、と愛おしそうにコップを見つめた。
しかし、明るい時代は徐々に形を変えていく。大量生産された商品が多くの人の手に行き渡ったあと、多くの企業は伸びた売上を落とさないためにあの手この手で商品を売ろうとした。買い換えを促進したり、価格を下げるために人件費を削減したり、過激な広告宣伝をしたり。そういった方向性の移り変わりを、菅沼さんは「過剰な大量生産・大量消費」と表現し、問題提起をしている。
「人々の暮らしや社会が良くなっていった高度成長期の最初の頃は、消費と生産のバランスがよかったんじゃないかなと思っていて。『今は忘れられてしまった、昔あった大切なことを現代に取り入れよう』とアートで提案したいと思うようになったんです」
芸大の助手をしていた3年間、学生と一緒に展示やコンペに参加するなど自身の作品づくりにも取り組んでいた菅沼さん。自身の考えを表現し、社会課題を人々に伝えるのに、アートは欠かせないものになっていた。
テーマはもちろん、自分を元気づけてくれた高度経済成長期。あの明るい時代から失われてしまったものを、現代に取り戻す。その過程自体をアートプロジェクトとして捉え、映像や作品におさめていった。

舞い戻ったニュータウンで
アーティストとして生きたい、自分の作品をもっとしっかり言語化したいという想いから東京藝術大学へ進学。その後、鳩山ニュータウンに移住する運びとなるのだが、その出会いは全く予期せぬ偶然だった。修了制作展で展示していた『ニューロマン』を見た、建築家で東京藝術大学建築科准教授の藤村龍至さんが、自身が関わりのあった鳩山ニュータウンへの移住を勧めたのだ。
「ニュータウンって高度成長期が生んだものなんですよね。都市に集中したサラリーマンの住む場所として切り開いた町だから。藤村さんいわく、私自身がニュータウンの出身だからこそ、ニュータウンを題材に作品を作ることが成長につながるんじゃないか、と」
もともと、仕事のために都会に住み続けることに疑問を感じ、地方への移住を考えてはいたという菅沼さん。しかし――。
「本当に本当に嫌だったんです、私。ニュータウンが嫌いでようやく出てきたのに」
幼少期に体感した窮屈さが蘇る、とでも言うように顔をしかめる。しかし葛藤はありながらも、アーティストとしての好奇心があった。
「めっちゃ嫌だけど、藤村さんの言う『自分の作品にニュータウンを取り入れる』っていうのは確かにそうだなって思うところもあって。時代ってつながってるんですよね。高度成長期は好きなのに、そこから地続きのニュータウンはなぜ嫌いになっちゃうのかな、という疑問もありました。私自身のルーツでもあり、高度経済成長期に生まれたニュータウンと向き合って作品化してみたいという想いが強くなりました」
熱心な藤村さんの誘いや良い大家さんとの出会いなどもあり、鳩山ニュータウンの一軒家に引っ越すことに決めた菅沼さん。移住してみると、“均一で多様性がない”というニュータウンのイメージとは少し違っていたという。
「鳩山ニュータウンの特徴は『みんなが、わざわざここを選んでいる』っていう点なんですよ。初期の頃のニュータウンは、社会の大きな流れに乗って人々がバーっと流れ込んできていたんですけど、遊ぶところもなくて都心から離れているニュータウンに、今はあえて住もうと思わないですよね。だからこそ若い世代は特に、子育てなり仕事なり、何かしら自分の価値観を持ってこの町を選んでいる人が多いんです」
高齢化・人口減少などの課題はありながらも、人数の少なさから異業種や他の活動をしている人とつながりやすいことも良い点だという。菅沼さんも、鳩山町コミュニティ・マルシェで働くうちに多様な人々とつながり、ときがわカンパニー合同会社が主催する比企起業塾(現在は、比企起業大学・比企起業大学院)に入ったことで大きく世界が広がった。
「アーティストとして生きていくためにはどうしたらいいのか。それを真剣に考えることが始まりましたね。ビジネスを手段として使うことで、“アート”と“人”はもっと関わりしろが多くなるっていうことがわかったんです」

また、自宅兼喫茶店である『ニュー喫茶幻』をニュータウンの真ん中で開いたのにも菅沼さんなりの理由がある。
「ニュータウンってお店が全然ないし、自分で何かをやる人があんまりいない印象があったんです。このお店で人が出会って、おもしろいつながりを生めたらいいな、それをきっかけに自分で活動を始める人が増えたらいいな、というのをコンセプトにしていて。ニュータウンが単なるベッドタウンとしてではなくて、多様な活動をしている人たちが生まれる場所になったら、個々が自立して賑わいのある町になっていくと思うんです」

新しい風が吹く、新しい町
「菅沼さんは、人を引きつける力がすごいんですよね」
ニュー喫茶幻に集う、移住者の若者はそう言う。鳩山町を“おもしろく”する開拓者として自身のアート活動とニュータウンでの生活を模索してきた彼女の元には、移住を考える人や何かを形にしたい人が訪れ、菅沼さんもまた彼らから刺激をもらいながら活動を続ける。
そんな彼女に、これからやってみたいことを聞くと、やはりアート作品としての活動を見据えていた。
「学生時代は苦手だったニュータウンに、今あえて選んで暮らしている。それならば今度は、自分の手で自分が暮らす町をどう楽しくできるか?それがここでの挑戦だと思っています。ニュータウンに馴染めなかった経験があるからこそ、『こんなものがあったら地域は楽しくなるんじゃないか? 』と思うものをアートを通じて形にしたい。人々が集う場を作ったり、自分の手で仕事をつくる働き方をしたり。それをもって、まさに『昔あった大切なことを取り入れて、現代をもっとよくする』につながってくる。それが私のニュータウンでの生き方かなって考えています」
時代はつながっている。菅沼さんが惹き込まれた高度経済成長が、学生時代に窮屈な思いをしたニュータウンを生んだ。そのニュータウンも時代が移り変わるにつれ、空き家や高齢化が進み、そこへ舞い戻った菅沼さん。今度は“アート”という自分のやりたいことで、苦手だったニュータウンに新たな風を運び込んでいる。
少しずつ変わり始めた鳩山ニュータウンがこれから作っていくのは、どんな時代なのだろう。きっと「みんな同じでつまらない」なんて誰にも言わせないような、“新しい町”になっていく。
あわせて読みたい